対談:橋本 治 × 浅田 彰「日本美術史を読み直す」
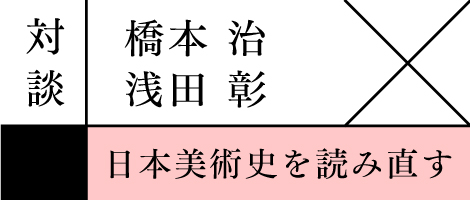
2019年1月29日、小説家で批評家の橋本治氏が亡くなった。その仕事のひとつに、日本美術史を独自の視点で読み解いた『ひらがな日本美術史』(全7巻)がある。シリーズが完結した2007年に、批評家の浅田彰氏との間で交わされた対談を、追悼の意を込めて転載・公開する。

写真提供:新潮社写真部
私の中に「奇」はない
浅田 お久しぶりです。二十五年くらい前に、『広告批評』が紀伊國屋ホールで開いたシンポジウムで、オブザーヴァーと称して隣どうしに座らされて以来ですよね。
橋本 あれは何だったんですかね。僕はオブザーヴァーになってくださいって言われた記憶もないんですよ。客席にいてくださいって言われて、何か最後に言ってくださいって言われて、すごく過激なことを言ったという記憶だけはあるんですけどね。
浅田 ぼくはそのとき、橋本さんのデビュー作「桃尻娘」が雑誌に掲載されたときからのファンだと言ったんですけど、あれ以来、橋本さんは、元祖ひきこもりという感じで部屋にこもりながら、膨大な仕事を積み上げてこられた。ぼくはあちこち出歩きながら仕事らしい仕事もせず、ファンと言いながら橋本さんの仕事をきちんとフォローすることさえできずにいるありさまです。ともあれ、橋本さんは、その仕事の一環として、古事記から源氏物語や平家物語を経て南総里見八犬伝に至るまで、いわば日本というものを自分で改めて書き直すという途方もない企てを実行してこられた。このたび完結した『ひらがな日本美術史全七巻』(新潮社刊)もその一環で、これまた埴輪から東京オリンピック・ポスターまでの日本美術史を全部自分で書いてしまうという途方もない企てです。「みんな日本について知らなさ過ぎる」と言う人は多いけれど、だからと言って「じゃあ自分が日本を全部やっちゃうよ」という人はまずいない。橋本さんのその気力は一体どこから来るんでしょう。
橋本 「やっちゃうよ」じゃなくて、『ひらがな日本美術史』の場合は、「やっていいんだったら」なんですよ。私が自分からやりたいっていったのは、枕草子(『桃尻語訳枕草子』)と源氏物語(『窯変源氏物語』)と平家物語(『双調平家物語』)だけなんです。この仕事はいきなり「芸術新潮」の編集者に「美術史を書いてください」と言われて、「やっちゃうよ」じゃなくて「やらないとわからないだろう」と思って引き受けました。人がどれだけ知らないかは、大体分かるんですよ。じゃあ自分はどれだけ知っているかになると曖昧だから、取り敢えずやってみた、とそんな感じですね。
浅田 橋本さんはやっぱり職人だと思うんです。自分でやってみて分かる、そこで分かったことには絶対的な確信をもつ、と。一方で「漢字日本美術史」というべきものも世の中にはあって、専門家がやたら難しい用語で決まりきった日本美術史のメイン・ストリームを語り続けている。そちらが「源平盛衰記」なら、こちらは「ひらがな盛衰記」なんだ、職人として勝手に逸脱しながらつくっていくんだ、というのが、この本のコンセプトでしょう。ただ、今回通読してみて思ったのは、そういう建前でありながら、実際にはこの本はものすごく正統的に日本美術史のメイン・ストリームを呈示しているな、ということです。
世の中では、ここ三〇~四〇年というもの、どの領域でもリヴィジョニズム(歴史修正主義)が広がった。昔は例えば江戸時代の絵画なら土佐派・狩野派・円山派なんかがメイン・ストリームだったのに対し、一九七〇年に辻惟雄の『奇想の系譜』が刊行され、伊藤若冲とか、曾我蕭白とか、あるいは歌川国芳とか、それまでの主流から落ちこぼれたところにヘンな人たちを見つけて面白がる風潮が出てきた。西洋美術史で、セザンヌからキュビスムへというメイン・ストリームに対し、高階秀爾なんかが象徴主義やアール・ヌーヴォーなんかをジャポニスムがらみで評価したのも同じ文脈だと思います。最初は、そういう仕事には、メイン・ストリームをひっくり返すという意味で大きなインパクトがあったかもしれない。けれども、それ以来、主流派の「大きな物語」なんていうのはどこにもなくなったにもかかわらず、彼らの弟子たちも同じように路傍の異端の花々を探すようなことばかりやっている。そんな中で、実は『ひらがな日本美術史』が一番真っ当なメイン・ストリームを呈示しているというところが、とても面白いと思うんです。例えば円山応挙はなぜいいのか。松の絵なんかはダメだけれど、子どもの絵はなぜあれほど生き生きしているのか。それは応挙が一八世紀市民社会の画家だったからだ、と。そんな真っ当なことを言っている人はいまやどこにもいない。
橋本 辻惟雄先生の『奇想の系譜』が刊行されたのは私が大学生の頃で、当時はやはりオッと思ったんです。でも、そのすぐ後で、『奇想の系譜』関連の展覧会があって、そこで曾我蕭白の《群仙図屏風》を見て、これ好きじゃない、《商山四皓図屏風》のほうがずっといい、と思ってしまったんですよ。それに私は、歌川国芳を奇想だと思わなかったんですね。これは私にとってはオーソドックスなものであるし、これをオーソドックスだというところからスタートする美術史というのがあってもいいんじゃないか、初めからやればそれが整理できるかな、と思って書いたところもあるんです。だから、もう奇をてらうもへったくれもない。私のなかに「奇」はないのね。「これもいいあれもいい」の、イーブンであるというところから考えはじめて、なんとなく宙に浮いているもの二つを、この同じ宙の浮き方で二つは繋がっているんじゃないの、という風に書いたのがこの美術史なんだと思います。
弥生的なものこそ
浅田 『ひらがな日本美術史』では、前近代が終わったところで一種の仕切りなおしがあり、弥生的なものを改めて日本美術史の枠組みとして設定し、縄文的なものを「奇」として面白がる岡本太郎的なポーズを排除するわけでしょう。ある意味で定番と思われている弥生的なものこそ、ヘンなものを自由に取り込みながら、日本美術史のメイン・ストリームをつくってきた。そっちのほうが主観的な好き嫌いを超えていいんだ、主観的に面白いとかいうんじゃなくたんにいいからいいんだ、という宣言をしている。全面的に賛成するかどうかは別として、潔い態度だと思いました。「俺は反動だ」と言っているのに近いところもあるわけだから(笑)。
橋本 潔い決断をしちゃったから、困っているんですよ。その後、分からなくなったのは、「弥生の器を捨ててしまったあとには何があるの?」ということ。もう一度、弥生の器の中に何か入れるにしたって、壊れているものの中には入らないんじゃないか、という問題がある。例えば、柳宗悦、河井寛次郎、北大路魯山人がしたのは弥生的な器のなかに何かを復活させようという動きなんだけど、それって美術史全部をフォローしようとするようなものじゃないから、ある時代のディレッタントな営みにしかならないんですよね。でもじゃあどうすればいいの、ということになると私分かんないんです。
浅田 例えば丹下健三は日本における近代建築のパイオニアということになっているけれど、広島平和記念資料館なんかはまさに弥生的なんですよ。細い木の柱を、コンクリートの打ち放しでいかに繊細に模倣できるか。当時、そういう弥生的=公家的なものに対し縄文的=民衆的なものの方に向かうべきだという議論があり、世界の建築界でブルータリズムが流行ったこともあって、丹下健三もそちらに傾斜するわけだけれど、全体としてみるとやっぱり弥生的なんですね。だから、弥生的な器が壊れたかに見えても、近代建築のもっとも荒っぽいところまでそれが続いているようにも見える。まあ、それが現在の建築にまで続いているのかどうかといえば、微妙ですけどね。
橋本 『ひらがな日本美術史』で、逃げちゃったことがいくつかあるんですが、近代に関して、建築からは逃げましたね。近代の建築に必然があるんだろうか、ということになるとよく分からないんですよ。建物として、そういうものを造らなければいけない必然はあるだろう、しかし、あれは日本人の美的な必然と合致しているものなのか、ということになると私は大疑問なんです。例えば東京駅をみれば、嫌いじゃないよなと思うけど、嫌いじゃないよなと思うことと、美術史のなかでどう位置づけるかということになるとまったく別なんでね。美術史の流れそのものがまったく違う。横山大観、菱田春草系の近代日本画を『ひらがな日本美術史』から外しちゃったというのも同じなんだけども、そういう流れがやってくるのは分かる、やってきたのをどう処理したのかも分かる、でも何かそれに意味があったんだろうか、ということになると、分かんないんですよ。
浅田 江戸の職人、橋本治としては、ある意味で当然の選択だろうと思います。ただ、たまたま橋本さんの連載中に刊行された、磯崎新の『建築における「日本的なもの」』や、磯崎新と福田和也が日本各地の建物を行脚した『空間の行間』なんかで、興味深いパラダイムが提起されている。日本史においては、外圧があって内乱が起きると、橋本さんの言う弥生的なものが揺らいで、とんでもないものが出現するんだけれど、それがまた和様化されて弥生的なものに戻るというパターンがある、と。具体的に言えば、白村江の戦いと壬申の乱、元寇とその前後の内乱、鉄砲やキリスト教の伝来と戦国の乱、黒船と明治維新ですね。その中でも特権的に取り上げられている建築物が、『ひらがな日本美術史』にも出てくる重源の東大寺南大門で、そこには磯崎新の、近代建築を本気でやるならああいう構造がむき出しになったようなものを屹立させたい、という気持ちが、明らかに透けて見える。だけど実際は、南大門のようなものはなし崩しに和様化されて弥生的になってしまうんですね。
橋本 つまり、弥生化というのは卑小化だということでもあるわけでしょ。
浅田 卑小化というか、外からのインパクトを融通無碍に散らして、やんわり受けいれる、と。それに抗って、インパクトを直接受け止めるようなもの、それ自体もインパクトのあるものが出来るかどうかというのが、磯崎新の問いだと思うんですね。だから、橋本さんの弥生的な構造が本流だという言い方と、磯崎さんのそれにどうやって抗えるか(ただし岡本太郎流の縄文的な「爆発」によってではなく)という問いは、背中合わせになっているとも言えるんじゃないか。
橋本 私にとって、弥生的だというのは、これはいいと思う、これもいいと思う、これもいいと思う、と「いい」が並んでくると、この「いい」の間に何か共通しているんだよな、ということなんですよ。言ってしまえば、縄文的なものっていうのは常にちょろちょろ湧いてくるんだけど、結局それを洗練してしまうのが日本美術であって、その洗練するという行為を弥生的って言ってしまえばいいのかな、というくくりなんですね。そう考えると、近代以前は洗練する時間的な余地があった。でも、近代以後になると洗練する余地がなくなった。だから、年寄りよりも若者がやることのほうがいい、となってしまったんだと思います。
浅田 幼児的な前衛芸術家気取りというのがあって、彼らは「近代では何でも新しいほうがいいんだ」と思い、つねに新奇なショックを生み出そうとする。それに対して、江戸の職人である橋本治は、大人の職人として成熟するということを言い続けている。それはよくわかります。ただ、その上で僕は、一方で新しいものをどんどん使い捨てながら、他方で弥生的なものが支配的なイデオロギーとして今もずっと残っている、という気がするんですね。
橋本 でもそれは、いい弥生的なものが残っているのか、それともこれがいいものだという思い込みが残っているのかってところで、微妙じゃありませんか。
浅田 それはそうです。
橋本 そういう線引きもなんか嫌だって思って、それで『ひらがな日本美術史』の近代篇はあっさり終わらせてしまったんですよ。そういうことを入れていくと、ひらがなじゃなくなって、アルファベットになってしまうんです。
本居宣長的な構造
浅田 たしかに、橋本治日本美術史のいいところは、退屈だけれどもいいものだということを、はっきり言っていることだと思います。狩野派は、唐絵とやまと絵を織りまぜて、いわば和漢混淆文のようなものを作った、それこそが日本画のマトリクスになりえた、と評価されているところや、さっき言ったように、円山応挙を一八世紀の近代日本画の祖として評価するところですね。
それに対し、「奇想の系譜」だけを追いかけるのはやはり問題がある。だいたい、伊藤若冲が忘れられた画家だとかいうけれど、あえて京都人として言わせて貰えば一回も忘れられたことはないと思うし(笑)、現に夏目漱石の『草枕』にも出てくるぐらいでしょう。曾我蕭白はたしかに忘れられていたかもしれないけれど、あれはやはりゲテモノと言われてもしようがない、その上であえて面白がるかどうかというようなものだと思うんですね。やはり、いかに退屈ではあっても、土佐派があり、狩野派があり、円山派があり、というまともな美術史をわかっていないと、日本美術史の面白さはわからないんじゃないか。そこは橋本さんと同感なんですよ。
橋本 ゲテモノという言葉がなくなったのは問題だと思う。ゲテモノはやはりゲテモノなんですよ。人は時々、ゲテモノが好きになる。基準が二つあるってことがいいんであって、ゲテモノだから全部いいということはない。
浅田 ちなみに、和漢混淆文の話をきっかけとして、先ほどの磯崎新パラダイムをさらに敷衍すると、柄谷行人の『日本精神分析』や石川九楊の一連の漢字論のような議論があるでしょう。まず漢字を受容した上で、そこから仮名を作り出す。ところが、仮名は漢字から派生したものであるにもかかわらず、仮名こそ日本人本来の自然な心情を表現するのに適している、
橋本 そういう議論について言うと、ルーツについて、一個わかるとそのキイによって全部がわかるという考えかたは、あまりにも単純すぎないかっていうふうに私は思うんですよ。ある部分ではAというタームを持ち上げ、別のところにくるとAを否定しつつBというタームを持ち上げ、とそれでいいんじゃないか。
大体、漢意とやまとごころという概念は、それを言い出した本居宣長が、いろんな方面からせっつかれた末、自分のありかたを守るために言い出した防御の言葉なんじゃないか、という感じがしているんです。じゃあ漢意とやまとごころをどう線引きなさるんですかと突っ込まれた時に、宣長はちゃんと答えたのか、答えたとしてもそれが正しいかどうかは分からないじゃないかと思ってしまう。それよりも重要なのはやまとごころと漢意という概念を出してきて、それで本居宣長が守りたがっていたものは何なのか、ということなんですけど。
浅田 本居宣長に対して上田秋成が、オランダわたりの世界地図を見て、日本というこんな極東の島国に太陽神が降臨したなんてありえないとか、子どもみたいにストレートな議論をする。それに対して宣長が、いや、そういう言い方そのものが漢意なので、素直に古事記と向き合うということが君にはわかっていない、などと言う。橋本さんの言われるように、すごく屈折したディフェンスというか……。
橋本 それ以前に、宣長に人に説明しようという気がないんだと思う。だって、あれで分かれというのは無理ですよ。
浅田 小林秀雄と坂口安吾に「伝統と反逆」という有名な対談がある、あれも同じような構図でしょう。安吾は子どもみたいにストレートなことを言う。小林の骨董趣味を批判する一方、小林の評価する梅原龍三郎なんて「奇型児」じゃないか、と。それに対して小林は、「奇型児」と言えば「奇型児」かもしれない、しかし、それは日本で洋画を描くことからくる宿命なので、その意味では「奇型児」でいいじゃないか、と。それで「奇型児だって遂に天道を極める時が来るのかも知れない」なんて強弁するわけです。僕自身は、上田秋成や坂口安吾のように突っ張るべきだと思う。だけど、彼らが相手にしている本居宣長的あるいは小林秀雄的な構造というのがすごく強力なものだし、いまも持続しているということは、きちんと見なければいけないと思うんです。
橋本 多分、私は坂口安吾や上田秋成の言うことのほうがよく分かり、小林秀雄や本居宣長の言うことのほうが分かんないんですよ。ただ、小林や宣長が何を問題にしてたのかは分かる。分かるんだけど、その分かることをこっちに分かるように説明してくれないかなというのがあって、彼らがその言語を持ち合わせていないのか、その必要を持ち合わせていないのか、多分両方だと思うんですけど、結局それはまだそんなにオープンになれない時代のせいなのかなあと思うんです。だって普通に考えれば変じゃないですか。江戸も京都も好きな宣長が、音曲が花盛りの時代に、なぜ和歌だけがいいとしたのか。そういうところで、宣長がたまたま和歌が好きだった、ということではなんで悪いんだろうと考えちゃうんですよ。
浅田 とにかく、和歌や源氏物語のようなものこそ国学の精粋だということになっているわけでしょう。やたらと道徳的な議論をするのは漢意にすぎない、仮名で日本人の心情を綴った源氏物語はどうしようもない乱倫の話ではあるが、それを平然と肯定するのがやまとごころだ、と。ある意味でめちゃくちゃな話ですよ。でも、上田秋成なんかと対応する中で、本居宣長はどうにも硬直した居直り方をしてしまう。小林秀雄も最終的にそういう居直り方を反復しているところがある。あれはちょっといやなんですね。
橋本 小林秀雄が「源氏物語」をどう思っていたのかがさっぱり分かんないんですよね。で、本居宣長を問題にし、「古事記伝」を書く宣長を問題にするが、なんでこの人は「古事記」そのものをまったく問題にしないんだろうって、そこもよく分からない。小林秀雄は別に「古事記」も「源氏物語」もどうでもよかったんじゃないのか。あの人は自分の関心のないものに関してはどうでもいいといって退ける人だったんじゃないだろうか。問題は、その退けたものの中に結構いろんなものがあるんだから、小林秀雄を否定するつもりはないけど、他もありということにしてくれないかな、というだけなんですけど。
浅田 「古事記」自体はさておき、漢意を捨てて「古事記」に素直に向かい合う本居宣長がいるとか、あるいはその「古事記伝」に素直に向かい合う私がいるとか、結局そういう話になっちゃうんですね。
橋本 私、一応、大学時代に国文科の学生だったんで、時々とても不思議な感じに襲われるんですよ。最近若い人から、「国文学というのは本居宣長の国学から始まった」と言われ、別の人からは、「あなたの言うことは定説とは違うけれども」と言われてね。「定説とは違う」と否定されてるわけではなくて、相手はとまどってるんですよ。だから、両方合わせてびっくりしました。本居宣長という人は定説に縛られないで、自分の感性で考える人だったはずなのに、その人をルーツにしていつの間にか定説というものが出来上がっていて、それと違う考えかたをすると変だということになったのは何故?
という感じなんです。
骨董屋の丁稚の手習い
浅田 そういえば橋本さんは大学時代、美術史の山根有三の研究室に居候的に押しかけていたんですって?
橋本 山根先生の美術史のゼミというのがあり、私、国文科で美術史ってなにをやるんだろう、という野次馬気分で顔だしたら、教職課程のカリキュラムのせいで、ほかに生徒がいなかった。美術史の学生も全部よそに行っていた。で、なりゆきで山根先生も美術史専攻じゃない学生の私に美術史を教えるというゼミをなさったんです。
浅田 じゃあ、一対一だったんですか。
橋本 そうです。障壁画の図版を三つ出してきて、「この中に一つ本物があります。それはどれでしょう」とか「この五つのうちに二つだけ本物があります。どれでしょう」とか、幼稚園の入園テストみたいなことやっていました。その時に山根先生に「貴方は目が確かですね」って言われたんですが、私は、学校に入って先生に褒められたのは、おそらくそれが最初です。それで、結局、自分の目でみればいいんだっていうように、体が理解しちゃったから、その後なんの話も聞いてなかったんですけどね(笑)。
浅田 いや、それはすごくいい教育だったんじゃないかな。
橋本 だけど私は教育の原点でしか教育受けてないから、分かんないんですよ、そのさきの複雑な話が。
浅田 知識だけの教育が多い中で、とにかく自分の眼で見ることに自信をもたせるというのは、素晴らしいと思う。ある意味で骨董屋の丁稚の手習いみたいなものですよね。
橋本 でも、職人教育には、ぴしっと手の平をひっぱたかれるというのがあるじゃないですか。ひっぱたかれないところが学問ですよね。
浅田 僕の両親は三島由紀夫と同い年で、敗戦の時に二十歳だった世代なんだけれども、京都大学の学生仲間と、森
橋本 毛利菊枝って、「新諸国物語 紅孔雀」の黒刀自をやった方ですよね。
浅田 そうそう。僕は子どもの頃から時々その会に付いていって、神護寺の曝涼(虫干し)を見せてもらったり桂離宮を見せてもらったりしたんですよ。最近のリヴィジョニズムから言えば、森暢は古臭いモダニストということになるのかもしれないけれど、実物に触れながら一定のパースペクティヴをもった話をしてくれた、それはとても貴重な体験だったと思う。面白主義でヘンなものばかりつまみ食いさせられるよりいいでしょう。
橋本 古い日本のものを近代以後の日本人が見て、引き出せるのはモダニズムだけだと思うんですよ。『ひらがな日本美術史』でやったのも、結局は古いものの中から今に通じる何かを引き出したい、ヒントをもらいたいってことなんですよね。逆に言えば、温故知新じゃないけど、昔のものの中から何か引き出してくる能力というものを失ってしまうとなんにもなくなってしまうよ、というのが私の今の日本に対する危機感です。
浅田 まったくその通りですね。ともかく、米倉迪夫が『源頼朝像―沈黙の肖像画』で説いた、神護寺の《源頼朝像》は実は頼朝ではなく、足利尊氏の弟の足利直義の肖像だという説は、なかなか説得力があるけれど、個人的にはあれが頼朝像であってほしいなあという気はする(笑)。森暢は、昔、歩いて神護寺に通って、古文書を解読し、あそこに頼朝像や重盛像や光能像があったということを確認するんですね。ちなみに、ある説では、院政期は男色が盛んだったし、後白河法皇はバイセクシュアルだった(という表現もアナクロニスティックだけれど)から、後白河法皇の肖像を囲んで彼の寵愛した男たちの肖像が並ぶようになっていた、それが頼朝像や重盛像や光能像だ、とも言われる。とはいえ、あの《源頼朝像》が古文書にある頼朝像に対応するのかどうかは、確かにわからないわけです。僕らはそう思い込んでいるけれど……。
橋本 そういう刷り込みが出来てしまっていますよね。
浅田 それこそ安田靫彦の《黄瀬川陣》にも、あの《源頼朝像》そのままの頼朝が出てくるから。
高橋由一の可能性
橋本 ただ、本音をいうと、私は安田靫彦の《黄瀬川陣》の中の頼朝はあんまり好きじゃないんです。近代の日本画の最大のネックは、その人のもっている嫌な部分が描けない。なんかみんないい人になるんですよね。「これをいい人と思え」だとか。昔の絵は、いいも悪いもなくて、その人の微妙な、嫌な人かもしれないっていうニュアンスも同時に伝えてくる。それは写実のせいではなくて、対象把握のありかたそのものが違うんだろうと思うんですけどね。
浅田 《黄瀬川陣》について言うと、頼朝と義経の感動の再会を描きながら、しかし兄はこの弟を戦略的に使い捨ててやろうと思っているかもしれないという感じにも見えて、それを一九四〇年から四一年という時期に描いたというのは、一種の戦争画として見ても面白いと思うんです。ただ、橋本さんの言われることはよく分かる。あの種の近代日本画は、なんとなく絵本のイラストレーションみたいで、人間の多面性に迫るリアリティがないんですよね。
橋本 リアリズムは、国家が持っているからいいとでも思っていたのかなあ。何かを捨てていますよね。それで、逆にリアリズムにしようとすると極端にえぐい方向にいくのが、近代の悲しさだと思う。勉強の基本では写実写実って言うんだけれど、その写実が作品に結実していくのかとなると微妙です。そこら辺を突っ込むと、私は近代に対する悪口しか言わなくなっちゃうんで、極力悪口を言わざるを得ないようなシチュエーションは捨ててきましたけど。
浅田 いいものはいいというための本ですからね。だけど、何でああなったんでしょう?
最初にアーネスト・フェノロサや岡倉天心の戦略があって、実際に横山大観や菱田春草なんかの作品が出てくる。国際的な視点で日本の伝統を見直しながら、近代日本画というものを作り出したわけです。ところが、安田靫彦や前田青邨となると、だんだん歴史絵本の挿絵みたいになっていく。で、まさに挿絵から出発した東山魁夷を経て、平山郁夫に至るわけですよ。
橋本 あとなんか、日本ってあくの抜けてるもの程いいんじゃないかという、美意識がありません?
食文化もそうでしょう。味を落としてしまうことが料亭の料理だ、みたいになっていたじゃないですか。今までの自分達から逃げることがいいことなんだという考え方があるのかもしれないですね。
浅田 だから、両極化するんでしょうね。無難に洗練されたものがメインになると、今度は逆にたんにえぐいだけのものが出てくる……。
橋本 そこには、自分はそれでいいかもしれないけども、他人がそれをいいと思うかどうかっていうところが抜けているような気がするんですよ。つまり、職人というのは自分はそれでいいと思うけれども、お客さんがそれでいいと思うかどうかはまた別だ、という二律背反の中にいる。近代の画家にはそういうところがない。
そう考えると、近代以前の日本美術というのは根本的に弥生的であるとかいうことよりも、商業美術的なものであるということのほうが大きいのかもしれませんね。近代の画家っていうのは、認めてくれる偉い人達がどこかにいるわけじゃないですか。でも、それ以前の時代の職人にとってみると、認めてくれるいいお客さんというのは、エスタブリッシュメントの中にはいたかもしれないけれども、支配層ではないんですよね。武士の支配層に、美術が本当に分かったのかよという話になるといろいろ疑問な点もあるわけで、目の肥えているいい人のためにいいものを作っても、その人達がしかるべき地位にいなかったら、その人たちの声は通らないということになってしまう、そういう悲しい社会構造の問題というのもあったのかな、という気はします。
浅田 だから浮世絵のような商品の水準が高くなる。その流れが近代になってデザイン(いわゆる応用美術)の水準の高さにつながり、亀倉雄策の東京オリンピックのポスターまでいく。一方、官展系の画家は狭い政治の世界で生き残ったということなのかもしれない。
橋本 ひっくり返してしまえば、「官展系の画家はなぜ偉いんだろうか」じゃなくて、「このキッチュな絵はなんだろう」っていう見方もあるんですよ。近代は、初めそれでやろうかと思ったんですが、虚しい作業だと思ってやめました。
浅田 その点、僕は近代では高橋由一の時点にいちばん可能性があったような気がするんです。
橋本 私も高橋由一はとても好きなんです。だけど、それ以外の近代の日本画は、円山応挙から近代美術がはじまっていると考えると、大したもんじゃないと思います。それなのに、近代日本画の歴史は、円山応挙はとりあえず過去の人ということにして、別のバリエーションでやっていけば何か生まれるんじゃないだろうかという考えかたで作られてしまったんじゃないか、という気がします。
浅田 円山応挙は、おもちゃ屋の丁稚だったから、「眼鏡絵」という覗きからくりの絵も描いていたでしょう。芝居小屋を描いた「浮絵」の画家たちと同じで、西洋の遠近法・透視図法をマスターして、極端にパースペクティヴを強調するような絵を描いているわけですよ。その上で、いわゆる日本的な平面的表現をやってのけるんですね。
橋本 そうですね。
浅田 金刀比羅宮というのはなかなか面白くて、伊藤若冲の《百花図》という植物図鑑のような絵があり、円山応挙の《瀑布及山水図》という巨大な滝が床の間から流れ落ちている絵がある。一八世紀の西洋の美学でいえば典型的な「美」と「崇高」ですよ(応挙は一般に「美」に対応する作品の方が多いわけだけれど、一八世紀的パラダイムの中で「美」も「崇高」もこなせたということでしょう)。さらに金刀比羅宮には、その百年ぐらい後の高橋由一の油絵もある。パリの万国博覧会に対抗して個人の展覧会を開いたギュスタヴ・クールベみたいなもので(まあ高橋は反動的な県令のコミッションで仕事をしたりもしているから右翼のクールベと言うべきだろうけれど)、明治十二年の琴平山博覧会に35点もの油絵を奉納したんですね。そこには「美」でも「崇高」でもない、たんにリアルなものが描かれている。木綿豆腐と焼豆腐と油揚を描いた《豆腐》なんて、ほとんど構造主義かと思うような絵だけれど。
こうしてあえて西洋近代の視点から見ても、一八世紀の若冲や応挙の段階で同時期のヨーロッパの「美」と「崇高」の美学が実践されているし、さらに一九世紀後半の高橋由一はクールベのレアリスムに近づいているとさえ言えるような気がする。ところがそのあと急に黒田清輝とか青木繁とかが出てきて……。
橋本 西洋なんかにいっちゃうからいけないんですよ。
浅田 しかも、ラファエル・コランとか、下らない折衷派のアカデミシャンに師事しちゃったりするものだから。
橋本 高橋由一が可哀相だったのは、彼が生まれた時代のせいで貧乏だったことだと思う。つまり、若冲、応挙らはスポンサーがいるから、やれっていえば何でもやれたんですよ。由一は先生探しから絵の具作りまで自分一人でやらなくてはならなかったからクールベにならざるを得なかったんではないかと思います。彼の中には、貧乏に由来する力業のよさみたいなものがあって、それが洗練されると平板になる。
浅田 高橋由一は横浜にいたイギリス人画家のチャールズ・ワーグマンに絵を習ったわけだけど、絵の具をつくるところから全部自分でやった、それがよほど徹底していたのか、油絵としてきちんとできていて、マチエールが非常に堅牢だというんですね。それが、黒田清輝以降になると、フランスに留学して勉強したはずなのに、絵の具が高くてあまり使えなかったのか、ひどく薄っぺらになってしまう。その辺から日本近代の貧しさが前景化してくる気がするんですけどね。
橋本 高橋由一、その前の渡辺崋山は素描の力がしっかりしているんです。遡っていくと、日本の絵画って狩野探幽ぐらいからずっと素描がしっかりしている。つまり、絵を描こうとする人はきちんと素描をしなければいけないという肚が、根本にあったんですよ。でもそれがいつの間にかなくなっていて、素描が妙に東大寺南大門の金剛力士像のような、過剰に強いものの方にいってしまうへんてこりんさというのは、美術をとりまく環境が不幸だったというのがとても大きいんじゃないかなと思います。
浅田 言い換えれば、素描で漫画が描けないと駄目だということがあったと思うんですね。だから、西洋ではドーミエがあってクールベにいくんだけれど、強引に見ればワーグマンと高橋由一がそれに当たる。「ジャパン・パンチ」で諷刺画を描いていたワーグマンに習った高橋由一が鮭や豆腐を描いているのがまた凄いと思うわけですよ。あそこに日本の近代の可能性があった気はするんだな。
橋本 まあでも、高橋由一は、貧乏でまじめだったから漫画を描くような飛躍は出来なくて、豆腐描いていたっていうところもあるのかなあという気もするんですけどね(笑)。
個人を超えた美術史
浅田 でも、金刀比羅宮の高橋由一の作品の中には、左官が壁土かなんかを捏ねている脇の壁に相合傘の落書きなんかが描いてあるところまで写し取った絵がある。貧乏もあそこまでいけばすごい。他方、貧乏じゃないとどうなるかといえば、岡本太郎になるんじゃないですか。人気漫画家だった岡本一平が、息子を連れ、妻の岡本かの子とその愛人たちまで引き連れてヨーロッパへ行く。で、太郎は、抽象のグループ(アブストラクシオン・クレアシオン)から、シュルレアリスムを経て、シュルレアリスム異端のバタイユのグループまで、あるいは、コジェーヴのヘーゲル哲学講義から、出来たばかりの人類学博物館での民族学講義まで、あらゆるものを横断していく。一九三〇年代のパリの前衛の最先端をなで斬りにしたわけで、世界的に見てもあれほど短期間にあれほど横断的に動いた人はほとんどいないでしょう。そして、そこで身に着けた民族学の視線で日本の縄文を再発見することになる(実はその前に雪の科学者として有名な中谷宇吉郎の弟の中谷治宇二郎がフランスで縄文研究をしていたのを発見したようだけれど)。お坊っちゃまのパリ遊学としては世界最高のレヴェルですよ。だけど、戦後「夜の会」で一緒だった花田清輝も言う通り、君は話は面白いのになんで作品はダメなんだ、と。
橋本 近代篇に岡本太郎を入れようかって、はじめは編集者と話していたんですよ。だけど、「今すごく人気があるんですよ」って言われて、「え、じゃ止めよう」となった。つまり、岡本太郎はああいうものを認めない前提にたてば面白い存在なんですが、認められてるという前提にたつと、いいじゃん別にってことになる……。
浅田 当時のヨーロッパでも芸術や思想の最先端をあれだけなで斬りにした人は少ないんだけれど、それが作品に結実したかというと……。
橋本 なで斬りに出来ちゃうということは、通り過ぎられるということでしょ。自分にひっかかるものが何もないというのは、凄いっちゃ凄いんですけどね。
浅田 岡本太郎より前の世代の藤田嗣治だと、岡本太郎より貧乏だったということもあり、キュビスム以降の「秩序回帰」の流れの中で日本的なものをいかにうまく生かした具象画を売り出すかということを、ものすごく職人的に研究すると同時に、自らトリックスターとなって広告したわけでしょう。
橋本 それは、南蛮蒔絵と同じレヴェルなんでしょうね。むこうの要求にあわせて、日本的な技術を出すということになったら、南蛮蒔絵にしても、イギリスのヴィクトリア&アルバート美術館にある日本の磁器にしても、日本人の作るものは本当に優れていると思うもの。
浅田 乳白色の完璧なマチエールを作るとか、日本の面相筆で狂いのない極細の線を引くとか、あれは相当な修練がいりますよね。日本をいかに売り出すかという戦略を持ち、かつ職人的修練を積んだというのが、藤田嗣治のすごいところでしょう。岡本太郎の場合は、戦略しかない……。
橋本 戦略もあったのかどうか。
浅田 そう、ただ面白がっていただけかもしれませんね。ちなみに、近代篇に藤田嗣治は入れようと思われなかった?
橋本 図版載せるのが面倒くさいらしいという話を聞いていたんで、佐伯祐三入れちゃえば藤田はいいかなあと思ったんです。ただ、佐伯祐三は取り上げようと思っていたけど、梅原龍三郎は入れる気なかったんですよ。ところが、うっかり生家の職業というものをみたら、佐伯祐三がお寺で、梅原龍三郎が呉服屋だってことが分かって、なんだ、絵は生家の職業そのままなんだってことに気づいたんです。佐伯祐三がパリで描いた《広告貼り》は、ポスターの文字をお経のように書くことでレーゾンデートルを確立したし、梅原龍三郎の《雲中天壇》は緞通とか絹のキルトみたいでしょ。で、両方とも入れることにした。
浅田 ともかく、近代篇はそれまでの六巻に比べるとずいぶんコンパクトな印象でしたね。
橋本 近代になると、この人は何年生まれでこの時に何歳で、というのを全部考えなくてはならないじゃないですか。それが面倒くさいんですよ。
浅田 全体としていうと、『ひらがな日本美術史』は個人を超えたところにある日本美術史なんで、近代になると個人が出てきてうっとうしくなるんだろうな、という気はしましたね。
橋本 院政の頃の絵巻物って、作者が誰だかほとんど分からないじゃないですか。だけど作品のすごさのまえで、作者名がどれほど重要だろうかっていう気はするのね。後白河法皇の時代の絵巻物の筆遣いの見事さというものが、その後の日本美術のなかのどこに行ってしまったんだろうか、というのが私には謎なんですよ。ひょっとするとあれは、王朝社会が育てた時間の熟成の結果であって、王朝社会が壊れてしまったら続かなかったということなんではないかな、という気がします。結局、その後日本の美術はあの線描を復活してないですから。
浅田 僕はたまたま自宅が京都の北野天満宮の近くなんだけど、《北野天神縁起絵巻》なんて、誰が描いたかなんて関係なくて、たんにすごいですよね。それはやはり、後白河法皇という目利きのパトロンがやりたい放題やっていた時代の豊かさなんでしょうね。近代の作家はパトロンや観衆を自分たちで発見しなきゃいけなくなる。藤田嗣治でも岡本太郎でも、それでジタバタして深みにはまっていくところに悲しさを感じます。藤田嗣治は、エコール・ド・パリが下火になると、メキシコ流の壁画なんかを試みたあと、戦争画で観衆を獲得するんだけれど、それで後に「戦犯」扱いされることになる。岡本太郎も、前衛を気取りながら、国家の祭典としての万国博覧会のマンガみたいな「太陽の塔」で観衆を獲得するわけで、まああれはあれですごいものには違いないけれど……。
橋本 それなら、川端龍子みたいに「会場芸術」って言っちゃえばいいのに。
浅田 川端龍子が自宅の画室の横に爆弾が落ちたのを描いた《爆弾散華》なんて、戦争画として見てもなかなかのものだと思いますよ。
橋本 川端龍子のすごさというのは、絵だけ見るとこの人は反戦なのか、好戦なのかよく分からないということです。そのアナーキーさというのは、やっぱり日本人が絵を描くときに持たざるを得ない必然なんじゃないですかね。伊藤博文に依頼されて描いたという狩野芳崖の《大鷲》になってしまうと、とうとう権力に買われる職人が出て来てしまったのかな、と悲しくなりますから。
浅田 そういう意味でいうと、パトロンがいた時代というのは、アーティストも楽だった……。
橋本 西洋のルネサンスが花開いたのはメディチ家がいたからなんて言うけれど、日本にはずっとパトロンがいるんですよね。日本美術史で、ある時代にあったものがなくなったり、新しいものが生まれたりするのは、パトロンの質の変化なんだろうと思う。つまり、日本美術史という観点で見ると、パトロンの質の変化が日本の社会の質の変化なんでしょうね。
だから、白河上皇から後白河法皇の院政の時代というのは、私はあれが日本のブルボン王朝だと思っています。そうなると、鎌倉時代の到来がフランス革命なのかもしれない。もちろん、日本の歴史をあまり西洋の歴史に当てはめようとしすぎるのはいいことではないですけど。
浅田 院政期の文化というのは、その前の王朝文化をもう一回屈折させてものすごく洗練させたものですよね。たしかにあれは日本文化の一つのピークだと思います。
橋本 ただ、日本の巻物やなんかで残っているのって、だいたい院政期のものじゃないですか。そうすると藤原道長の時代にどういうものが描かれていたか、というのが想像つかないんですよ。「源氏物語」のなかに、絵合というのがあるぐらいだから絵は描いていたんだろうが、それがどういう絵なのか、想像する手だてがまったくない。だとすると、もしかしたら紫式部は絵のない時代にフィクションで勝手に絵合というものを作っていた、と考えられなくもない。そう思うと摂関政治の時代って、われわれが思っているよりも退屈な時代だったのかもしれないな、という気もするんですよね。
浅田 王朝といっても、今の古びてしまった平等院鳳凰堂なんかから想像するのは難しいですからね。でも、いま鳳凰堂が修復中で、天蓋なんかを間近で見ることができる、これは実に華麗なものですよ。装飾的でありながら、あえて左右対称にならないようにしてあったり……。
橋本 ただ、《信貴山縁起絵巻》を見ると、あの当時のお寺が壮麗で美しいもので、しかし中世のヴァチカンのようなぐちゃぐちゃした感じがあって、というすごい時代であった気はするんですよね。なにしろ死体がゴロゴロころがっているし、人は道端で平気でお尻だしてウンコするしって、一方でそういう世界だから。
王朝時代は絵よりも文字の時代で、院政の時代になって、はじめて漫画が文化になったというような考え方をすると、よく分かる気はするんですよ。「待賢門院は和歌が読めなくて、だからこそ《源氏物語絵巻》を白河上皇が作らせた」という説があって、待賢門院ってもしかすると字が読めなかったのかもしれない。王朝という一つのシステムが出来上がって、そこに乗っかれば別にたいして教養がなくても生きていけた時代なわけで、後白河法皇だってはじめは馬鹿だと思われていたことを考えると、後白河法皇と、活字の本を読むよりも漫画雑誌読んでるほうがずっと好きだった私というのがダブってくるんですよ(笑)。
浅田 違いは絵巻物を作らせるお金があるかどうか……。
橋本 後白河法皇の作らせた絵巻の多くは字を読まなくても絵でわかる。《伴大納言絵巻》なんか「映画」ですよね。後白河法皇は、今様が大好きでうたうことしかないという身体感覚の権化みたいな人だから、文字で物事を考えるのではなく、絵で見るということが初めてあそこで形になったという考え方も出来なくはない。
浅田 それが「鳥獣戯画」なんかにもつながるんでしょうね。植物は王朝文化の洗練を伝えて繊細きわまりないのに対し、動物は当時の武士や民衆のダイナミックな身体性に溢れている……。
俵屋宗達は匿名である
浅田 橋本さんが考える日本美術史のピークは、一つはいまの後白河法皇のあたり、もう一つは安土桃山時代から江戸時代の初期まででしょう。さらに強いて言えば、一番のピークは俵屋宗達あたりですか。
橋本 誰が一番うまいんだって考えると、それは俵屋宗達でしょうね。論理的な根拠じゃなくて、作品がそれを言ってるんだから、それを前提にして話を作っていかざるを得ないんですよ。安土桃山篇だけ私の書きぶりが微妙に変わっているのは、一つの時代を流れで捕まえるんじゃなくて、すでに出来上がった一つの時代を固定して三百六十度いろんな角度から眺めざるを得なかったからです。だから、第三巻は、《日光東照宮》、《能装束》、《変り兜》から始めて、後に狩野探幽の《二条城二の丸御殿障壁画》を出し、第四巻の冒頭が俵屋宗達の《風神雷神図屏風》という構成にしたんです。
宗達はいろいろと謎の多い人物ですが、それが僕にとっては幸福な感じがするんですよ。宗達が何者なのか、個人のありかたで分析すること程、不毛なことはないんじゃないかという気がしてね。
浅田 日本美術史でもっとも優れた作品が匿名であるという感じですからね。
橋本 俵屋宗達と尾形光琳の関係って興味深くてならないんです。光琳は素性がはっきりしていて知的なのに、作品となると悲しい苦闘をせざるを得ない。宗達は謎めいた存在だが、作品は素晴らしい。そこまで符丁があっちゃうのかなという可笑しさがあります。
浅田 光琳の表現は屈折しているし、内心の葛藤がこのような屈折を生んだとか何とか近代心理小説的に読めなくもないけれど、宗達にはそれがないですからね。
橋本 光琳について雑誌で書いた後、《紅白梅図屏風》について「2003年にMOA美術館が依頼し東京文化財研究所がおこなった研究・調査によって、本作の大部分を占める金地部分は、本来の説であった金箔を貼ったものではなく、金泥を用いて金箔を模し、箔足(金箔が重なり合う部分)を加え描いたものであると結論付けられた」という説を読んで、成る程それで分かったと思ったんです。《紅白梅図屏風》ってあまりにも簡単すぎる絵で、簡単すぎるからこそ、描かなくてもいい下地まで全部描くという面倒くさいことを自らに課して、描くという行為を満足させる。尾形光琳というのは、多分そういう人だったんだと思うんです。
浅田 宗達だったら豪勢に金箔でやっちゃうだろうけれど。
橋本 私は光琳のようにやりかねない人なんです。というか、絵の具を垂らしておいて、ティッシュペーパーをぐじょぐじょに丸めておいて上に押しつけると金箔みたいになるというのはイラストレーターの頃やったことがある(笑)。大したもの描けないけど金もらっているから、そうやってごまかすかっていうのは当時考えたんです。光琳が同じだとは言わないけど、光琳がそれをやりかねない感覚は分かって、光琳って、人が思っているほど自分が絵が上手だとは思ってなかった人だと思います。
浅田 逆にいうと、デザイナーとして自己限定した時はすごいわけですね。
橋本 だって、宗達の絵をいきなり見せられてしまったら、それを真似して描いて自分が絵がうまいと思えるはずないもの。自分が描けるなって思うところに、限定して描いた時だけ、光琳はいいんですよ。
浅田 それは非常によくわかりますね。しかも、実は光琳に近い橋本治が、宗達こそいちばんすごい、いいものはいい、と断言する、そこが『ひらがな日本美術史』のいいところだと思います。
躾けのなくなった日本
橋本 あとがきでも書いたんですけど、『ひらがな日本美術史』はしんどい仕事じゃなかったんですよね。私のなかで、リラックスして出来た仕事の一つです。それでも書き下ろしだったらずっとやんなければいけないけど、これは一月にせいぜい二日だったし、一冊分書いたら三ヵ月は休みをくれたので、いい仕事でした。
浅田 毎月楽しみでした?
橋本 いいものしか見ないというのは幸福なんですよね。ただ、やっていて思ったのは、確かに「日本にいいものがあるのに、なんでみんな知らないんだろう」っていう気持ちはあるんだけど、「日本美術がこんなにいいもんだぞ」と言いすぎて、美術を必要としない人が押しかけてくるという風潮を作ってしまったら、それはかえってくだらないことになるぞと思いましたね。だから、日本美術というのはどこかマイナーで不思議な、「やはり野に置けレンゲ草」みたいなジャンルでいいのかもしれない。いつの間にかふっとというような終り方が出来てよかったな、と思います。
浅田 おっしゃることはよく分かります。そもそもぼくは日本的美意識なるものを無批判に称揚したいとは思わない。ただ一方で、例えば東京オリンピックと長野オリンピックのポスターを比較すると、やはり愕然とするわけですよ。東京オリンピックの亀倉雄策によるポスターは、橋本さんも最終回に取り上げた力作でしょう。ところが、長野オリンピックの絹谷幸二が描いたポスターは、造形的に整理されていない人物像で、しかも口のところから「ファイト、ファイト」とカタカナが出ているんですよ(笑)。
橋本 よくそういうものが採用されましたですね。
浅田 東京オリンピックの時は、みんな本気で頑張った。亀倉雄策だって世界に通用するレヴェルでやろうという意気込みでやっていた。それが長野オリンピックになったら自閉的な冗談でよくなったというのは何なのか。
橋本 東京オリンピックの頃は、まだ官僚が幼児性を認めてなかったですよね。おそらく大阪万博の頃からキャラクターを作ったり、街角の公園の滑り台がキリンやゾウの形になったりだの、幼児的なシンボリックなものを置けばそれが子どもを理解することになるという風潮になったんだろうと思うんです。私は建設省の車に「けんせつしょう」ってひらがなで書いてあり、さらに子ども受けするキャラクターの絵が描いてあるのを見て、国家がみんなに好かれようとして却って国家の体面を損なうようになっているというのをはっきり感じましたね。多分、長野オリンピックもその末路なんでしょう。
浅田 まさにその通りだと思うけれど、そういう意味でいうと、やっぱり大阪万博の岡本太郎の「太陽の塔」が転換点だったのかもしれない。丹下健三・磯崎新組の「お祭り広場」のプランは、弥生的なものを暗黙のベースに、情報化社会にふさわしい「見えない建築」をつくろうというものだった。そこへ岡本太郎が大屋根をぶち抜いて「太陽の塔」を建ててしまった。そちらの方が「キャラ立ち」してしまって、丹下・磯崎組は敗北を喫したわけですよ。幼児化が顕著になるのは最近のことだとしても、源泉はそこにあったのかもしれませんね。とにかく、橋本さん風の大人の職人としての常識をかなぐり捨てて、「女子供」が喜べばいいだろうというポピュリズムの方向にとめどもなくすり寄っていく……。
橋本 そうそう。でもだからといって、「いま大人の職人の復権を」なんて簡単に言っても無理なんですよ。みんな追い詰められていて、どうしたらいいか分からなくなって、もう有明海のムツゴロウのようになっているから、生きていく余地ってそんなにないと思うのね。
浅田 近代まで続いてきた弥生的構造もついに解体され、あとには情報化社会の基盤の上で「女子供」向けの「キャラ」が浮遊しているだけなのかもしれない……。
橋本 いや、解体できるようになったという段階で、すでに日本は解体されてるんですよ。システムがしっかりしている時は生半可なものって絶対に受け入れられないもの。
七〇年代前半に新聞社に写真撮ってもらった時は、当時はみんな口閉じてて表情がないから、あえて笑ったら、口閉じろって怒られたんですよ。ところが今はみんな口開けて写真撮っている。
浅田 ミシェル・フーコーが近代の基盤だと言う「ディシプリン」だけれど、日本語で言えば要するに躾けですね。姿勢をちゃんとしなさいとか、げらげら笑っていちゃいけませんとか(笑)。ぼくらはそういう躾けが嫌いな側だったんだけれど、躾けがなくなってしまうとやはり呆然とするほかない……。
橋本 口開けてちゃいけないっていわれている時代は、「口開けてて馬鹿と言われてもいいんだけど」って言っても、そのあえては許して貰えなかったんです。それが許されちゃうと、許されることの意味がないんだよね。
浅田 そこで橋本治はあえて大人の職人になって『ひらがな日本美術史』を書いた。本当をいうと、ぼくはこれが日本美術史の教科書になればいいと思うんです。
橋本 長すぎません?
浅田 でも、あえてこれぐらいの量は読ませるべきでしょう。
橋本 そうかもしれませんね。ただし、本当に必要なことって教科書で学ばないじゃないですか。それこそ、教科書は躾けだけであって、躾けだけじゃ人間つまらなくなるから、どういう活動するかってところが問題なわけで、その教科書の外側に教科書よりも豊かなものがないといけないんですよね。
浅田 確かにその通りですね。ところで、ずっと日本美術を見てきて、自分でもし何でも貰えるとすると、何がいいですか。
橋本 私、光悦の《白楽茶碗 銘不二山》が欲しいんです。あと本当は桂離宮が欲しいんですけどね(笑)。ただ、美術っていうものは、かつては所有できるだけの大金持ちがいた時代には所有するものであったけれども、もう現代では所有というのはおこりえないわけじゃないですか。そうすると、共有するという方向に美術がいってしまっていると考えざるを得ない。何が欲しいという考え方自体が無意味だし、私は金もないし、そこら辺は金のある人に考えて貰おうという感じですかね。
浅田 もちろん本物を見ることは絶対必要だけれど、きちんとした図版が体系的に収録された本をもっているというのも、インターネット時代には消え去ってしまうかもしれない一種の贅沢かもしれませんね。ちなみに、執筆の時は資料は基本的には画集ですか。
橋本 そうです。ただ、たまたま展覧会をやってる時には行きましたね。現物見た時の違い方ってあるじゃないですか。高橋由一の《鮭》が大きいっていうのは成る程と思いましたし、色も印刷と原画では微妙にちがうんですよ。古い絵は印刷のほうが綺麗で、現物は汚くて何が描いてあるか分からないなんてことも多分にある。
浅田 そうですね。ちなみに、ぼくが同世代で面白いと思って見ているのは福田和也という人で、彼は今の原稿料と印税で川端康成のようなコレクションが欲しい、それで無茶苦茶に書きまくって無茶苦茶に買いまくるわけでしょう。無謀ですよ。ぼくは逆に、できるだけ何も持ちたくないと思う。本物のリアリティが情報に還元できないことはよくわかっているけれど、やっぱりものに縛られたくない。
橋本 収入の限界って大きいじゃないですか。そうすると今の自分の金で買えるものはこの程度というのが、似合う似合わないに結びついてくるんです。四十代の時に、四十代でこれしか買えないんだったら買わないほうがいい、という新しい日本の美意識になってしまいました(笑)。ただ、私、複製でもいいんで、二十代の頃に画集はよくそろえたんですよ。複製でも何でも、美術って自分で持っちゃうと食物のように食えるんです。それで消化してしまえる度合いは強くなったな、と思います。
浅田 同感ですね。実は、雪舟論なんかを見ると、小林秀雄なんかもいろいろ蒐集もしながら結局はそう思っていたんじゃないか。そうやって食べて消化して排泄してしまえばそれでいいんですよ。
(平成19年4月14日)
はしもと・おさむ
小説家、批評家、随筆家。1948年、東京生まれ。東京大学文学部国文科卒。小説・戯曲・評論・エッセイ・古典の現代語訳・浄瑠璃などの古典芸能の新作ほか、多彩な執筆活動を行う。2002年『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』で小林秀雄賞を、2005年『蝶のゆくえ』で柴田錬三郎賞を、2008年『双調 平家物語』で毎日出版文化賞を受賞。著書に『窯変 源氏物語』『巡礼』『リア家の人々』『ひらがな日本美術史』『失われた近代を求めて』『浄瑠璃を読もう』『九十八歳になった私』などがある。2019年没。
あさだ・あきら
批評家。1957年、神戸市生まれ。京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長。同大で芸術哲学を講ずる一方、政治、経済、社会、また文学、映画、演劇、舞踊、音楽、美術、建築など、芸術諸分野においても多角的・多面的な批評活動を展開する。著書に『構造と力』(勁草書房)、『逃走論』『ヘルメスの音楽』(以上、筑摩書房)、『映画の世紀末』(新潮社)、対談集に『「歴史の終わり」を超えて』(中公文庫)、『20世紀文化の臨界』(青土社)など。
※この対談の初出は『新潮』2007年8月号です。転載を許諾して下さった橋本治氏のご遺族、浅田彰氏、そして新潮社『新潮』編集部に感謝申し上げます。なお、同じ対談が同社の『ウェブでも考える人』http://kangaeruhito.jp/に掲載されます。
2019年5月4日公開

