芸術論の新たな転回 03 平芳幸浩(1)デュシャンはどのように受容された(される)か――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって1(Interview series by 池田剛介)
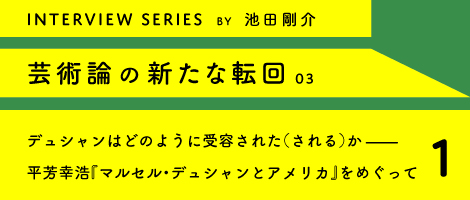
インタビュー:平芳幸浩
聞き手:池田剛介
優れた芸術評論に送られる吉田秀和賞が平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ: 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』(ナカニシヤ出版)に授与されるというニュースが届いた。緻密かつ広範なリサーチに基づきながらも従来の作家論のあり方を刷新し、これまで幾度となく語られてきたデュシャンへの新たなアプローチを示す意欲作にふさわしい選出と言えるだろう。受賞直前のタイミングで収録された、本書をめぐる徹底討議。

左:平芳幸浩/右:池田剛介(Photo: Kanamori Yuko)
池田 今日の現代美術に最も大きな影響を与えたと言っても過言ではないデュシャンの《泉》、この男性用小便器がアート史に登場して今年で100年目になります。この節目に20世紀芸術の可能性と限界を捉え直しつつ、その先へ行くためのビジョンを考えることが、「芸術論の新たな転回」を始めるきっかけのひとつでした。
平芳さんは、去年『マルセル・デュシャンとアメリカ』を上梓されましたが、そのベースとなる博士論文を2004年に完成させ、また同年には国立国際美術館の学芸員として『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展を企画されています。
今年4月から来年3月にかけ、京都国立近代美術館では『キュレトリアル・スタディズ』というシリーズの一環として平芳さんが企画に関わられているデュシャンをめぐる連続展示が行われ、ニュイ・ブランシュKYOTOではREALKYOTO編集長の小崎哲哉さん企画によるデュシャンと千利休をめぐる展覧会『見立てと想像力』が開催されるなど、《泉》100周年に関連して様々な試みがなされています。

『マルセル・デュシャンとアメリカ: 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』平芳幸浩=著 2016年 ナカニシヤ出版
鏡像としてのデュシャン
池田 考えてみれば、これまで散発的なものかもしれませんが、例えば荒川修作がデュシャンとの直接的な関係の中で、その影響の色濃い作品を作っていたり、あるいは『見立てと想像力』にも出されている藤本由紀夫さんは音の観点を中心に長年デュシャンを扱われていたり、最近だと毛利悠子さんが《大ガラス》をエコロジカルなモデルとして展開していたり、日本でも様々な作家への触発はあったのだと思います。だけれど他方で、例えばレディメイド、つまり絵画や彫刻のような作品を制作するのではなく既製品をそのまま扱うというようなことは、もはや現代美術において当たりまえの前提になっていると言えるでしょう。ここで改めてデュシャンが現代美術にもたらしたものを見定める上でも、平芳さんの『マルセル・デュシャンとアメリカ』は大きな示唆を与えてくれるように思います。
平芳 いま、池田さんがおっしゃったように、散発的にデュシャンが刺激を与えるソースとなって参照され、現代的に翻案され続けているという状況があり、そうした状況そのものがデュシャンの作品や思考の質を物語っている部分があると思います。常に見る側の欲望の鏡のような存在としてある作家だと考えているのですが、その鏡としての機能は意外とまだくすまずに、相変わらず様々な欲望を反映する場所としてあるのかな、という印象をもっています。
池田 見る側の欲望を反映する鏡と言われましたが、この本は戦後アメリカ美術の言説状況がデュシャンを通じて映し出されるものにもなっています。色々な状況の中でデュシャンがその都度引き合いに出され、それに言及する者たちが様々に論陣を張って批判と擁護の応酬を行う様子が生々しく見えてくる。日本の美術批評には、なかなかそうした言説的なダイナミズムそのものが成立しないように思います。
平芳 日本の場合は、おそらくこういうダイナミズムは成立してこなかっただろうし、いまもしないでしょう。何人かの批評家たちは、そういう風になればと考えて一時期色々な議論が行われたりもしたのですが、残念ながら相手を罵倒するだけで終わるというのが繰り返されて来た感じはあって(笑)、なかなか難しかったのだろうと思います。本のあとがきでも少し書きましたが、デュシャンが取りざたされる裏側には、必ず抽象表現主義と、それにまつわるクレメント・グリーンバーグを中心とした言説があり、その対極側にデュシャンが想定されるという構図があって、そうした動きが見えやすいということもあるでしょう。
池田 それにも関連して特徴的だと思うのが、あとがきにも書かれていますけど、デュシャンをめぐる本でありながら、デュシャン作品そのものについて論じない点です。デュシャンは様々な解釈をひたすら誘発し続けるところがありますが、あえて作品そのものを論じずに、それがどう受け取られていったのかという点にフォーカスされています。こうした方法論を取られる背景には、どういった問題意識があったのでしょうか。
平芳 そもそも、この研究に着手し始めたのにはいくつか理由があります。ひとつには、デュシャンに対する考えかたの問題、もうひとつには、いわゆる美術史学という学問のありかたとして、どのようなアプローチが可能かという問題です。
私が研究を始めたのは20年くらい前で、ちょうど日本にニュー・アート・ヒストリーという考えかたが、かなり浸透し始めていたころでした。それまでのいわゆる作家論や、あるいは実証主義的な、何か新発見がなければ研究として成立しないというような美術史学の研究のありかたではなく、もう少し社会的なコンテクストに広げて、迂回するようなかたちで作家や作品を見直していくような傾向です。特に近代以降、つまりロマン主義的な天才神話が成立して以降の作家論というのは、作品ないし作家の意図の汲み取りに収斂していく傾向が強い。そうすると作家の考えから逃れられないという限界があって、作家神話を補強することにしかならない。なんとかそれを解体できないか、ということを考えていました。美術史学の問題として、そういう関心があったわけです。
もうひとつには、これまでのようなデュシャン作品の読解、日本では特に東野芳明さんらが率先してやられてきた、暗号を読解して神秘を共有できるものにしていくような考え方に対して距離を取りたいということです。新たな神秘の発見や、それに対する解答の発見といったものに、大きな意義を感じられませんでした。ではいったいデュシャンとは何なのかというと、先ほども言ったように、他者の欲望を常に反映する場所と言えると思います。その様々な欲望が重ね合わさって相対的に浮かんでくる、カギ括弧つきの「デュシャン」、私が研究で相手にしているのは、そういうものです。他者がどこまで言語を介してアプローチをしても、結局のところ本人そのものや、作品そのものには永遠に到達できない。そういうカギ括弧つきの何かを常に相手にするのであれば、そもそも明瞭なカギ括弧つきのものとして相手にする、ということを態度としてはっきりさせることが重要だと考えました。そうすると結局、自分がやっているこの研究もまたひとつのカギ括弧つきであるという位置にいられるので、メタの状態にとどまらない。その位置が大事だということですね。
池田 なるほど。平芳さんの研究はデュシャン論についての議論というメタな立場を取っているけれども、しかし結局のところ、そのような立場を維持し続けることはできないわけで、メタな立場を取っているということ自体が、ひとつのカギ括弧に括られる、という感じでしょうか。
平芳 方法論的には、おそらくメタな立場になるのですが、そのアプローチそのものがまた、さらなるメタに回収されていくことを自覚しつつ研究をするという感じです。デュシャン研究としては当然、東野さんが作ってきた神話を脱神話化、あるいは脱構築することを目指しています。デュシャン研究を始める時点で、おそらく方法としてはそれしかありえないだろう、と。東野さんが見落としている何かを新たに発見するというのは、それこそ重箱の隅をつつくようなもので、そういう研究は未だに世界中でやられてはいますが、日本という極東で、英語でもフランス語でもなく日本語でやって一体誰が読むのかと考えると、なかなか難しいだろうと思ったわけです。
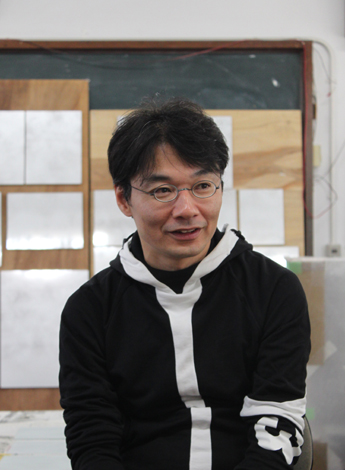
創造行為と創造過程
池田 デュシャンという行為主体が確固としてあり、それが誰かに影響を与えるという、一方から他方への影響というものがあるとすると、平芳さんの本では、様々なプレイヤーがそれぞれにデュシャンを読み、またそれに対してデュシャンがどのように応答していくかも含め、複数の力が押し合いへし合いする場として、デュシャンという名をめぐる出来事を捉えようとしている印象を持ちました。
少し話は飛びますが、國分功一郎さんが『中動態の世界』を出されて、する(能動)とされる(受動)ではない世界の捉え方について、文法の観点から論じられています。さきほど言われた、作品や作家の意図の汲み取りに収斂していくタイプの研究というのは、作品の意味や作家の主体性なりが前提とされ、そこに漸進していくという構図になるわけですよね。そこでは作家という能動者とその受け手という受動者とが明確に区別されている。國分さんによる中動態をめぐる議論を経ると、一見すると能動的にも見える行為の中にもいくばくかの受動性があり、その逆も然り、ということがよくわかる。このような能動と受動という前提を回避しようとする國分さんの議論は、平芳さんのアプローチと共鳴するところがある気もします。
平芳 もちろんこの本を書いた時に中動態のことを意識していたわけではないですが、デュシャン自身がそれに近いことを考えたり、発言したりしています。常に作品を通して、なんらかの場や出来事が形成されていくわけですが、デュシャンは、作品というものは作家側だけで完結するものではなくて、常にもう一方の他者からの作品へのアプローチがあるという、その関係によって初めて作品が完成へと近づく、という考え方をしています。そういう意味では中動態的な出来事性を制作論の中でも意識しているだろうと思います。また、この本にも書いていますが、デュシャンはアートの世界をチェスゲームとして捉えるような傾向があり、常に他者性が介在している中で物事が進展していくのであって、自己完結はしないという部分が大きいだろうと思いますね。
池田 デュシャンの言う「創造過程」。
平芳 英語では創造行為(creative act)だったのが、フランス語でprocessの意味に変わって、創造過程となる。『マルセル・デュシャン全著作』はフランス語から訳されているので創造過程となります。
池田 創造過程と創造行為とでは、ずいぶんニュアンスが違いますね。
平芳 もともとは英語の講演の中での発言で、おそらくデュシャンが英語で書いていて、それをあらためて自分でフランス語に翻訳しています。
池田 それは面白いですね。もともとは英語でアクトだったものが、フランス語のプロセスという言葉になっている。過程(プロセス)ということで言えば、特に90年代以降、参加型の作品や、何らかのプロセスを作品とするといったことは当たり前になっています。それは確かにデュシャンが開いたものの延長上と言えるとも思うのですが、どこか決定的に違っている気もする。
平芳 観者参加型のアートやプロセス型のアートには、確かにデュシャンの影響が50年代の後半あたりから綿々と受け継がれてきています。90年代以降のいわゆるリレーショナル・アートやソーシャリー・エンゲイジド・アートが、直接的にどれくらい関係しているかというと、その間に様々なものが介在しているため、遡ればデュシャンと言えなくもないかな、という程度ですが。
現代的な、作者と観客の関係性を問題にするアートと、デュシャンの言うところの創造過程の違いに関して言えば、リレーショナル・アート的な考え方というのは、関係性を通して一種の調停や和解、合意などの成立を目指す傾向が非常に強い。つまり観客が参加することによって作者の意図を汲み取ることができる、という前提がある。あるいは様々な触発があるとしても、それらもすべてある種の合意の上に成り立っている印象を受けます。他方、デュシャンの創造過程というのは、もっと突き放されています。作品が提示されて、ひとつの行為が一旦完了した時点から、もう一度始まる創造過程の中で読まれていくプロセスというのは、どちらかというと誤読に近くて、必ずしも作者の意図へとフィードバックされるものではなく、どんどんと違う意味や別の関係性がひとつの作品の上に蓄積していくということも十分ありえる。
池田 予定調和やコンセンサスに開かれていないからこそ謎なのであり、観る者がそこに巻き込まれてしまう。これをみんなで共有しましょうとオープンにするのではなく、謎めいた魅惑が内に隠されているからこそ、神秘的な解釈も含めていろんなものが引き出されてしまうわけですね。むしろ作品が謎めいたアクトとして閉じられているからこそ、デュシャンにすら予想外のプロセスが可能となる。

《遺作》の裏切り
池田 本書では、デュシャンの謎に誘われるように、様々な欲望を巻き込みながら、デュシャンが多様に受容されていく戦後アメリカ美術の状況が詳らかにされています。ですが最後の《遺作》をめぐる章では、こうしてデュシャンがある意味では好き勝手に受容されていく状況そのものに対するひとつの切断が描かれています。
それまでレディメイドやマルチプル的な複製物を通じて、芸術概念を転覆させ作品のオリジナリティを批判していく、そういう存在としてデュシャンがしばしば言及されていたのに対し、《遺作》の場合、美術館という芸術の殿堂のような場で、そこでしか見られないものを抜け抜けと作ってしまっている。この作品はフィラデルフィア美術館に、ほぼ移動不可能な形で設置されているわけですが、こうした《遺作》と美術館という場との関係について伺えますか。
平芳 《遺作》自体は、よく知られているように、1940年代の中ごろから、20年強くらいの時間をかけて、家族とごくわずかな友人以外にはまったく誰にも告げずに、アトリエの一室に鍵をかけた状態で密かに作り続けていたという作品です。死後に発表されてから、フィラデルフィア美術館に恒久設置のようなかたちで公開されていますが、発表された時には、「デュシャンが作品を作っていた」と世界中で話題になりました。その前の時代には、ヨーゼフ・ボイスが「デュシャンの沈黙は過大評価されている」というパフォーマンスをやったくらいデュシャンは何も作らなくなったと言われていたし、沈黙を貫き通していることにデュシャンの価値が見出されていたわけですが、それに対する正面からの裏切りというか、あえて裏切りのようなかたちにするために、デュシャンは作っていることを隠し、沈黙を守っていたのではないかと考えられます。
デュシャンが《遺作》の制作を始めた40年代半ば当時、フィラデルフィア美術館や美術館制度について彼がどれくらい考えていたのかは定かではないですが、おそらく戦後の、特にアメリカにおけるデュシャン受容の状況と、自分の作品がまとめて美術館に入り、周囲から現代美術のカリスマとしてのポジションが作られていくことに対し、そこをチェスゲームの場にしよう、という考えが芽生えてきたのだろうと思います。彼の遺言には、作品を美術館に設置をすることと、もうひとつには写真による複製を15年間公開禁止にすることが書かれていて、フィラデルフィアに行かなければどんな作品なのかわからないので、結果としてデュシャン詣でをさせてしまうという、極めて矛盾した、非常にアイロニカルな場を作ったわけです。《遺作》と《大ガラス》との関係や、あるいは愛人のマリア・マルティンスとの関係についてなど、色々な解釈を提出することは可能なのですが、何より《遺作》が収められるために様々なことを計算し、初期の作品がフィラデルフィア美術館で公開された1954年以降の最後の10数年が積み上げられてきたことの方が、デュシャンとしては非常に大きいだろうと思います。
池田 そもそもレディメイドは複製芸術の代表みたいなもので、ヴァルター・ベンヤミン的な「礼拝的価値から複製的価値へ」というパラダイムで言えば、複製的なものを代表していたデュシャンが、聖地巡礼のようなしかたで「いまここ」としてのアウラに帰着するわけですね。ちょっと話がずれますけど、いまの地域アートや芸術祭にしても、もはや礼拝的な価値に帰っているというか、しばしばツーリズムと結託して巡礼的な場を作る方が資本主義の論理にも適っている、という状況にもなっています。それは写真公開を禁じるという戦略をとってまで巡礼を強要するデュシャンの《遺作》において先取りされていると言えなくもない。
平芳 かなり意図的だったのだろうとも思います。レディメイドの再制作や、他者が買ってきた既製品にサインを入れてオーソライゼーションするという、つまり複製物のさらなる複製物をオリジナルとして認めるということを、あっけらかんとやってきた。そういう作家だと思われてきたし、その権化のような立場だったので、そうした自己像に対して自分がどう次の行動に出るかを考えたときに、その結果としての「複製禁止」ということになったのだと思います。
デュシャンとネオダダ
池田 そうした多様なデュシャン像が築きあげられてきたからこそ、《遺作》での裏切りの強烈さが見えてくるわけですね。レディメイドに代表されるように、デュシャンは芸術と日常とを地続きにし、その境界を無くしていく作家として扱われているところがあって、いまではネオダダのロバート・ラウシェンバーグやジャスパー・ジョーンズも、その延長線上で語られる。こうした議論がどのように現れてきたのか、本書では当時の批評言説などを紹介しつつ丹念に検討されています。
平芳 《遺作》についての論文を書いた後に、戦後、厳密にいうと戦前期の1930年代あたりからのアメリカでのデュシャンの読まれ方を詳細に見ていこうと思いました。デュシャンは、レディメイドの作家として、あるいはネオダダの始祖として、ときには芸術と日常とのギャップを埋めるような作家として語られるのですが、実際のところ、そうした言説が形成されるのはいつどこからだろうか、ということをはっきりさせる必要があるだろうと。
よく見ていくと30年代、40年代当時の言説では、レディメイドのことはほとんど触れられないことがわかってくる。このような確認作業を通じて、キュビスム的デュシャン像と、シュルレアリスム的デュシャン像という位置付けが見えてくる。それらの言説の中では、いずれにしてもデュシャンは画家はやめたけれど、芸術ということを非常に大きな視野で考える知の巨人のような存在として特権的な芸術家像の中に位置付けられていた。ですがこのときレディメイドは必ずしもクローズアップされていません。その理由はおそらく、当時のアメリカにおける芸術の価値の問題、芸術とはいかなるものかという認識の限界によるものでしょう。
そこからしばらくしてジョーンズやラウシェンバーグが出てきたときに、ほぼ初めてレディメイドがクローズアップされてくる。ここで50年代の言説上のせめぎ合いというのは、レディメイドを絵画とどう分離していくのか、あるいは一体化させていくのか、ということであって、ネオダダが登場したころのデュシャン、ジョーンズ、ラウシェンバーグにおける言説のあり方の違いを分析することで、その分離と接合のせめぎ合いが芸術価値の有無と表裏一体の動きになって出てくる、ということを明らかにしようと思いました。
池田 当時のネオダダの評価のあり方というのは、具体的にはどういったものだったのでしょう。
平芳 よく見ていくと50年代のジョーンズやラウシェンバーグについての美術界での言説というのは、いわゆる今日的な意味でのネオダダ的解釈ではなく、いかに彼らがダダ的なふりをしながら絵画的な問題を扱っているかという回収の仕方を必ずやっています。そして、その回収が成り立たないものに関してはダダになっていく、という構図が50年代には支配的だったわけです。
池田 芸術作品として評価される上では、単にダダ的というよりは、それをいかに絵画の中に回収しているかが重視される。
平芳 そういうところが必ず出てくる。そこが価値の判断基準として機能していたことがわかります。いま、ジョーンズやラウシェンバーグを通じて言われるような、芸術と日常のような問題は、当時必ずしも評価の根拠にはなっておらず、少なくとも、デュシャンからの直接的な系譜として評価されている、ということではないことは明らかです。いかにデュシャン的な振る舞いをしながら、絵画の問題、つまり抽象表現主義以降のアメリカ型絵画というものの可能性を考えているかということが評価の基準です。日本では東野芳明さんらを経由してジョーンズたちが解釈されていくので、そこの色合いはだいぶ薄まるのですが、アメリカではジョーンズ自身もそうですし、ラウシェンバーグもおそらく当時は、そういうかたちで自分たちの作品を意識していたのだろうと思います。
池田 前の世代の抽象表現主義に対して何を出していくかという、その緊張関係こそが重要だった、と。そのときに抽象表現主義のカウンターパートの位置に、レディメイド=ダダの極が措定される。
平芳 そうだと思います。つまりデュシャンはあくまで参照される項として出現はするけれども、「デュシャンに対してどうなのか」ということがまず念頭に置かれているというわけではなく、常にアメリカの前の世代のカノンに対して新しい芸術のあり方を模索するときに、デュシャンがその迂回路の中に出てくるということです。
芸術と日常性/世俗性
池田 同時代に振付家のイヴォンヌ・レイナーがいますが、最近京都で、彼女をめぐる企画が行われました(「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビジョン」)。上映されていたドキュメンタリーの中で「舞台上で洗濯物をたたんでいるんじゃないか」と言われたりした、などと語られていて、芸術と日常との関係を問い直すことがジャンルを超えた同時代的なテーマだったことが見て取れます。ラウシェンバーグやジョーンズの場合は、そうした日常性を意識しつつ、それを絵画のほうに引き寄せていくわけですが、ある意味ではよりラディカルに日常に向かう動きがフルクサスから起こっていますよね。
平芳 フルクサスの中心人物であるジョージ・マチューナスは、もともとデザインをやっていた人でしたが、メンバーは音楽家が多く、デュシャンというよりはジョン・ケージの影響下にあって、ケージを通してデュシャンのことを知るというかたちでした。彼らが音楽やパフォーマンスの可能性を模索する中で、デュシャンが引き合いに出されてくる。マチューナスは、マルチプルで非常に廉価な、お小遣い程度で買えるような、どうみても芸術品と呼べないものを作品として通信販売したり、ボックスに詰めて販売したりしながら、美術市場の撹乱、美術の金銭的価値に対する攻撃を正面切ってやろうとする。フルクサスの名前がそうですけど、作品としては何も形に残らずに、つねに流動している状態の中で何かを生成させようとするわけです。
こうした、どこまで芸術と呼べるのかわからないような、既製品としても価値をもたないものを作るということは、デュシャンの作品や構造が持っていた左翼的なユートピア思想、すなわちすべてが平準化され、誰しもが同じ行為を同じ価値でやれるということを、極端にリテラルなかたちで実現しようとした結果なのだと思います。それゆえ美術市場とは乖離していくので、どうしてもフルクサス自体の評価は、かなり後の時代まで待つ必要があった。
池田 フルクサスの場合、芸術か否かという問いをラディカルに推し進め、非芸術の方へと向かうわけですが、ポップ・アートになると絵画や彫刻として、ある意味では「普通に」芸術としての形式をとる。そこでは「芸術か否か」という問いよりも、とりあえず芸術としての形式は踏襲した上で、描かれるテーマの次元で日用品を選んだりする中で、そこでもまたデュシャンが引き合いに出される。ポップ・アートの登場時は初めに伺ったような言説的な応酬が特に強く起こっていますね。
平芳 おそらくポップ・アートのときがいちばん強かった。その理由は、非常に現実的な部分で言うと、ポップ・アートの作品は登場すると同時に、ものすごく売れたからでしょう。作品を購入するのは、いわゆる新興コレクターと呼ばれる人たちで、それまでのアメリカ美術を支えていた人たちとは世代が全然違う。新しいコレクターが新しい芸術を支えるので、旧世代対新世代のような対立がジャーナリズムの中でも生まれてきて、それでポップ・アートを認めるかどうか、という論争が大きく出てきました。そのためアメリカでは、芸術に関わるすべての人たちがポップ・アートを避けて通れなくなる。
このポップ・アートの大きな話題性が、デュシャンのレディメイドをアメリカ中に知らしめることになったのではないかと思います。ポップ・アートでは、日用品をテーマにすること自体がアメリカの芸術のありかたとして捉えられ、ヨーロッパでなくアメリカで起こった現象としてアメリカ人が引き受けるので、そこでデュシャンのレディメイドが大きく取りざたされる。デュシャンの作品がフィラデルフィアで公開されたのが1954年で、そのときは、興味のある人がデュシャンを見にいく、という感じだったのですが、ポップ・アートが登場した直後の1963年にパサデナ美術館でデュシャンの大きな回顧展があったこともあり、非常に強く認知されることになりました。ただ、先ほど言われたように、ポップ・アートは彫刻と絵画の形式そのものは完全に踏襲しているので、これらが作品と呼べるかどうかということ自体はあまり問われない。問題は、こんなものを描いてどうするんだ、ということだったわけです。
池田 いまではコーラ瓶であれキャンベル・スープであれ、普通にポップなものとして見えてしまいますが、当時はこんなものを描いてどうするんだというモチーフを露悪的に描くのが強烈だったわけですね。ネオダダのジョーンズやラウシェンバーグは、レディメイドを絵画のほうに引き寄せるわけですが、ポップ・アートでは、デュシャンが持っていた世俗性を徹底して増幅してみせる。その姿勢が、強い拒絶反応も含めて様々なリアクションを引き出すことになる。
平芳 面白いのはアメリカ人たちがその「世俗性」を、アメリカ的な病として捉えていることだと思います。ポップ・アートを見るときに、彼らはどうしてもそこに自分たちの姿を見てしまう。パサデナ美術館でデュシャンの回顧展が開かれた1963年は、彼の《階段を降りる裸体No.2》がアメリカにセンセーションを引き起こしたアーモリー・ショーの50周年に当たります。このときにアーモリー・ショーを見直しながら、それを愛国主義的に読み直すという動きが強くありました。あのときヨーロッパがアメリカにした仕打ちに対してどう応えるかというかたちで、アメリカとは、あるいはアメリカ美術とは何かということが問われました。アメリカ芸術の伝統の中でポップ・アートを読み直そうという動きの中で、アメリカ芸術における通俗性はデュシャンやレディメイドの影響によるものではなく、そもそもデュシャンが来る前からアメリカでは通俗的な絵画を描いてきた、ということが主張されたりもしました。
池田 通俗性をアメリカ美術の正統さの根拠にするというのも、なかなかすごい話ですね(笑)。少し話がずれますが、いまでは《泉》がまさに20世紀美術の源泉のように言われます。ある程度そのようなものとして認識されたのはいつごろなのでしょうか。
平芳 記録を追いかけている限りでは、1936年の末にMoMAで行われた『幻想美術、ダダ、シュルレアリスム』展のカタログで、ジョルジュ・ユニェがテクストの中で少し触れていて、年表にも出てきます。その時点ではそれくらいの扱いで、ダダのメルクマールとして登場するわけではない。ロバート・マザウェルが戦後にダダのアンソロジーを編んだときも、マザウェル自身は《瓶乾燥器》こそが1914年の最も美しい彫刻であると言って、便器のことには特に言及はしない。ただ、そのアンソロジーの出版に合わせるように、シドニー・ジャニスのギャラリーでダダに関する展覧会が2回開かれています。そのときジャニスは便器を購入して、デュシャンにサインしてもらって展示をする。そのとき、おそらく戦後アメリカで初めて便器が実体化することになります。
池田 何年ですか。
平芳 ジャニス画廊では、1950年と1953年の2回、展覧会に便器が展示されています。便器自体は、それまでにも様々な言説の中で触れられるのですが、いま言われているような「20世紀美術に最も影響を与えた」というふうになるのは結構遅い。
池田 そして先ほど言われたように、特にポップ・アートの時期に引き合いに出されることによって、デュシャンがアメリカ美術の中で存在感を持ってくるわけですね。
(2017年10月17日、元新道小学校・HAPSスタジオにて/2017年12月25日公開)
▶デュシャンはどのように受容された(される)か
――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって2
ひらよし・ゆきひろ
美術史研究者。京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授。マルセル・デュシャン研究およびレディメイド以降の芸術を専門とする。国立国際美術館主任研究員時代の2004年に『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展を担当。著書に『マルセル・デュシャンとアメリカ 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』(ナカニシヤ出版)〈吉田秀和賞〉がある。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。
〈C O N T E N T S〉
芸術論の新たな転回 03 平芳幸浩(Interview series by 池田剛介)
・デュシャンはどのように受容された(される)か
――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって1
・デュシャンはどのように受容された(される)か
――平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐって2

