芸術論の新たな転回 04 國分功一郎中動態から想像力へ ——國分功一郎『中動態の世界』をめぐって(Interview series by 池田剛介)
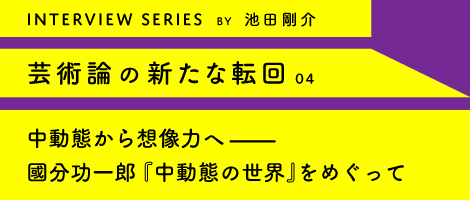
インタビュー:國分功一郎聞き手:池田剛介
2017年春に出版された『中動態の世界』は、古典ギリシア語の文法を歴史的・哲学的に検証していくという学術的な内容ながら大きな反響を呼び、同年の小林秀雄賞を受賞。紀伊國屋じんぶん大賞2018では第1位となった。能動態でも受動態でもない中動態を起点とし、旧石器時代から情報化社会までを横断しつつ、文化や芸術そして想像力をめぐる広範なビジョンを展開する徹底討議。

國分功一郎(All Photos: Tahara Tadayuki)
池田 今回は哲学者の國分功一郎さんにご登場いただきました。近著『中動態の世界』を起点に、主著の『暇と退屈の倫理学』について、さらに最近は想像力の問題について考えられているとのことなので、こうした関心についても、文化や芸術との関連を見据えながらお聞きできればと思います。

國分功一郎
『中動態の世界 意志と責任の考古学』
(医学書院)
池田 まずは2017年に出版されて話題になった『中動態の世界』ですが、今回読み直してみて、やはりこの本が医学書院から出されていて、依存症の問題がひとつの出発点になっているというところに意表をつかれる思いがします。というのもこの本では、古典ギリシア語の文法についての歴史的・哲学的な検討がたいへん緻密に展開されているからです。まずはこの中動態と臨床的関心との接点について伺いたいと思います。
國分 中動態への関心というのは昔からあって、本当に自分はポストモダニストだなと思うのですが、近代的主体に対する様々な疑問を持っていたんです。言い換えれば、人間の弱さに対する関心ですね。主体を立てなければならない、という抑圧をなんとかしたいと、ぼんやり考えていました。そのときに、中動態という言葉で記述される主体のあり方に関心を持った。そういうことを考えるうちに気付いたのが、能動/受動の図式で考えることのもたらす深刻な被害であり、依存症という事例はまさにその中心に位置するものだったんです。
ですので、この本を医学書院から出したことには必然性があって、自分がここまでやらなくちゃいけないと思えたのは依存症という事例との出会いがあったからなんですね。依存症と出会う以前だと、「この概念を使えばこれまで小難しく言われてきた現代思想の概念がどれも簡単に整理できてしまう」くらいに考えていたんですが、それはあまり強いモチベーションにはならなかった。だから、ちょっと大袈裟な言い方をすると、この中動態という概念が存在していないがために苦しんでいる人たちがいる、と思ったんです。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、本当にそう思って書き始めました。
池田 そうした具体性と、高度に概念的な議論を結びつけるところが國分さんらしいですよね。『暇と退屈の倫理学』にしても、きわめて日常的な「退屈」という感覚を哲学的に掘り下げていくわけですし。
ところで、今言われたように、中動態という概念を使うと、ある意味なんでも説明できるようにも思えてしまうところが、この本の魅力であり、同時に厄介なところでもあるのかなという気がします。これは何度も注意を促されていることですが、中動態というものを能動と受動の間にあるものとして考えたくなってしまうところがある。むしろ重要なのは、現代において支配的な行為の捉え方として能動/受動の対立が一方にあり、それとは別のあり方として、かつて能動/中動の対立があった。そのパースペクティブの変化を捕まえる、ということが本の中で丹念に議論されているわけですが、これを実感するのはなかなか難しくもあります。
國分 それはやはり歴史というものを実感しつつ頭で理解することの難しさだと思います。この本は僕の中で、初めて歴史について書いた本だという気持ちがあるんです。歴史記述の難しさとは、自分もその歴史の中にいながらにして、その歴史を自分で記述するということです。中動態を理解することの難しさはまさしくそれなんですね。中動態が抑圧された歴史の中にいて、その歴史の中で考えながら、中動態を思い描かないといけない。能動/受動の対立でしか僕らは考えられないから、口先では何とでも言えるけれども、なかなか体でわからない。能動/中動から能動/受動へと対立そのものが変更されてしまうということは、説明されればわかると思うんですけど、それによって主体に変更が起こるまでには非常に時間がかかると思います。
今、この中動態という言葉が誤解されて使われているところもあると思いますが、それは仕方ないし、誤解がたくさんあるってことは広まっているということでもあるから、その意味では問題ないと思っているんです。『中動態の世界』はとにかく世に出たわけだから、誤解した人がいたとしても、「ここを読めば書いてあるでしょ」と訂正できる。その準拠点を作れたので、多少の誤解があっても大丈夫かなという気持ちがあります。
中動態という名称の「起源」
池田 中動態という言葉を、能動と受動の中間としてぼんやりイメージしてしまう、その大きな理由が「中動態」という名称の問題だと思うんですよね。第2章ではこの問題についてかなり込み入った議論がされていて、なかなか読むのが大変なところです(笑)。
國分 あそこはすごく苦労したところですね。
池田 あの箇所がわからないと中動態というものが能動と受動の中間的なものとするイメージから逃れがたいとも思うので重要なところかと思います。ポール・ケント・アンダーセンによるディオニュシソス・トラクス読解が大きなキーになっていますが、この議論をかいつまんで教えていただけますか。
國分 まず中動態はギリシア語ではメソテースですよね。これは中間的という意味で、たとえばアリストテレスの言う有名な「中庸」もメソテース。よく使われる言葉なのです。この言葉を文法用語として「中動態」と訳すのを誰が始めたのかはわからないわけです。ただ一般的には、トラクスの『文法の技法(テクネー・グランマティケー)』でこの言葉が使われていて、後世に大きな影響を与えたと考えられています。ところが、このトラクスの能動/受動/中動についての説明は全然すっきりしないものになっている。というのも、最後の中動だけ4つ例が出てくるのですが、それが中動態の例ではなく、その内の最初のふたつは能動態なんです。そんなわけのわからないことをごまかして現代まで来ているわけです。
アンダーセンによる議論は明快で、彼はまず用語の翻訳の仕方に注目した。能動態/受動態/中動態と訳されてきたエネルゲイア/パトス/メソテースをそのように訳してはいけない、と。実際、ギリシア語には基本的に動詞の活用はふたつしかない。だからメソテースという言葉が中動態を指すというのは後世の誤解で、この語は例外を名指すために使われているというわけです。そうすると、メソテースの4つの例が中動態の活用をしていないことの意味がよくわかる。
本の中では反復的起源という言い方をしました。トラクスがメソテースという言葉で中動態を名指してしまったのが誤解の起源であるわけではないし、トラクスはおそらくそんなことはしていないんです。そうではなくて、後世の学者が何度もトラクスを翻訳したり注釈を書いたりしながら、自分たちの頭の中にある能動と受動の対立構造──ということはつまり中動態を両者の間に位置づける見方──を疑うことなくそこに投影してきた。それによって能動態/受動態/中動態という三区分のパースペクティブが強化されてきたという奇妙な構造がある。ここはデリダ的な、反復される起源のようなものをイメージしながら書いていました。
池田 すでに能動/受動になった視点からトラクスを翻訳し直すときに、エネルゲイア/パトスを能動/受動の意味で翻訳し、そのどちらでもないものとしてのメソテースを中動とする、と。ここでは非常に密度の高い検証をされていて、独特の文体の息遣いが感じられました。
國分 あそこは自信を持って書いたところなのですが、あまり取り上げられないので、そう言ってもらえてうれしいです。あの本は買っても最後まで読んでもらえないだろうと思っていて、なぜなら第2章で絶対に挫折するから(笑)。トラクスについても資料をかなり集めましたが、日本では研究者もかなり少ないようです。でも流石にヨーロッパではギリシア文法自体がしっかりとした研究対象としてあるので、いろいろサーベイしていくなかでアンダーセンの論文も見つけられたんです。やはりがんばって探していると、助けてくれる論文が出てくるものですね。
意志は「ヤク」のような作用を持っている
池田 能動/受動のパースペクティブ自体の問題と同時に、副題にも入っている「意志」という言葉と「能動」との分かち難い結びつきが強調されています。意志、つまりwillは英語を習う初歩の段階で、不思議に思うわけですよね。未来を表すと同時に、意志という意味を持つ。
國分 willという言葉が未来を表す助動詞であると同時に、意志を意味する名詞、あるいは意志することを表す動詞であるということについては、アレントが『精神の生活』の中でも書いています。未来と意志を結びつける我々の思考の前提のようなものが英語の中にははっきりと現れている、と。それは英語のネイティブ・スピーカーではないアレントだからこそ、非常に敏感に気づいたということだと思います。
僕の本の中でひとつのキーであると同時に、「これで絶対に正しい」とは確信できていないところがあって、それは能動/受動のパースペクティブの登場と意志の登場が並行している、と主張しているくだりなんです。何の証拠もないですからね。わかってもらえるように工夫して書いてはいますが、そこは議論の余地がある。この話を書いている時も歴史を記述することの難しさについて考えていました。それは、歴史に関してWhy(なぜ)は言えないということです。Whyの問いを立ててそれに答えることは歴史をひとつの要因によって説明することであり、それは単純化です。人間はどうしてもWhyと問わざるを得ない。それに対する答えをもらって安心したいと言う気持ちがどうしても出てくる。しかし歴史はWhyを斥けるものだということを肝に銘じておかねばならないと思っています。
歴史はWhyを斥ける。けれども、歴史について、How(どのように)と問うことはできます。つまり、中動態がどうやって消えたとか、意志という概念がどうやって発生したかというふうに。このことをいちばんよく考えたのはフーコーを読んでいるときでした。18世紀末に監獄が誕生した際に、それまで様々な刑罰の可能性があったし、それは盛んに論じられていたのに、その可能性は突如消え去り、監獄──正確には罰金と死刑を両端とする刑罰の間を占めるものとしての監獄──が刑罰の中心に据えられる。『監獄の誕生』を読んでいると、「なぜなんだ!?」という気持ちがすごく出てくるんですけれども、フーコーはそれがなぜかについて何ひとつ述べていないんです。皆さん、あの本を読み直して欲しいと思います。驚くほどに抑制的に書かれているんですよ。フーコーが述べているのは、いかにして監獄が現れたのか、ということだけです。
僕もフーコーに倣ったところがあります。ギリギリのところまでしか言わなかった。つまり古代ギリシアには中動態があり、意志の概念はなかった。その後、能動態/受動態の対立が前景化していく。そして同じようにして、意志の概念も強いヘゲモニーを獲得していく。そこまでしか言えません。
池田 過去を断ち切って、前だけを向いて行動することと意志との結びつきが言われていますが、アレントの議論を通じて、こうした意志概念がきわめてシャープに切り出されていくところは、この本のひとつの読みどころかと思います。
國分 あそこは書いていて何か「わかったぞ」と思えたところでした。精神の中に「無からの創造」なんてあるはずないのに、それがあるかのようにするのが意志という概念の非常に巧妙なトリックなわけですよね。意志の概念に関しては、この本を出してから考えが進んだところがあります。おそらくアレントが言うようにキリスト教が、つまりパウロやアウグスティヌスが意志というものを作ったのは間違いない。そしてそもそも、「無からの創造」であるという意味で意志はキリスト教と切り離せない。僕たちはそんなことはもちろん意識していない。けれども、矛盾に満ちたこの概念を使わずにはいまの社会は成立しないようになっている。すると、僕らの社会はある意味で意志を信仰しているのではないだろうか。現在我々の生きている文明は意志への信仰を基礎としているのではないだろうか。そういうことを考えるようになりました。
ここで僕は意志という概念を非常に強く批判しています。現在というものは過去とつながっていて、それを意志によって断ち切れると考えるのは間違いだという議論をしているわけです。でも、これは熊谷晋一郎さんとの議論の中でわかってきたことですが、あまりにも過去が辛くて、切っていかないと生きていけない人たちがいる。小さいときに虐待を受けた人がPTSDを抱えていて、そういうものから逃れるために薬物やアルコールを使うようなケースがある。意志は同じような役割を持っていると思うんです。意志って「ヤク」ってルビを振ることができると思う。意志にある種の効用があるのだとしたら、それを単純には否定できない。
池田 よくわかります。本の中では切断的な「意志」に対して、周囲の状況を見つめる「意識」というものに比較的に肯定的な意味が与えられていますよね。ですが例えば鬱のケースにしても、周りの目を過剰に意識しすぎてしまう、あるいは過去に取り憑かれるような状態になってしまい、そのぬかるみの中で足が動かなくなってしまう、という状況も多いと思うのですが、この点に関してはいかがでしょうか。
國分 それは千葉雅也さん的な問題ですね……。大雑把な言い方ですが、千葉さんは意識しすぎてしまう、つながりすぎてしまう、ということに対して切断の必要性を訴えたわけです。先日、東浩紀さんも交えて3人でお話していたのですが(鼎談「接続、切断、誤配」、『ゲンロン7』所収)、僕のほうはあまりにも強い近代的主体の抑圧をなんとかしたいと思っているのに対し、千葉さんの場合は、そういうものはまったく信じられず、むしろグダグダに主体が溶解してしまうポストモダン的状況がデフォルトの状態になっていて、おそらく課題としているものが違うのでしょう、と。
池田 でもそれは同じ事態の表と裏という感じもします。単純化した言い方ですが、鬱のように意識しすぎて動けなくなってしまうときに、千葉さん的にかろうじて切断するということが必要になり、しかしそれが躁状態に振れて過剰に決断的になると、今度は國分さん的に連続性を言う必要が出てくる。
國分 そう思いますね。そのときに、どちらも仮置きとしての主体を考えている気がします。自分の身体や精神も、仮置きだと思うんですよね。いつも状態は違うし、加齢とともに変化していく。仮設であるということを自分の中で飲み込んで、その仮設的な主体をどうやって上手く使っていくか、あるいは一人ひとりがどう発見するか、ということが必要かと思います。強い主体でも確たる主体でもない、仮設としての主体。

「したい性」と「します性」
池田 意志的な確固たる主体ではない、仮置きとしての主体ということで思い出す映画のシーンがあります。神経学者オリバー・サックスの臨床経験に基づく原作による映画『レナードの朝』は、一時期流行した嗜眠性脳炎による意識障害者が集められた神経科病棟を舞台にしています。
少し古い作品なので病棟での描写に問題がある気もしますけれど、ひとつ印象的なシーンがあります。ようやく少し歩けるようになった患者が、なぜか途中で止まってしまい、そこから先に進めなくなる。実は患者が進もうとしている床は白黒のマス目状のパターンで出来ていて、そのマス目が途切れてしまっていて、そこから先に進めなかったわけですね。そこで床にマス目を描いて延長してみると、その先まで行けるようになる。これは、いわゆる自由意志を持った主体ではないかもしれないけれど、周囲の環境とともに仮の主体のようなものを立ち上げていく例であるようにも思います。
國分 その話は、熊谷さんたちとよく話をする、自閉症的な知覚のあり方と結びついている気がします。自閉症の場合、知覚の解像度が違うと言われるんですね。解像度が粗いと簡単に行為することができる。邪魔するような知覚がないから。駅に向かうとき、「ああ、向こうに駅がある」とただそう知覚して、駅に向かうことができる。ところが、知覚の解像度がすごく高い場合、たとえ駅が見えたとしても、そこにたどり着くまでにあまりにも多くのことを知覚してしまい行為が妨げられてしまう。情報量がありすぎて行為できなくなるわけです。自閉症の人はコミュニケーションの障害というふうに言われるけれど、そうではなくて、定型発達の人との知覚の解像度のズレが問題になっているのです。人間が情報を処理できる能力には限界がある。だから、解像度の高い人の場合、何らかのパターンを頼りに行為することになります。床のマス目というのも同じパターンの繰り返しですから、それが行為の頼りになるのかもしれません。
これは綾屋紗月さんの本に書いてあるのですが、綾屋さんもアスペルガー症候群の当事者であり、常に行為の困難を抱えてきた。例えば、彼女から、お腹が空いたということがわからないという話を聞きました。お腹が空いたと言っても、身体が発するサインは様々ですよね。普段僕らはそういう多種多様なサインをボンヤリとマクロ的に知覚し、まとめあげて「お腹がすいた」という認識を得ている。でも、知覚の解像度が高いと、一つひとつのサインが謎めいたものとして現れてきて、なかなか単純なマクロ的認識にたどり着けない。
そのときに綾屋さんは、「何々したい」ということを、うまく作り上げられない、と言います。それを彼女は「したい性」と名付けています(これは「主体(しゅたい)性」との言葉遊びになっているのかなと思います)。「したい性」がうまく発動しないときはどうすればいいか。彼女はそれに対して、「します性」というのを作るわけです。何時になったら「何々します」と決めてしまう。お腹が空いたからご飯を食べる、とやっているといつまで経っても食べられないので「12時になったらご飯を食べます」と決める。
池田 行為のガイドラインを外側から作ってしまう。
國分 そう。ただ僕らの日常生活の中で問題になるのは、もはや「したい性」すら意識できないということかもしれないですね。『中動態の世界』での権力の話のような、「したい性」と「します性」が重なっている状態というか……。
池田 一時期よく言われたアーキテクチャ型権力というのも、環境を通じて、意識されない内に人々の行為をコントロールしている、というものでしたね。
國分 まったくその通り。だけどアーキテクチャの話は少し狭い感じがしているんです。この本で書いたことだけれど、非自発的同意というのは我々の行為のすべてを覆っているのではないか、という気すらするわけです。アーキテクチャによる操作ということになると、操作される部分と、そうじゃない自由な人間の行為という対立が出てくるのではないでしょうか。そこが、僕があの議論に懐疑的なところで、フーコーの極度に抽象的な議論のほうが、むしろ社会で起こっていることを具体的に記述できる、という感じはあるんです。
例えば同僚とご飯を食べにいって、同僚が蕎麦を食べたいというから仕方なく蕎麦にする場合。これは自発的なのか、そうでないのかというと、どっちでもない。このときに、もうひとつ「同意しているかどうか」という軸を持ってくればいい。この場合、自発的ではないかもしれないが同意はしている。同意は僕らの行為を極めて深いところで規定している概念だと思います。
デカルトとスピノザの違い
池田 本の中で困っている人にお金を渡すこととカツアゲの区別が言われますよね。能動/受動の対立で言うと、渡しているという意味ではどちらも能動と見なされかねないわけですが、能動/中動のパースペクティブを通じて、行為している人の内側に、どのようなプロセスが働いているかを議論できるようになる、と。このときにスピノザを参照しながら、自閉的・内向的なプロセス、つまり自己の内側への巻き込みの次元が出てきます。ともすると國分さんの議論は「私」というものが世界と連続的になってすべてが一体となるようなものにも思えるわけですが、最後にもう一度、個体の内的なプロセスが強調されるのは少し意外にも思えます。
國分 なるほど、そうですね。世界のすべてがひとつの実体に包み込まれているのだから、すべては神という実体が形を変えたものに過ぎず、すべての個体が神の中に溶けていってしまう、という見方は非常に凡庸な誤ったスピノザ理解として、よくあるパターンです。スピノザが個体の本質の話をしていることはいつも見落とされています。スピノザは個体には本質があるし、さらにその本質は永遠だ、とまで言っている。書いているときにはそこまで考えていませんでしたが、自閉的・内向的プロセスという言葉がしっくりきたのは、おそらくスピノザの持つ個体性の次元というものを強調したかったからです。中動態の世界は、いろんなものを混ぜこぜにしてしまうものではないわけです。
やはり「私」という本質があって、それが「私」に行為させている。かといって、その「私」という本質は世間から切り離されているわけではない。これは簡単なようでいて、理論的に言うのはなかなか難しい。僕の議論は極めて簡単に出来ていて、つまり変状のプロセスは二段階だ、というものです。外部から影響の起こる段階と、自分の中で変状が起こる段階は違う、というただそれだけのことなのですが、このふたつを区別することによって、あらゆる個物が実体の変状であるというスピノザの存在論と、「私」が本質を持っているというスピノザの個体性の議論とが結びつくわけです。
それはスピノザ解釈の問題だけではなくて、中動態の世界をどう考えるか、ということでもある。先ほど池田さんが例として出してくれたように、困っている人にお金を渡すのとカツアゲで渡すのとの区別は、「私」の本質を導入しないとうまく説明できないわけですね。そういうことを無視して能動か受動かだけで行為を決めるのは非常に雑な見方で、内向的・自閉的プロセスを考えることが、中動態の世界を位置づける上でも決定的に重要なわけです。
池田 そうした個体性の次元が「本質」という概念で最後に登場するのは興味深いです。
國分 そのときにひとつ重要なポイントがあって、スピノザの考え方が僕らと大きく違っているのは、本質の表現というところです。本質の表現は客観的に確認できないものなんです。『スピノザの方法』で書いたことですが、これはデカルト的な真理観とスピノザ的なそれとの違いなわけですね。デカルトの場合、科学主義的に反証可能なものだけを真理と認めていて、それをもっと陳腐にすると今のエビデンスということになるでしょうが、そういうものだけが真理であると。スピノザの場合、真理を認識している人には、それが真理だとわかる、と言ってしまう(笑)。
池田 それはすごいですね(笑)。
國分 『エチカ』にそうはっきりと書いてあります。「真の観念を有する者は(中略)そのことの真理を疑うことができない」と言うのですが、これは明らかにデカルト的真理観に対する批判なんですね。あるいは、スピノザとデカルトのパーソナリティの違いでもある。スピノザは公的に反証可能なかたちで提示される真理しか真理と認めないという近代の考え方を真っ向から拒否している、ということなんですよね。
もちろん一方で科学のやり方は大事です。けれども、反証可能性のもとでしか真理を認めないから、非常に狭い物事しか扱えない。ここで言っているような本質の表現なんて扱えない。こうした考え方によっていろんなものを近代は多くのものを投げ捨ててきたわけで、そこで失われたものを取り戻さないといけない、というモチベーションは昔からあるんです。
フェルメールとトーマス・ルフ
池田 美術の世界でスピノザとともに言及されるのは、同じ1632年の生まれと言われるフェルメールですよね。ジャン=クレ・マルタンは『フェルメールとスピノザ <永遠>の公式』の中で、《天文学者》の地球儀に触れる男を、あれはレンズを磨くスピノザなんじゃないかと言っていたり(笑)。
國分 あれは夢があっていい本だよね(笑)。
池田 印象論的な話ですが、フェルメールの作品はどこか國分=スピノザ的なビジョンと通じるところがあるのかな、という気もします。フェルメールにおいて行為の中断がよく描かれます。チェンバロを弾いていて、ふとこちらを向くとか、下を向いて作業をしていたところに光が差してきて窓の外を眺めるとか。
國分 ラブレターが届いたりね。
池田 そうですね。なんらかの行為に集中しているんだけれども、そこでふと外的なものに触れたときに行為が中断されて宙吊りになる、その一瞬を描く。カラヴァッジオのようにすべてがガチガチにドラマチックにキマっているというのでもないし、晩年のレンブラントのようにひたすら内面への深い沈思があるというのでもない。窓辺に光が差してきて、ある行為がふと途切れて何事かに思いふける、夜の実存的な深みとは異なる、午後の光の明るい内向性というか…….。
國分 たしかに「私」というものを考えるときに、光学的なイメージを持っています。光学って焦点を合わせることでそこにないものが現れるわけですよね。存在していることとは違うけど、そこに何かが見える。だから「私」のようなものも、実態というよりは光学的な効果として見られるものだと思うし、意志というのも、そうかもしれない。
マルタンがあの本で、フェルメールがやたらと額の広い女の子を描いたのは、レンズが曲がっていたからではないか、という斬新な説を出していて(笑)、でもあれはすごく納得したんです。ああいうのを見ていると、物を写し取るとかいうことを全然考えていなくて、映った光をトレースしているというような感じ。フェルメールの絵って、すごく精巧に見えるけれど近くで見ると結構ぼんやりしてますよね。
池田 シャープにピントが合うギリギリ手前、という感じ。微妙にピントがずれているからこそレンズの透明な厚みを感じさせる。
國分 ハイデッガーの『芸術作品の根源』だとゴッホの農民の靴に存在がある、という感じですが、フェルメールは全然そういう感じではない。フワーッと明るくて、電気を切ると消えるんじゃないかという(笑)。それはたしかに僕の考える、仮置き的な主体のイメージと合うような気はします。
池田 外的な情報に知覚を合わせていくことで現れる仮置き的な主体ということでは、知覚の解像度を床のパターンに合わせることで行為が成立する、というような話とリンクしそうな気もします。フェルメールの床も白黒のマス目ですし(笑)。
國分 昔から解像度には関心があるんですよ。jpegのシリーズをやっているトーマス・ルフの写真なんかも好きですね。遠くからみると綺麗な土星の写真なんだけれど、近づいて見るとピクセルが見えてきたり。あれは僕らの知覚というのはいったい何なのだろうと考えさせる。
池田 あるいはネット上のポルノ画像を、それと判別できるギリギリまでぼかしたり、日本の漫画やアニメをデジタル加工して抽象画のようにしたり。これらも基本的に解像度の操作ですね。國分 そう、しかもルフの場合、アウトプットされたものが信じられないほど綺麗なんだよね。
「退屈」とは何か
池田 『中動態の世界』のあとがきにもありますが、『暇と退屈の倫理学』でハイデッガーの退屈論を大きく取り上げたことが、医療関連の分野で中動態への関心を膨らませていく、ひとつのきっかけとなったそうですね。先ほど言われたような『中動態の世界』での周囲から切断された意志概念は、『暇と退屈の倫理学』での決断主義のありようと重なっているようにも思います。このふたつの本の結びつきについてはどのように考えられますか。
國分 ふたつの本に共通するものとしてはっきり言えるのは、意志や決断することへの批判です。意志や決断を批判するというと、「じゃあ、ダラダラするってことかい」という反応がたまにあるんですけど、全然そういうことではない。最近、決断と似ているけれど違うものとして「覚悟」という言葉のことを考えています。宮台真司さんが使っていて気になったんです。覚悟は言葉の響きとして決断と似ている。けれども両者は全く異なります。決断も意志も流れを断ち切るわけですが、それに対して覚悟とは、自分のいる流れを自分で引き受けることです。全く逆なのです。だからこれは『中動態の世界』から取り出せる倫理のあり方かもしれないし、『暇と退屈の倫理学』であれば、退屈の第二形態から導かれる行為のあり方にもなりうる。
ハイデッガーは退屈の第二形態について、パーティーの中でボケッとタバコとか吸いながら空虚になっている時、そこには正気がある、と書いているんです。これに対して退屈の第一形態では、たった4時間も駅で待っていることができず、気晴らしをしようとしては失敗して、彼は自分の元にいない、ある種の狂気だと。
池田 周囲の状況や過去の引き受けの前提として、ワーカホリック的な狂気ではない、パーティーの中にあるような「正気」が必要だと。
國分 そう、第二形態が正気だというのは、つまらない話かもしれないけれども、自分を見つめるだけの時間も能力もある、ということです。そして自分を見つめるところから何かを引き受けるというところに行けるかもしれない。
こうして覚悟や引き受けというものを決断や意志との関連で考えると、ニーチェの運命愛という概念が非常にわかりやすくなります。あれはわけのわからない概念で、つまり戦争が起こってもそれを運命として受け入れる、というふうに理解されかねないわけです。そうではなく、意志や決断によって誤魔化さないで、自分が今いる中で物事を引き受けていくものと考えれば、運命愛という概念がずいぶん身近になる。
池田 「正気」という言葉もそうですし、美や快もこの本では重視されていますよね。このシリーズ第1回目の星野太さんとの議論の中でも話していたことですが、特に70年代以降の美学的パラダイムでは美よりも崇高が重視され、アートにおいても90年代ごろから快原則の彼岸にある死への欲動やリアルなものへの注目があったように思います。つまり感性や快原則のリミットが盛んに論じられ、むしろ美や快といった概念は、いわば保守的なものとして退けられてきたとも言える。國分さんによる美的なものや快への注目は、とても興味深いと同時に、結論だけ見ると何か当たり前のことが言われているように思われかねないですよね。
國分 70年代くらいから現代思想の中で「分裂病」に特権的な地位が与えられていましたよね。この人間の極限にこそ、人間の真理がある、というような話です。完全に現代思想によっておもちゃにされていたと思いますが、そうした極端なものに人間の真理を見出す議論というのはロマン主義の別バーションだと思います。僕はそういう分かりやすく刺激的なものに強い警戒心があります。たとえば、ポストモダニズムが流行ったときも、ポストモダニズムってモダニズムの運動が終わってしまったわけだから、何もかもがつまらなくなるという話だったはずなのに、ポストモダニズム自体がなぜかやたらと刺激的なものとして受け止められた。そこでも実際に僕らが生きている日常的なものが忘れ去られていたわけですね。
以前、千葉雅也さんが松本卓也さんとの対談で『暇と退屈の倫理学』を取り上げてくれていて、「日常への回帰」という言い方をしていたのですが、僕はたしかにロマン主義的な極端主義では捉えられないようなものに魅力を感じていて、それは一貫しているように思います。ハイデッガーも現存在の日常的なあり方を問題にしていたわけですよね。
池田 退屈とは何か、とか(笑)。
國分 そう、ダラダラおしゃべりして頽落している、と。そういう分析に非常に共感するんです(笑)。ポストモダニズムの極端主義を見ていると、「人間そんなに刺激に曝されて生きていけないでしょう」というごく当たり前のツッコミを入れたくなる。そこを具体的に論じたのは『暇と退屈の倫理学』の増補版の付録でのサリエンシーの話で、つまりサリエンシーが高すぎると人間は生きていけないという議論を、退屈の問題も踏まえて、もう一度定式化したものです。
池田 サリエンシーの議論は重要ですよね。特に日本では、歴史的構築性を否認して、とにかく自爆的に破滅に向かうものこそが真の芸術だとか思われているところがあって(笑)、でも実際には、そんなに破滅に突き進みながら制作なんて続けられないわけです。國分さんの議論を踏まえて言えば、あらゆる人間が生きていく過程で無傷ではいられないのだから、そこでサリエンシーを極端に高めて傷を覆い隠すような仕方ではなく、むしろその傷を自分固有のこだわりへと変化させ、そこに断続的に向かい合いながらコントロール可能なものへと馴致させる、そうした技術として制作というものを捉えることも可能かもしれません。

池田剛介
人間と動物は同一か否か
池田 ところで『暇と退屈の倫理学』では、退屈や日常性の議論と並行して重要なものとして、人間と動物をめぐる議論があります。人間は動物のように固定化された環世界に浸りきることができず、だからこそ退屈から逃れられない。だけれども、ひとつの環世界に浸りきることができないことこそが人間的な自由の条件でもある、と。
國分 哲学の中には、人間は動物と一緒だという議論と、人間は動物と違うという議論の両方があって、環世界論の便利なところは、両方を取り入れられるところです。環世界を移動できるという点では動物も人間も変わりないけれども、人間は相対的に環世界間の移動能力が高い。あまりにも高いから、量の差異が質的差異になっている。
しかし同時に僕は『暇と退屈の倫理学』の最後の方で、人間が動物になる、という言い方もしているんですよ。それはこの本の中でいちばん自信がないところでもあって、はたしてそういう表現で良かったのかなと。ただ直感としては人間と動物の違いを見た上で、でも人間が動物のようになることはある気がするんです。人間か何かに熱中しているときって、人間が人間じゃなくなって、どこか動物になっているんじゃないか。もしかするとそれは僕の恣意的な言葉の使い方かもしれなくて、そういう意味で自信がないのだけれど……。
池田 本能への囚われとは異なる動物的な熱中ということでしょうか。ここでの「動物になること」は肯定的に言われていますよね。
國分 肯定的に言っているのですが危険性もあると思います。熱中するということは強い快楽をもたらすけれども、非常に危険なものでもある。つまり人間は熱中することもできるが、冷めることもできる、と。でもそれでいえば、動物も熱中できるかもしれないんですよね。ダーウィンがミミズの研究の中で書いているのですが、ミミズは光や振動に敏感で、普段だと地面を踏んづけたりするだけで隠れてしまう。だけどミミズがセックスをしているときには、なかなか隠れない(笑)。
池田 (笑)。同じくハイデッガーの動物論を扱っているアガンベンの『開かれ』でも、ティツィアーノの晩年の絵画を挙げながらセックスの話をしています。あれはニュンフと牧童がセックスの後で何もせず、無為に横になっているのだ、と。絡み合うと同時にすれ違い、親密であると同時に互いに無関心でもあるようなふたりの、性的充足の後の沈静した覚醒のようにも言われていて、退屈の第二形態の議論と通じるようにも思います。
優れた芸術家は新しい「効用」を発明する
池田 一方で國分さんの場合は、アガンベン的にやたらと高級な無気力という感じではなくて(笑)、ウィリアム・モリスのような、より生活に結びついた仕方での美や快のほうにこだわられているようにも思います。なんと言うんでしょう……普通であることの徹底というか。
國分 ええ、でもそれは別に戦略的にやっているわけでもなくて、単に僕がそういう人間だからだと思います。REALKYOTOというアートの媒体に合うかどうかわからないですが、なんとなくハイカルチャーな話について行けない、ついて行きたくないという気持ちがあって。モリスのように、芸術をこれまで特権階級が占有してきたけれど民衆の芸術を考えないといけない、という発想には共感するんです。
池田 モリスのようなクラフトやデザインであれば生活と直接結びついていて、その意味でも中動態で言われたような周囲との連続性を重視するところとも通底するのだと思います。他方でアートは、普通の意味では生活から切り離されていて、クラフトやデザインのようには生活の役に立たないわけですよね。あえて聞くわけですが、そのときにアートの持っている積極的な意味を考えられたりしますか。
國分 そうですね……例えばルフなんかも、数年前に知って面白いなと思ったわけですけれど、僕にとっては何というか、健康にいい、と感じなんです(笑)。
池田 それはすごい(笑)。
國分 ゴダールなんかも見ていると頭がどんどん冴えていって、目が良くなる感じがする。映画を見ていて全然違うことを考えてしまうんです。美的なものは、やはり快なんだから何か心身にとってよいものがあるんじゃないでしょうか。あとこれはカントが言っていますが、美の経験って純粋に想像力の経験じゃなくて、そこに必ず悟性が入り込むわけですよね。想像力が唯一自由に作動して生み出されるのが美なわけですが、そこには必ず悟性的な概念が入ってくる。つまりそこに言語が入るわけですよね。
池田 カントの美的判断力の場合、想像力が概念の規定なしに自由に働いて、悟性もまた概念なしに働いて協調する、と。例えば「この作品は美しい」と感じるときには、あくまでも個別の感覚に基づいて感覚されるしかないわけですが、その個的な判断が同時に普遍性を要求する。つまり「この作品は美しいでしょ」と誰かに伝えるように、個別的判断にとどまらず言語を通じて社会化されるものでもある。
國分 もし言語的なものがまったくない純粋な美の経験というものがあるとすれば、これは預言者の啓示のようなもので、人に伝えられないんですよ。それはたぶん苦しい経験でしょう。カントも言っていますが、いいものを見たら絶対に人に話したくなる。でもそれは当たり前のことで、想像力と悟性が手を結んで美の経験があるから、ある程度は言葉にすることもできて、それを伝える快楽もある。だから批評家の役割というのは、美の純度が高くてなかなか言葉にできないものを、うまく言葉にすることだと思うんです。
ところで芸術の効用みたいな話は、あまりされないのでしょうか。もちろん芸術が効用に還元されてしまったらダメだけれど。
池田 そうですね……あったとしても、その効用がエビデンス的になってしまうんじゃないでしょうか。アートでこれだけ集客して地域が活性化しました、とか(笑)。もっと別のレベルでの効用を考えることもできると思いますけれど。
國分 先日、写真家の金川晋吾さんに展覧会での対談に呼んでもらって作品を見てきたんです。あれは一体何の効用があるのか……。ただとにかくあれを見たとき、僕にはものすごい解放感があったんです。自分が自由になる感じがあった。
池田 蒸発するお父さんの写真ですね。
國分 そう、それがお父さんの顔の写真に現れている。必ずしもその背景にある話を知らなくても、何かが顔に現れていて、それが人に解放感を与えるんですね。どんな芸術も解放感を与えるとは思わないけれど、やっぱり優れた芸術家は、新しい効用を発明するということなのかな。
洞窟壁画はどのように描かれたか
池田 『暇と退屈の倫理学』に話を戻しますが、生活のあり方と文化的なものの結びつきについて、定住が始まった新石器時代にまで遡って議論されています。アートをめぐる議論は、ここ5年10年の動向がどうだとか今何が流行っているだとか、そういう話になりがちでもあるのですが、それとはまったく別のスケールで文化や芸術の意味を捉えなおす意味でも示唆的かと思います。
國分 でもあの本での定住革命によって芸術が始まるという話は、今となってはちょっと間違っていると思うんですよね……。暇になったから絵を描いたとか、そんな消極的な理由じゃないでしょう(笑)。やはりもっと積極的な理由があるんじゃないでしょうか。
池田 それはラスコーなどの洞窟壁画についてですか。
國分 そう、旧石器時代の壁画には関心がありますね。
池田 日本では港千尋さんなどが紹介しているデヴィッド・ルイス=ウィリアムズは、洞窟壁画が描かれた状況が、かなり過酷な環境であったことを重視しています(『洞窟のなかの心』)。神経心理学の知見に基づいているのですが、例えば薬物などを使って意識の特殊な状況を作り出したときに見えてくる幾何学的なパターンが、洞窟壁画に描かれたそれと類似していることが言われています。つまり壁画を描くときに、ある特殊な意識状態の中で見られる人間の脳に内在するパターンを利用していたのではないか、と。実際、洞窟壁画というのはものすごく狭いところで描かれていたり二酸化炭素の濃度が異常に高かったりという環境で描かれていて、たしかに暇だから描いたというのとは違う気もします。
國分 命がけなんですよね。僕の場合はラスコーに描かれた動物のような写実的なものに関心があって、今見ても何の遜色もなく魅力的。初期キリスト教の絵画って、単純な記号だけで描かれていて下手なマンガみたいなところがありますよね。ああいうのに比べると、洞窟壁画の場合、本当にそこに存在があるというか……人間は一回退化して、もう一度戻ってきたんじゃないかという気すらする。
池田 ルイス=ウィリアムズの議論でも時代状況の変動は重要で、特に中期旧石器時代と後期旧石器時代の端境期は、現生人類がヨーロッパにやってきて、ネアンデルタール人との接触が起こった時期なんですよね。そうやって社会が複雑化していく中で現生人類の意識構造や言語が発達して、高度な壁画が生まれる素地になったと言われてもいます。つい先日、スペインで見つかった洞窟壁画はネアンデルタール人が描いていたんじゃないかという大きなニュースが出ていて、現生人類中心主義も揺らぐことになるのかもしれませんけれど。ともあれラスコー壁画でも、洞窟の中の岩が迫り出している部分を利用しながらバイソンを表現したりしていて、それこそ見ることと対象との間に現れる光学的な効果と言えそうです。
國分 光のことはずいぶんわかっていた気がしますよね。揺れ動く火の中で見るから、ムービーのようだったらしいし。
池田 あるいは口から顔料をスプレーのように吹きかけて、ネガティブな手形を残していたり。しかも顔料の毒性も強いらしくて何でそんなに大変なことをしたんだろう、と。シャーマンによる制作も指摘されていますが、謎が多いですよね。
國分 なぜ人は命をかけて芸術を作るのかってことですよね。洞窟の狭いところによじ登って、いつ死ぬかもわからない状況で描いている。それを考えると、やっぱり暇になったから始めたというものではないと思うんです(笑)。

想像力とコミュニケーション
池田 先ほどのカントの判断力や、あるいは解像度の議論なども関わるかと思いますが、最近は自閉症に関連して想像力に関心を持たれていると伺いました。シンプルにお聞きすると、ここで言われている想像力とはどういったものでしょうか。
國分 これはまさしく研究を始めたばかりなので、まだぼんやりとしたことしか言えないのですけれど。自閉症は他人の心が想像できない、想像力の障害であると言われますが、これは端的に間違っている。先ほども言ったように、知覚の解像度にズレがある場合にうまくコミュニケーションができないということであって、いわゆる「健常者」が自閉症の人の心を理解できないように、自閉症の人が「健常者」の心を理解できないだけです。どっちが悪いというわけでもないのに、勝手にマイノリティのほうに責任を押し付けているわけです。
ただ想像力の働き方に、知覚の解像度は関係しているかもしれない。想像力というものを僕らはひとつの能力として思い描くし、たとえばカントはそう論じたけれども、実際には想像力には量や質や強度など、様々な差があると思うんです。
ドゥルーズの無人島論は、一度もイマジネーションという言葉を使っていませんが、実際には想像力の話になっています。たったひとりで無人島にいる状態では、自分が見ているものしかこの世に存在しない状態になってしまい想像力が縮減してしまう。自分が見ているものと世界が同値の状態になる。逆に言うと、想像力は他者との関係があってはじめて生まれてくるわけですね。
チンパンジーが鏡に写った自分を自分だと認識できるか、という実験が行われていて、生まれたときからたった1匹で育てられたチンパンジーの場合、鏡を見ても自分だとわからないらしい。他の個体と一緒に過ごしていたチンパンジーは、鏡を見て自分だとわかる。さらに不思議なことに、ガラスなどで部屋を隔てて他の仲間が見える状態に置かれながらもひとりで育てられた場合、鏡で自分を自分だとわからないらしい。他の個体を見て知っているだけなのと、混じり合って生活しているのとでは、知覚や自己認識に差がでるらしいのです。これも想像力の問題と結びついていますね。このあたりのことも最近考えています。
池田 あの無人島論の中でドゥルーズは、無人島では他者構造が崩壊すると言っていますよね。僕らは日ごろ、あるものを想像的な他者の視点を通じて多角的に見ることで、物事を立体的に立ち上げていくわけだけれど、無人島で文字通りひとりになって、そうした他者が失われたときに、世界が立体的なまとまりを失って崩壊していく。カント的に言えば、感性によって受け取られる情報が想像力によって表象化されてまとめられるわけですが、想像力が失われると、それがバラバラな瞬間的知覚にほどけていってしまう。
國分 そこでドゥルーズはぼんやりと「他者」としか言ってないのですが、ある想像力を生み出す他者には、もっと複雑な条件があるんじゃないかという気がするんです。つまり単に誰かがそこにいればいい、というだけではないかもしれない。そうすると想像力の起源がさらに複雑化していく可能性がある。
なぜ想像力に注目するかというと、これはカント以来の哲学の中心的な話題だったわけですが、ハイデッガーがカントについて書いた本の中でこれを論じていて、感性という受動的な能力と悟性という能動的な能力には共通の根があるというんです。それが想像力ないし構想力なわけですね。結局カントはこの図式を維持できなくて、『純粋理性批判』の第二版で二元論のほうに持っていくわけです。ハイデッガーはそうなる前の第一版が重要だというわけですが、カントはやっぱり想像力の問題を扱いきれなかったんだと思います。
どうしてかというと、感性と悟性の共通の根が想像力であるとすると、人間の諸能力がいずれも想像力から生まれる、ということになってしまうからです。つまり人間の能力を定義するものとして想像力があって、それ自体もなんらかの仕方で発生する。ドゥルーズが言っていることが正しければ、他者とともに、ということになるし、先ほどのチンパンジーの例で言えば、もしかしたら社会性の次元も含まれてくるわけですね。
池田 松本卓也さんが編集協力した『atプラス30』の特集で、小倉拓也さんがドゥルーズの想像について書かれています。ここでは想像が、瞬間々々に入ってくる知覚を現在性の中に束ねていくものとされていて、老いやアルツハイマーの事例では、こうした想像によって束ねられた現在をストックしていく記憶の次元が失われてゆき、記憶に統合されることのない現在が前景化してしまう。しかしこれはほとんど狂気なわけで、そのとき、想像には何が可能なのか。アルツハイマーの人がしばしば「作話」をするわけですが、これは記憶が失われて自己の連続性がままならない中で主体を仮構する方法かもしれない、と。
國分 外側から連続性の枠組みを作っていくわけですね。
池田 そうですね。ここでの「作話」はファブリケーション(fabrication)なので、仮設的にものを作り上げていく「仮構」の意味を持っている。痴呆症の老人が、そうやって妄想のような話をすることは広く知られているわけですが、例えば介護をするときに、そうした話をこちら側の基準に照らして正してもうまくいかないそうなんですね。むしろそうした作話に合わせていく、ある種の演劇のようにして作話=仮構の世界を受け入れることで介護がうまくいく、といった話もあるそうです。そういう意味でもイマジネーションやクリエイションは、単に自由な芸術制作といったことだけでない、切実な生の問題とも関わっていると思います。
國分 そこで僕が考えているのは政治の問題なんです。インターネット環境が今、非常にいびつな想像力を作り出している。ネトウヨが典型ですね。人間の想像力の可変性をああした存在はよく示していると思う。もうひとつには言語の問題。つい最近、朝日新聞で憲法について書いた文章の中でも言ったのですが、言葉というものの地位が決定的に失墜して、人が感覚だけで動くようになっている。この言語の失墜と想像力の問題はおそらく関係していると思います。
池田 なるほど。僕は想像力というときに、概念による認識の規範性がゆるくなって、物事と物事との別の連結が、例えば痴呆症の作話=仮構のような仕方で立ち上がるようにイメージしていたわけですが、やはり言語的なものとの結びつきを重視するわけですね。
國分 カントの図式で言えば、『純粋理性批判』と『実践理性批判』では、想像力は悟性や理性といった他の能力の言うことを聞いていて、おとなしくしている。でも本当は、全然そんなことなくて非常に自由奔放なわけですよね。しかも存在しないものを存在させることができるのが想像力なわけだから、実はとんでもない才能を持っている。
僕は想像力というこの自由奔放なものが、ひとりの心の中でどういう風に育ってきたのかということを考えたいわけです。きっと言語も関わるだろうし、社会関係も関わってくると思う。あるいはチンパンジーの実験のように、身体的接触が関わっているのかもしれない。想像力は心というOSにプリインストールされているアプリではないんですよね。頻繁にアップデートしているし、気がつくとこのアプリはこのOSでは使えません、ということにもなってしまうような、維持しようとし続けないとおかしくなってしまうものが想像力だと思います。
池田 グローバル化や情報環境によって、僕たちの行為やコミュニケーションが過剰に可視化されることによって、「空気を読め」というような、個々のパースペクティブや解像度の平準化が求められているようにも思えます。
國分 それは間違いなく、そうでしょう。グローバル社会ということで言うと、我々の想像力の範囲を超えて行為が遠くまで届いてしまうのが現代社会の大きな問題だと思います。その辺の店でチョコレートを買っても、もしかしたらアフリカの児童労働に手を貸すことになるかもしれないし、SNSで差別発言したら一瞬にして世界中に拡散される。しかしそんなことを我々は想像できない。行為が想像力をあまりにも容易に超えていくというのが今の状況だと思います。グローバリゼーションの中で想像力がどういう役割を果たすのか、ということについては関心があります。
京大タテカン問題をめぐって
池田 グローバルな話から急にローカルな話になって恐縮なのですが(笑)、REALKYOTOが京都のメディアということで最後にお聞きしたいことがあります。今京都大学で、立て看板、いわゆるタテカンが問題になっています。京都市の景観条例に抵触するのではないかということで、キャンパス外に向けられたものはなくし、学内のものはサイズを規定内にして決められた場所に置きましょう、という話になっている。これもコミュニケーションの平板化のような問題とおそらく関連していて、つまりタテカンのようなわけのわからない異物を管理し均質化させたいという力が、どこかで働いているようにも思うんですよね。景観条例に端を発していることもありますが、それこそ「京都の空気を読め」と(笑)。
國分 最近、「この周辺でビラまきをしたりすると罰せられます」という看板を神奈川県が立てていて、弁護士がそれは憲法違反じゃないかと抗議したら認められて、そのビラまきを禁止する看板は撤去されたそうです。つまりタテカンを禁止するのは、表現の自由の抑圧なんじゃないかという論点が、まずあると思います。だいたい京都市の条例って、何が条例だよという感じですよ(笑)。たかが条例にそれを禁止する権限はないと思います。ただ、これまでやってきたのだからという主張だけでは弱くて、もっと積極的な意義を主張していく必要があると思うんですよね。タテカンだからこそ伝わっていた情報がある。タテカンを通じてその場で情報を共有するという意味があったのではないか。
池田 まさにそうで、あれは勝手に置かれているから、たまたま通りかかった人が偶然的に目にする、ということがあるわけですよね。SNSだと様々なフィルタリングで、その人が関心を持つものばかりに方向付けされてしまう。
國分 住民投票をやったときに、町内会の掲示板が意外と重要だということがわかったんです。あれは非常に重要な社会資本で、いざというときのために残しておくことが大事。普段は全然役に立たないけど何かあったときに使える。タテカンも一緒だと思います。最近SNSで京大のタテカンの画像が流れてきていて、なかなかいいことが書いてありましたが、それを見たある京大出身の先生が、「いいこと言っているが、字がフニャフニャで情けない」って感想を言ってました(笑)。タテカンにはタテカンの流儀があるわけですが、すでに失われかけているのかもしれません。
池田 文化的な継承が必要なわけですよね。
國分 そう。やっぱり大学と戦わないといけない時はあるし、その時にタテカンは重要だし、だとすると、町内会の掲示板と一緒で、普段はさほど利用されていなくても、その時のためにきちんとタテカンという社会資本を維持しておく必要があるし、タテカンを作るスキルを継承しておかないといけない。タテカンって僕も学生の時に作ったことあるから分かるけど、かなりのスキルが必要ですよ。で、スキルもタテカンそのものも完全に失われているのが、僕の出身校でもあるけど早稲田大学でしょう。数年前に必要があって行ったら、大隈重信の像が完全な姿で見えるの。もう、なんというか、情けないというか、大隈重信も泣いてるよって思った。こんなタテカンもないキャンパスに何の価値があるのか。『あばれはっちゃく』のお父さんじゃないけど、「情けなくて涙出てくらあ」という感じですよ(笑)。実際、大学の人気も落ちてる。
池田 大学としてのブランドを保つという意味でも、タテカンというのは意外と重要なんじゃないかと思いますけどね(笑)。もはや全国的に見ても明らかに希少価値があるので。
國分 まったくその通りだと思うよ。そのくらいの力量があるといいんでしょうけどね。もうひとつには、大学として放っておく領域が重要だと思います。今、何でもかんでもルールで覆わなければいけないと思われているみたいだけど、法律の世界ではすべてを覆わないといけないなんていう原則はなくて、覆わない領域というのはあるんです。ここまでは大学が管理するけど、これ以上は放っておくということ、それをはっきりさせればいい。
池田 情報環境があらゆる領域を可視化させていく中で、すべてが管理で覆い尽くされて、放っておかれるようなグレーな領域が失われていく。すべてをフラットな管理下に置いて、そこから外れたら即、自己責任というような。タテカンの問題に限らず、広くこうした状況を考える上でも中動態の概念は有効かもしれませんね。
國分 今日は責任の話はしなかったけれど、僕らが使っている責任や意志、あるいは自己責任なんていう言葉は、僕らが生きている領域を全然網羅していない。そこを考えるときに、中動態の見方というのは役に立つのではないかと思います。
池田 『中動態の世界』から始まって、『暇と退屈の倫理学』の文化や芸術と関連する側面、さらに想像力の問題まで、大変に充実したお話が伺えたかと思います。今日はどうもありがとうございました。
(2018年2月28日、五反田にて/2018年5月14日公開)

こくぶん・こういちろう
1974年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は哲学。主な著書に『中動態の世界』『暇と退屈の倫理学』『ドゥルーズの哲学原理』『来るべき民主主義』『スピノザの方法』など。訳書にガタリ『アンチ・オイディプス草稿』(共訳)、ドゥルーズ『カントの批判哲学』などがある。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。

