芸術論の新たな転回 05佐々木敦×池田剛介 モノとトートロジー
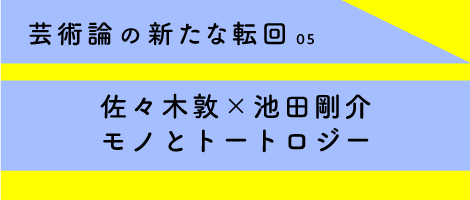
対談:佐々木敦 × 池田剛介

『アートートロジー 「芸術」の同語反復』
佐々木敦 著、2019年、フィルムアート社
池田 今日はよろしくお願いします。佐々木さんの批評活動は前々から拝見していて、音楽や映画、文学や舞台美術など数々なジャンルを横断しながら精力的に書かれていることに関心を持っていました。ちょうど僕の初めての単著『失われたモノを求めて』が出るのと非常に近いタイミングで、アートについては初となる佐々木さんの著書『アートートロジー』が発売されています。そもそも芸術についての論集が本になること自体が珍しいわけで、それがほぼ同時期に出るということで、ぜひお互いの関心をクロスさせることができればと考え、対談相手をお願いすることになりました。『アートートロジー』については、文芸誌『すばる』に本の序論となった論考がはじめに出て、その後少し経ってから本格的な連載が始まりましたよね。
佐々木 まず序論に入っているものが月刊誌『すばる』に掲載されて、それから1年くらい経って2017年から18年にかけて同誌で連載をしていたのをまとめたもので、中身はほとんど時評のようになっています。その時にたまたま見ることのできたものしか書けないし、書かない、と決めていました。ですので、結果としてこのような内容になっていますが、自分の意志とは違うところでできていった部分があります。その後に、かなり長めの補論をつけて本になりました。
池田 連載1回目で、上妻世海さんキュレーションによる「Malformed Objects」展が扱われていて、たまたま僕もその展覧会に参加していたこともあり、連載開始後も気になっていました。ともあれ序論となった2016年の問題提起が僕にとっては印象深かったですね。いきなりティエリー・ド・デューヴの議論が大きくフィーチャーされていて、アート界隈ではそんな議論はもはや忘れ去られている、というかそもそも読まれていないわけですね(笑)。僕が大学生の頃に、理論的なものに関心を持ち始めた時期に、当時やっていた読書会で取り上げた記憶があります。
ド・デューヴの議論というのは、ざっくりいうとアート自体が「アートとは何か」という問題を自己言及的に問う、ということを近代芸術の原理とする、というものです。佐々木さんの議論でもアートの内在的な問題を問い直す、という姿勢が打ち出されていますよね。このような問題提起がアートの内部からではなく、様々なジャンルを横断されてきた佐々木さんから投げられる、というところに個人的にはインパクトがありました。最近のアートの流行りである関係性の美学やソーシャル・プラクティスのように、人と人との関係性を作ったり、具体的な社会問題に介入したりといった傾向が強くなり、アートが「外」へと開かれることがデフォルトとなっていくなかで、もう一度「アートとは何か」という問いに立ち戻ってみるという姿勢は、僕の問題意識と通じていると思います。佐々木 この対談が決まるよりも前から池田さんの本については関心を持っていて、今回の機会がなくても読んでいただろうと思います。しかし、実際にこの本が届いて一読させてもらった時に、僕が『アートートロジー』で扱っていたいくつかの問題系、そのかなり核心的な部分が取り上げられていることが分かって驚きました。
『失われたモノを求めて』というタイトルは、 ともすると反動的に「ものづくり万歳!」のような話にとられかねないのですが、実際に読んでみるとそれとはかなり違っているんです。モノとコトとを対置したときに、ある時期以後のアートは世界的な趨勢として、モノよりもコト、行為や出来事のほうにウエイトが高くなっていった。そういう状況のなかで、池田さんが自らもアーティストとして活動しながら考えてこられたことが、このタイトルに集約されている。つまりアートにおけるコトの重視から、モノをいかに回復するのか、ということがこの本を書かれた動機かと思います。実際に制作しているアーティスト自身が、こういう問題意識を持ちつつ、かつ制作を続けているというのが、心強い思いがしましたね。

『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』
池田剛介 著、2019年、夕書房
池田 もちろん様々な言説的な部分を踏まえているのですが、それだけでなく、多くの実制作者が薄々気づいていながら、きちんと言語化されていないようなところまで含めて議論の俎上にあげておきたい、という気持ちがありました。
例えばいま芸術祭やアーティスト・イン・レジデンス、日本の地域アートも含め、無数のプログラムが世界各地で行われていますよね。アーティストはそうした様々な現場を渡り歩きながら、その場の状況に応じて絶えずフレキシブルに制作を展開しないといけない。「サイトスペシフィック」とも言われますが、その都度の固有の文脈に関わっていくことが求められるわけです。
一方で、現在の企業などでの労働環境を見てみると、労働者は様々な職場を渡り歩きながら、その都度の新しい人間関係や環境にフレキシブルに対応し、期間限定で働いてはまた次の職場へと移動させられる、そうした状況なわけですね。グローバル資本主義のなかで、企業には絶えず変動する需要にきめ細やかに対応することが求められ、労働者はその不安定さを受け止める調整弁のように位置づけられている。
こう考えてみると、国際的な芸術祭であれ、ローカルなものであれ、アーティストが期間限定でその現場に赴いて、絶えずその状況に固有の社会問題なり政治問題なりに向き合うことが求められるというのは、単に今の社会状況を反映しているに過ぎないのではないか、と。もっと言ってしまえばアーティストが派遣労働者になってしまっているのではないか、という状況があるわけですね。こうした制作者をとりまく具体的な状況も、「モノからコトへ」の趨勢と深く連動しているように思います。
佐々木 派遣労働者でありパートタイムジョブとしてのレジデンス・アーティスト、というのは事実としてそういう構造になっていますよね。
先ほど池田さんに言及していただいた、この本の序文となっている「アートートロジー」という文章のなかで僕が議論していることなのですが、あるジャンルが、それとして成立している状態が長くなると、そのままひとつの制度や慣習になっていく。それはなぜそうなのか、ということが問われなくなっていく。それを言ってしまうと根本的に瓦解してしまうので触れないことにしておく、とされているようなものについて、そもそもアート以外でも関心を持っていました。
そういう意味で、僕が関わってきたもののなかで一番アートに近いと思うのは、文学です。「文学は文学である」というトートロジーも、やっぱりある。あるいは少し別の形で「ロックはロックである」というのもあると思います(笑)。そうした価値判断的な意味合いが含まれている言葉はトートロジカルになりがちなんですね。そういう意味で「アートートロジー」という言葉に、僕が言いたいことは集約されています。
この「アートはアートである」というトートロジーを考えるにあたっては、先ほども出てきたティエリー・ド・デューヴの議論を参照しています。2000年代初頭に、『マルセル・デュシャン』や『芸術の名において』といった翻訳が出たのが20年近く前で、原著はさらに前なわけですが、僕としてはアートについて書こうと思って遡行的にド・デューヴの議論を発見したのではなく、ずいぶん前から頭の中であったんです。それが今、時評的なものを書いていこうとするときに、ものすごくリアルでアクチュアルなものとして露出している、アートがアートであるがゆえに生じる悪循環が、実際のアートの現場において、20年前よりももっと明確に露出している、という感覚をもったんです。ですから一方では「アートとは何か」という一種の原理論をやっているのですが、それがそのまま状況論につながってしまう構造になっています。
そこの部分は、池田さんの本とも通じるところがある気がします。この本は、前半では長い書き下ろしがあり、後半では既出のものをまとめてあって、おそらく書いていた時期が比較的近いということもあるのだと思いますが、僕が外野から考えていたことを、アートのプレイヤーの一人である池田さんが考えていた、ということを興味深く思いました。
池田 確かに僕は美術作家として多少ともアートの世界に関わっていると思いますが、書き手としては、アートの外部とまではいかないにせよ、その内と外との境界線上で考えてきた、という気持ちがあります。後半のChapter IIでは、既出の論考をまとめているのですが、それらはいわゆるアートの専門誌で書かれたものではありません。そもそも批評的な論考など載せられる媒体はほとんどないわけで、批評誌や思想誌、文芸誌などの媒体で断続的に書く機会があり、それをまとめましょうかと声をかけてもらったのが、この本ができたきっかけになっています。
佐々木 アーティストが本を出すことはあるわけですが、基本的にそうした本というのは自作の説明になるわけですよね。しかし池田さんの本が特徴的なのは、自作についてはほとんど語られておらず、かなり批評家的な立場を取られていますよね。池田 そうですね。基本的にアーティストによる「アート・エッセイ」的なものは書かないし、書けないですね。それは僕自身が、いわゆるアートワールドとは異なる批評の世界と接点を持ちながら活動していたからだと思います。僕にとってはアートの世界というのは外部性のない非常に狭い世界で、限られた有力者が価値判断の鍵を握って、その世界の空気を作っている。批評というのは言説の力によってアートも文芸も映画もサブカルチャーも同列に扱いそれらの間を横断する、そうした風穴を開けるような作用を持っている。それがないと息苦しくて仕方ないんですよね。特に日本のアートの世界には、そうした外部的な視点を導入する批評こそが欠けていて、多少ともその役割を引き受ける必要があるのかな、と思っているところがあります。
作品を閉じること
佐々木 この本の書き下ろしの構えとして「結論を出す」ということを強調されていて、そのような姿勢自体が、今のアートに対する池田さんのスタンスになっています。つまり、とにかく結論もなく「開かれる」ことが果たしていいことなのか、という問題が提起されているわけですね。
池田 問いを立てて一定の思考のプロセスを経て、そこから答えを導き出す、ということに関しては、あえて意識的に取り組んだところがあります。というのも佐々木さんが言われたように、今のアートでは、答えなんて出す必要はない、様々な人がいろんな立場で集まって終わりなき対話を行う、その対話のプロセスやそこでのコミュニケーションこそが重要なのだ、という話がデフォルトになっているわけですね。かつての絵画や彫刻のような、形態として閉じられた作品などはもう古い、むしろ人々の参加や具体的な社会問題へと開かれていくべきだ、という議論は強くなっています。
そこで僕は逆張り的に(笑)、あえて結論を出すことを本のなかで行なっています。場づくりばかりに価値が与えられてしまうと、結局のところ場を作る人と、それに参加する人との関係性は固定化されてしまうんですよね。あらゆるところで「開かれること」が言祝がれる状況において、作品という単位を閉じることの重要性について議論している本なので、文章でも結論として閉じるということを、姿勢として強く打ち出すことになりました。
佐々木 結論自体はあらかじめ考えていたものなのですか。
池田 細かく言ってしまうとネタバレになってしまうのでボカしますが(笑)、実際には複合的な結論を提示していて、ひとまずの方向性として、作品を閉じることについてはあらかじめ考えていたものだったのですが、書いていくうちに、さすがにそれだけだと反動的なものになりかねず、その先にあるもうひとつの結論へとたどり着いた感じですね。書くことによって書くことを展開していて、つまり制作することこそが制作を展開させる、という本書での議論を実践しているんです。
佐々木 ふたつの答えというのが相補的なもので、ふたつめがひとつめをある意味では裏返しているようにも見えるのだけど、そのふたつがあって初めて池田さんが主張しているものが提示される、という構成になっていますよね。
池田 『アートートロジー』のなかでも作品におけるコンセプトとアクチュアライズの関係が言われています。ここ数十年、現代美術においてはコンセプトが重要だとされてきたわけですが、それがどのように具体的な形態をもって作品化されるのか、という後者の部分に僕の議論の重きがあるのだと思います。
佐々木 コトとモノという対立項を立てた時に、「失われたモノを求めて」と書くと、本当に物質的なもの、作ってナンボだ、みたいな話に聞こえかねないわけだけれど、そういうことではなくて、むしろコト的なものがメインストリームになりつつある、というか実際にそうなっているアートの世界のなかでなお、モノを見出すにはどうしたらいいか、という問いになっていて非常に今日的な議論でしょう。
忘却されたマイクロポップ
池田 佐々木さんの本でも、ある意味で「失われた」問いを今あらためて俎上にあげる、という姿勢がありますよね。特に松井みどりさんによる「マイクロポップ」をめぐる議論については虚を突かれる思いでした。僕の本のなかでも松井さんの文章を引用したりしているので、まったく忘れていたわけではないのですが、しかし2007年の「マイクロポップ」展については、ほとんど意識していなかったですし、本のなかでも指摘されているように、アートの世界ではほとんど忘却されている感じがします。
佐々木 本当に忘れられているんですね!(笑)
池田 そう思います。そこに改めて注目するというのは面白いですよね。「マイクロポップ」は主に90年代の日本のアートの動向を扱っているわけです。ざっくりいうと、ニコラ・ブリオーの「関係性の美学」も90年代のアートのひとつの傾向をフレームアップしていて、冷戦崩壊以降に世界のグローバル化が始まり、かつインターネットも登場し始めた時期で、水平的につながっていくということに希望があった時代と並行しているのだと思います。
それに対してソーシャリー・エンゲージド・アートというのは、その後2001年の9.11以降にグローバリズムが世界を一元化していくなかで、いわば内部的な戦争状態が露呈していく状況におおよそ対応している。つまりネットワーク的につがなればよい、などというのは幻想にすぎず、この世界の内部にあるシリアスな社会問題や敵対構造を直視すべきだ、という感じになっていくわけです。佐々木さんの議論は、こうした傾向のどちらにも回収されないようなものをマイクロポップのなかに見出したい、ということなのでしょうか。
佐々木 僕の本のなかで、なぜマイクロポップの話が出てきたかというと、これは端的に田中功起と泉太郎の展覧会があったからですね。二人の作品は前から関心を持って見てきていたんです。つまり「マイクロポップ」展に参加していたアーティストが、今どうなっているのか、という関心が入り口にあります。この展覧会は2007年に開催されたわけですが、先ほど言われたように、その前にニコラ・ブリオーが90年代のアートに対して「関係性の美学」と言ったわけですよね。それとマイクロポップのやっていることには似ている部分があるんじゃないかということを書いています。
しかしマイクロポップがなぜ忘れられたのかといえば、池田さんが言われたように、欧米でのアートの分節点が2001年の9.11だったとすると、日本においては2011年の3.11になるわけですよね。あのような出来事があって、それ以後にアーティストたちが自分には何ができるのか、ということを問い始めた状況がある。この本のなかでは、むしろマイクロポップは実は政治的だった、ということを言おうとしていて、明らかに松井さんは一種の抵抗の形式として考えていたわけですね。しかしどちらかというと日常を肯定する、という議論として受容され、3.11以降そんな日常が崩壊する状況のなかで忘れられていったのかなと思います。
このようなマイクロポップから3.11以後への転換を、身をもって体現しているのは田中功起だと思うのです。上妻世海は「田中功起は変わっていない」という主張をしていて、それはそれで彼なりの筋の通し方だとは思いますが、3.11から8年が経って、池田さんが書かれているモノからコトへという動向、僕がよく使う言い方ではコミットメントとコミュニケーションが主体になっている動向が強くなっていく。しかし僕は、マイクロポップが持っていたかもしれない可能性が、ポジティブなものも含めて一緒に忘却されたんじゃないかという気持ちがあって、だからこそ蒸し返したかったんですね。
池田 そこは改めて考えさせられた部分です。僕自身も、一応リアルタイムで見ていて、しかしあの「ささやかな私の内的世界」という感じに全然乗れなかったんですね。まさにそうした日本の終わりなき日常が3.11によってすべて押し流されてしまった、という感じがあるのだと思います。そうした分断された日常から、また共同体の紐帯を作り出していったり、より社会的な問題にフォーカスしたり、といった傾向が強まっていく。
佐々木 「もうそういうこと言ってる場合じゃないでしょ」という空気になったのだと思います。でもそこには実は問うべきものが残っていたのではないか、という気持ちがあるんです。
池田 今言ったように、自分の小さな箱庭的世界に包まれるようなマイクロポップ的な傾向にまったく乗れなかったのですが、佐々木さんの議論を通じて改めて気づかされたのは、意外と僕が本のなかで考えていることと近い部分もあるんじゃないか、ということなんですよね。というのも僕も、ある仕方で社会的なものに対して作品という単位を閉じること、封鎖することを強調しているからです。
松井さんに関してはマイクロポップよりも、その前の『”芸術”が終わった後の”アート”』のほうが重要かと思っていて、そこでは90年代のブリオーやハンス・ウルリッヒ・オブリストらによる関係志向の動向にもある程度の共感を示しています。しかし松井さん自身は、それらのユートピア的な空気を踏まえながらも、さらに日本独自の仕方で閉じること、というか否応無く閉じられてしまうことを肯定的に描き出そうとしていたと言えるのかもしれないですね。
佐々木 もしかしたらリアルタイムのマイクロポップは、箱庭的だという意味において批判されても仕方がなかったのかもしれません。このマイクロポップに対する批判、つまり日常性や箱庭的なものへの批判というのは小説でも見られると思うんです。例えば保坂和志さんや柴崎友香さんの小説は、何も起きない日常を肯定しているだけ、というふうに言われます。しかし保坂さんも柴崎さんも、小説のなかで何も起きないと言われることに抵抗しています。そのなかには様々なことが起こっているのだ、と。つまりそれは、何か劇的なことが起こるわけではないけれど、もっとミクロな観点で見てみると、いろんなことが起こっているのだ、というわけです。「何も起きない日常なんてないんだ」というのは小説のなかで柴崎さんも書いているところで、そうしたものとマイクロポップはつながる気がするんです。
池田 それはわかります。しかし同時にやはり、日本のドメスティックな風土を単に自己肯定しているだけとも見えかねないわけで、そこをどう考えるべきなのか、というのはありますよね。先ほど、僕の議論とも近い部分があるんじゃないかとも言ったのですが、しかし違いを言っておくなら、松井さんの議論には、「繊細で弱々しい私」というのを過剰に強調するところがあって、そこはやはり乗れないな、という気がするんです。今ネットをみれば、「私がいかに傷ついているか」、「いかに傷ついている人に共感しうるか」をめぐる闘争のようになっているわけでしょう。

左:佐々木敦、右:池田剛介
PC的なものをめぐって
池田 それこそ佐々木さんの本でも扱われている映画『ザ・スクエア』でも、PC(ポリティカル・コレクトネス)やマイノリティへの共感といった問題が、かなりアイロニカルに描かれています。現代アート業界を舞台にした映画なのですが、美術館のなかに正方形を描き、そのなかではすべての人が他者に対して寛容と思いやりをもつ、というような、いわば関係性の美学を戯画化したような作品が登場します。
この作品のプロモーションをする際に宣伝マンは、そんな偽善的な話をしても誰にも関心をもってもらえない、ネットで人々の興味を引くためにはインパクトが必要で、そのための最も強力なコンテンツが「弱者」である、というわけです。つまりここで、人々の情動を呼び込む弱者性と資本主義の論理が、とりわけネットによってまっすぐに結びついてしまう、ということがアイロニカルに示されているわけですよね。この映画に対してアート界隈の人々が拒否反応を示したように思うのですが、しかしそれはPC的なものに対して素朴すぎるのではないかと。
佐々木 そうですね。被差別的なものに寄り添う、寄り添い系アートってありますよね。もちろん寄り添うことは必要なんだけれど、行為としては正しくても、そのこと自体が自動化して、自動化するのみならずそのこと自体がある種の権威のようになってしまい、それに対する批判的な視座が成立しなくなってしまう、ということはあるんですよね。
弱さ、あるいはヴァルネラブルな(傷つきうる)ものが、ある種の聖痕のようになっていて、世界の芸術祭やアートワールドにおける流行も、広い意味でのPC的なものがあり、そこを押さえてないとどうにもならない、という状況があるのだと思います。池田さんの本で書かれているドクメンタの傾向も、完全にそうですよね。あるいは小崎哲哉さんの『現代アートとは何か』を読んでも、PC的なものがアートワールドを覆い尽くしており、しかもそれが資本主義とそのまま繋がっているという状況は、かなり飽和しつつあるような気がします。その時に、アメリカでトランプが現れたような反動的なモメントが、いつ大きなかたちで現れてもおかしくないんじゃないかと思うんです。
池田 僕の本のなかでは、もともと『POSSE』という社会問題を扱う雑誌に掲載された、2017年のドクメンタを扱った論考があります。佐々木さんが言われたようなPC的な傾向というのは、まったくその通りなのですが、少し補足するとドクメンタは、きわめてドイツ的というべきでしょうけれど、戦後にナチスドイツによって弾圧された抽象絵画をはじめとする前衛芸術にフォーカスするところからスタートしているわけで、成立当初からきわめて政治的なスタンスを打ち出しているわけですね。
佐々木 もともとそういう傾向だったけれど、最近はさらに強まっていますよね。
池田 そう思います。そこの部分は、植民地主義を背景として盛んになっていく万博をモデルにしたヴェネツィア・ビエンナーレと明確に異なる点でしょう。日本を含め、各地での芸術祭というのは、おおよそヴェネツィア・ビエンナーレのような多幸的なお祭り、今で言えばツーリズムと結びついたインスタ映え路線なわけで、とにかく最近の芸術祭というのは、どこもかしこも多様性ということばかりを掲げて、多元性というテーマで完全に一元化されている感じなのですが(笑)、少なくともそうしたレインボーカラーで現実の問題を塗りつぶしていくような傾向とは異なる路線を打ち出しているわけです。
先ほど佐々木さんがPC的なものに対する反動の可能性を言われましたが、まさにドイツはEUの中でも国家として多くの移民を受け入れるスタンスを示していて、ナチスへの反省的な姿勢も含めてリベラルな風土が強いところですよね。で当然そこからの反動もやはり強く出ていて、ネオナチの台頭や移民との分断というのはシリアスな問題なわけです。そうしたなかで社会や歴史の問題を背景とした沈鬱なトーンを打ち出しているというのは、一定の必然性があるとも思うんです。
けれども本当にそれでいいのかな、という気がする。とにかく多様にシリアスな問題がパッケージ化して並べられているようにも感じられてしまうわけです。総じて言えば世の中にはいろんなシリアスな問題がありますね、という印象しか残さないし、そうした疲れのなかから、さらなる反動が生み出される可能性は否めないと思うんです。
佐々木 モヤモヤしますよね。そのこと自体は非常に正しいわけです。例えばニコラ・ブリオーの議論に対してクレア・ビショップが批判する。その時に、ブリオーが関係性の美学において一番推していたアーティストのひとりはリクリット・ティラヴァーニャですよね。そのティラヴァーニャに対してビショップはトーマス・ヒルシュホーンを立てる。でもヒルシュホーンは今やあらゆる芸術祭に呼ばれてプロジェクトを展開する超人気アーティストで、作品も高額で取引されているはずです。そうした身もふたもないようなパラドックスがありますよね。まさにアートートロジーが機能しているからこそ、こうしたことが可能になっている。
池田 マーケット的な問題もそうですよね。ともかく一方でポスト・トゥルースと呼ばれる排外主義的な状況があり、それに対してカウンター的に現実主義的な態度を打ち出していくということになると、ほとんど同じ事態の表と裏、というようになりかねない。僕自身は、歴史的事実を扱って具体的に社会問題に介入すべきだというような現実主義とは異なる方向を探った方がいいのではないかと思っています。
作者と作品の解体
佐々木 先ほど言われた作者や作品の解体というのも、これに関わってきますよね。80年代くらいまでのポストモダンな論議では、アートに限らず近い話はあったわけです。それまでは作品や作者というものが非常に強固にあって、それに対するカウンターパートとして作者の解体が言われた。それから30-40年経った今では、本当に解体してしまっている(笑)。だからこそ、作者とは何か、作品とは何かということをもう一度問い直す、池田さんの問題提起は重要だと思います。
池田 アートって、そういうポストモダンな作者の神話性や特権性の解体を、ものすごく素朴にやれてしまう、ということがあるんですよね。哲学者がモダンな構築性を批判するからと言って、書くことをやめて哲学カフェだけやる、ということになっても困るわけで(笑)。しかしアートでは、ベタにそれがやれてしまうところがある。他のジャンルはどうなのでしょうか。映画で「ここまでは作りましたが、あとはワーク・イン・プログレスということで、よろしく」とか、さすがに通用しないと思うのですけど(笑)。
佐々木 いやいや、リアルにそうなりつつあると思いますよ。かつては作者によって強権的に作品が閉じられる部分が強かったので、それを開いていくことに様々な可能性があったと思う。それが今や、開くということ自体が常套手段になっていて、ここでもう一度、どう閉じるか、というのはかなり難しいんじゃないかと思うんです。
舞台芸術の世界でも、近年はこうした傾向が非常に強くなっていて、観客参加であるとかワークショップ形式とか、アウトリーチ的な作品もすごく増えていて、ポストドラマ演劇などと呼ばれる潮流のなかでも特に社会的なコミットメントの要素が前面化していると思います。これにはいわゆる「地域アート」や芸術祭バブル、助成金問題などが作用しているわけですが。本のなかでも書きましたが、とりわけ「3.11」以後、広義の芸術に明示的な有用性を求めるバイアスが生じていて、アーティスト自身もそのことにとらわれざるを得ないようになっている。
ソーシャリー・エンゲージド・アートなんかは、ほとんどアクティヴィズムと区別できないようになってきて、アートと言うのすら良くないのでソーシャル・プラクティスと言うようになって、社会活動のようになっていくわけですね。
池田 そうした社会派アートについて書いているパブロ・エルゲラなどは、シンボリックな実践とアクチュアルな実践とを明確に区別しています。つまり、かつての歴史画であれ社会主義絵画であれ、社会-政治的なものを主題にした芸術というのはあったわけですよね。しかしそれらは単に、そうしたテーマを表象レベルで扱っているにすぎないと。そうではなく、もっと実際に社会的に効果をもつしかたで介入するものこそがソーシャリー・エンゲージド・アートである、とするわけです。しかし後者のように、実際に社会のなかに具体的に介入していくことを至上命題として掲げるなら、佐々木さんが言われたようにアクティヴィズムと限りなく識別不可能になっていくわけですよね。
例えばスーザン・ソンタグは、アクティヴィズムというのは具体的な実効性に関わるものであり、それに対して文学はこの世界の複雑さをそのまま描き出すものだ、と言ったりしています(ソンタグ自身が、アクティビスト的な性格を持っていたことは、確認しておくべきでしょうけれど)。エルゲラの言うように、社会のなかで具体的な効果を引き起こしたいのであれば、単にアクティヴィズムとしてやるべきではないかと思うし、アクティヴィズムはそれ自体として価値があるわけで、アートなどという必要もないでしょう。
アクション(活動)とワーク(仕事)
池田 僕の本のなかでは、こうした問題をハンナ・アーレントの『人間の条件』で出てくる、人間の行為の三区分を用いて位置づけています。
佐々木 レイバー(労働)とアクション(活動)とワーク(仕事)の三区分ですね。
池田 そう、それ自体は有名な区分ではあるのですが、僕の議論のポイントは、その区分のなかで、これまでそれ自体としては注目されてこなかった〈仕事〉(ワーク)概念に光を当てる、というところにあります。
ざっくり言うと、一方で公的な場に出て行って人と人との関係を結びなから、公共的な価値をめぐって言論活動を行う〈活動〉(アクション)があり、他方では自分自身が生きることの必要性に基づきながら日々の食い扶持を稼ぐために行われる〈労働〉(レイバー)がある、と。前者は公的、後者が私的という意味で対極に位置づけられるわけですが、どちらもそこでの成果が具体物としての形を残さない、という点において共通しています。つまり、〈活動〉(アクション)の典型としての政治行動は、人々の前で言論的なパフォーマンスを行なっているときにのみ成立しており、後者の〈労働〉(レイバー)による生産物は、食べ物などに典型的なように生み出された側から消費されてしまう。そしてこの〈活動〉と〈労働〉との中間というか、どちらとも区別されている仕事=制作(ワーク)とは何か。ワークとは耐久性のあるモノ(things)を形づくる営為であり、職人やアーティストの仕事がその典型例であると。
佐々木 ワークには、そのまま「作品」の意味もある。
池田 そうですね。アーレントによるこの区別、とりわけ〈活動〉(アクション)と〈制作〉(ワーク)の違いに注目してみよう、と。この区別が使えるかなと思うのは、これまで話していたような関係性の美学やソーシャル・プラクティスのような、作品として形を留めることを重視せず、むしろ人と人とを結びつけることや社会のなかでの効果を重視する傾向というのを端的に〈活動〉として位置づけて、耐久性を持ったモノ=作品を実現する〈制作〉と区別することができる点です。
佐々木 しかし同時に〈活動〉の価値は認めながら、ですよね。
池田 その通りです。むしろアーレント自身は明確に、公的なアクションの方に高い価値を置いているわけです。大衆社会の到来によって、人間の行為のすべてが私的な利益に基づく労働(レイバー)となり、そうした労働と表裏一体をなす仕方で消費や娯楽が台頭してくる、というのがアーレントの見立てであり、そこでは耐久性あるモノを作り出すワークも、公的な価値に資するアクションも失われてしまう、と。
これを踏まえて言うなら、確かにアートはこうした状況のなかで、ある種の公的な価値を担う〈活動〉的なものを取り戻すための行為となっているのかもしれず、その意義については言を俟たない。しかし同時に、そうした〈活動〉型アートの隆盛は、そもそもアーレントが制作者のなかに見出していた、有限な輪郭を持ってモノ=作品を形作る〈仕事/制作〉の忘却にも繋がっているのではないか、とも思うんです。
佐々木 社会的なアートというのを論理的に展開すると、投票するのも政党を作るのも起業するのもアート活動なんです、というのは言えてしまうんですよね。こないだまで東京でTPAMという舞台芸術のフェスティバルをやっていたのですが、マレーシアのアーティストが作品を出品していて、その人は舞台芸術の人でありながら本当に政党の一員として立候補して、本当に国会議員になったんです。その人にとっては自分自身のアートとしての活動と政治活動というのは、完全に一致しているわけです。今、コミュニケーションやアウトリーチのような、コト的な活動が強まっているのは、そういうことをやるほうが、普通に作品を作るよりも、いろんな意味でコンディションがいいわけですよね。
池田 助成金が取れるとか(笑)。
佐々木 でも、それだったらバンクシーを探してればいいということにもなる。バンクシーはバンクシーで重要だけれども、そういう状況の中でワークには何が残るのか、ということが、まさにいま問題になっていると思います。

マルセル・デュシャンと赤瀬川原平
佐々木 池田さんの本のなかで面白いなと思ったのは、こうした議論を展開していくなかで赤瀬川原平が出てくる、というところです。赤瀬川については既出の論考のなかでも、書き下ろしの中でも非常に重要な位置づけを与えられていますよね。
池田 赤瀬川は本のなかでも重要な位置づけになっています。ひとつには、赤瀬川が現在のソーシャル・プラクティス的な傾向の先駆けのように見なされるところがあり、それに抵抗したいという意図があります。例えば先ほどの松井みどりさんなんかも、ハイレッド・センターによる銀座での「首都圏清掃整理促進運動」を日本での社会介入型アートの先駆のように扱っています。それはそれで分かるのですが、僕としてはグループとして行なっていた活動(そもそもハイレッド・センターはグループとしての活動は一年程度で終わっている)よりも、それと並行して進めていた赤瀬川個人での作家活動に注目したい、というところがあります。そこには、いわゆる社会に開かれていくアートとは異なるものを見いだすことができるのではないか、と。
佐々木 さっきのアクションとワークとの違いということで言えば、実際にはそれほどはっきり分けられないものも多くあるわけですよね。池田さんの本のなかでも、デュシャンと赤瀬川を比較されたりもしています。例えば、赤瀬川さんが千円札を複製して裁判沙汰になって、というような話は振り返ってそれを捉えると、そういう問題を引き起こすことを狙ってやったかのように見えるじゃないですか。
池田 問題提起型アートみたいな(笑)。
佐々木 そう、抵抗の美学のような。そして事実として抵抗の美学として機能した部分もあると思いますが、でも最初はそうじゃないと思うんですよね。多分最初は、単に複製したかったんじゃないかと。トマソンなんかもそうですよね。街に出て行ってなんのためにあるのか分からないものを見つけてきて、それをトマソンと名づけるわけですよね。そのことと、デュシャンが便器を持ってきて署名して出品したというのが似ているけど少し違うと思うんです。何が違うかというと、ある意味で赤瀬川さんには美学がある。そこには一種のフェティシズムがあると思うんです。
赤瀬川さんは、なんでもいいから無意味なものを持ってきて、アートというコンテクストの上に置いた時に機能する、その機能のありさまがアートなんだ、という風には考えていないんじゃないか。そうじゃなくて、トマソンにしても単純にグッときているんだと思うんです。それに対してデュシャンは、便器に対するフェティシズムはない。そう考えるとデュシャンよりも赤瀬川の方が、既存の意味ではアーティストっぽかった、と言える気もするんです。
池田 重要なポイントですね。確かにデュシャンは作品の無関心性を強調しつつ美学的な趣味性を批判したりしています。その意味でかなり戦略的に、既存のアートにおける趣味性に対してカウンターを食わせる、という明確な意図があったのだと思います。赤瀬川にフェティシズムがあるという点については賛成で、ある意味では僕はそこにこそ関心を持つんです。つまりデュシャン的なコンセプトやアートのコンテクストに対する戦略性でやっているのではなく、そこからはみ出る部分がある。
例えばデュシャンのレディメイドと赤瀬川のトマソンは、選ぶことや見立てることを成立原理にしているという意味で通じていると思います。もっと言えばトマソンの場合はアーティストによる署名すら必要とせずに、読者からの投稿を通じて誰でも選ぶことができるわけなので、より徹底しているとも言える。けれども同時に赤瀬川は、トマソンのなかにある厳密な論理やルールを自己批判していて、その後の路上観察や、僕が特に注目している『正体不明』などでは、さらに趣味的とも言える方に向かっていると思います。
佐々木 そっちの方が大きいですよね。カメラへの偏愛もそうでしょう。骨董的な感覚に近いものがあると思う。
僕の本の序論で掲げた「芸術でないような作品をつくることができようか」というデュシャンの言葉があるのですが、デュシャンが《泉》を出品しようとして拒否されて、それに対して抗議文を出しますよね。そこでデュシャンは、確かにR.マット氏は便器を作っていないかもしれないが、しかし彼はそれを選んだのだ、と言っているわけです。つまり選んだという意味では、デュシャンが《泉》でやったこととトマソンでやったこととは似ているわけです。
これは補論のなかで書いたことですが、デュシャンがやったことは、ジョン・ケージのチャンス・オペレーションなどに近いと思います。つまりなんでもよかったわけです。目の前にたまたまあったから、それを選んだと。でもこれが選ばれたことは決定的なんだ、ということだと思う。それに対して赤瀬川の場合には、目利き的な部分が入っていて、その違いは大きい。デュシャンの場合は、アートでなくなるにはどうしたらいいか、あるいはアートでないものがアートのなかで生成できるのかという、一種のゲーデル問題のようなことを問うているのに対して、少なくとも赤瀬川は彼なりの芸術を拡張するために活動をしていた。デュシャンのようにアートの外部へと向かう線と、赤瀬川のように超芸術へと向かうそれとのふたつの線があるとすれば、どちらにも可能性はあると思うんです。
池田 それで言えば、僕は明確に赤瀬川の方にシンパシーがあると思います。デュシャンの言葉で言われたけれども、そうした「芸術でないもの」が芸術として再領土化されていく、という循環的なゲームから距離を置くことを、赤瀬川はその後の展開で模索していたのではないかと。つまり、トマソンまでは「超」が付くしかたであるにせよ、芸術との緊張関係があったわけですが、それ以後は徐々に赤瀬川自身が芸術との関係から離反していくところがある。それはいわゆるトートロジカルな自己批判性からは離脱するものだと思うし、デュシャン以降の現代アート的なクライテリアから逸脱してしまうものでもあるのですが、赤瀬川なりにアートのトートロジーから抜け出す通路を見出そうとしていたのではないかと僕は考えてみたい。佐々木さんは、より徹底してトートロジカルな構造に対して意識的なデュシャンを重視するという感じでしょうか。
佐々木 重視するというか、偶然性であれ無趣味性であれ、なぜそれがアートとなるのかと言えば、それがマルセル・デュシャンという署名と関係しています。その署名があることで、結局それはアートに回収されるわけで、そうじゃないものをどうすれば見出すことができるのか、ということに興味があるのだと思います。
池田 ここは佐々木さんと考えが異なるところかもしれませんが、僕からすると今のアート、特に20世紀後半以降の現代アートは、意識的にであれ無意識的にであれデュシャンの呪縛に縛られすぎていると思っていて、実制作者としては、それとは別の道を見出す必要があるんじゃないかと考えているんです。
そうした論点の違いは、デュシャンに注目するポイントにも見出せるかもしれません。佐々木さんはあくまでも《泉》を中心とするレディメイドに重きを置いていますよね。もちろんレディメイドが重要なのは当然ですが、僕はレディメイド以降、特に1923年に《大ガラス》の制作を「決定的に未決定(definitely unfinished)」なまま放棄した以後の、制作をやめてチェスに専心したとされる時期に注目すべきではないかと考えています。
この時期デュシャンは確かに、一貫したスタイルを貫くような、いわゆるアーティスト然とした活動からは離脱していますが、同時にデザインや職人的な仕事などはかなり手がけているんですね。特にこの時期から、メモ書きの断片を集めたボックスや非常に凝った造本によるチェスの理論書、錯視的効果を生み出す装置やこれまでの自分の作品をコンパクトにまとめた《トランクの中の箱》などを手がけています。この時期はいわば《大ガラス》と《遺作》の間の端境期で、制作放棄していた時期と見なされてきたわけですが、実際にデュシャンが手がけていたこれらの作品には、デュシャンの趣味的な側面を見出すこともできるのではないかと。そこに断片的な要素たちを束ねあげることのないままに閉じ込める「箱」というモチーフが現れていることも、示唆的ではないかと思います。
確かにこれらはレディメイドがそうであるような、アートという概念を大きく揺さぶるようなものではないかもしれず、ゆえに大きく注目されることはなかったのですが、むしろそちら側にデュシャンの新たな可能性も見出せるのではないかと思うし、そうしたデュシャンの別の側面を赤瀬川と通底させることも可能ではないかと思います。
理論と実践
佐々木 僕は批評家として人がやったことについて語りながら「アートはどうなっていくんでしょうか」とか言っていればいいのだけれど(笑)、池田さんはプレイヤーなわけで、この本のなかで考えられていることを実践に移していく局面があるわけですよね。つまり池田さんによるワークと関係しているし、これから関係していくことにもなる。京都で新しく作られたスペース「浄土複合」なども含め、この先のことをお話しいただければと。
池田 京都の哲学の道や銀閣寺からもほど近い浄土寺というエリアに、他のメンバーと一緒に、シェアスタジオとギャラリー、そしてスクールを合わせたアートスペース「浄土複合」を立ち上げることになりました。それこそ佐々木さんのレーベルHEADZからもCDを出している空間現代の「外」というライブハウスがあったり、ユニークなラインナップの本屋さん「ホホホ座」などがあったりするすぐ近くという面白いロケーションです
これは今回の僕の本の議論とも綿密に関連していて、本のなかでの議論を社会のなかで実装させたようなものになっていると思います。この本のなかではいろんなことを原理的に考えながら、今いかに制作することは可能かを探っているわけですが、とはいえどうやって特に美大の卒業後に制作を続けられるのか、という非常にプラクティカルな問題はあるわけですよね。
佐々木 それで今度は実践だ、と(笑)。
池田 それがいいのかどうか分かりませんが、ともかく機会があったのでやってみようと。もう十年近く使われていない、ほとんど廃墟状態の二棟並びの物件を借り受け、自分たちでリノベーションをやって、いちおう人を呼べる状態になったと思います。
佐々木 制作をやって発表が行われて、さらにそこが学びの場にもなる、ということですね。
池田 しかし、最近の流行りみたいにコレクティブとして一体化してしまうのは避けたいと思ったんですね。僕はそもそも集合体とか共同体とか全然好きじゃなくて、基本的に個別的なスタンドアローン状態をベースに考えるべきだと思っています。ギャラリーにしても、FINCH ARTSという独立したギャラリーに入ってもらったり、スタジオのアーティストにしても、特に僕が声をかけて集めたりしたわけでもなく、たまたまのタイミングで使ってもらっている部分が強いので、僕はたいした方向づけをやっていません。
僕としてはコミュニケーション的に交流するのではなく、クロスロードのように交差する、という感じです。個別の人たちがそれぞれの関心を発展させながら並立していることによって、互いに触発が起こったり起こらなかったりする、そうした環境になれば良いのではないかと思います。
佐々木 ではそろそろ質問タイムにしましょうか。ご来場の皆様いかがでしょうか。
質問者 ふたつ質問があります。池田さんの本のなかで「アマチュアになること」というキーワードが出てきますよね。ここでアーティストによる「アマチュアになること」と同様に、それぞれの職能についているアーティストではない人々による「アマチュアになること」とが、ある程度、等価に語られていると思います。それはソーシャル・プラクティス的なものにおけるひとつの理想形かもしれませんが、これが本当に等価になりうるのか、ということをお聞きしたいと思います。もうひとつは、そういう活動をした時に、モノにするなり、写真や映像にするなり、それをなんらかの形で残さないといけないですよね。この点についてどう考えられますか。
池田 まずふたつめのご質問から答えると、例えば僕は、2014年の台湾での学生運動から着想を得た「占拠」についてのプロジェクトを行っています。アートセンターや美大で、そのへんに置いてある様々なモノたちを使いながら部分的な封鎖空間を作るというもので、参加者や学生と一緒に行っています。
先ほどのアクションとワークの区分でいえば、完全に前者の側にあたるもので、もちろんそこで起こったことを多少は文章にしたりもしますが、そもそも作品として残るものだとは思っていません。ある種のエクササイズのようなものだし、それでいいと思っているんです。多くのソーシャル・プラクティス的なものはそこが中途半端で、めちゃめちゃ長い映像にしたりして芸術祭なんかで流したりしますよね。でもそんな記録はほとんど作品としては見るに堪えないものだと思う。
あえて何が残るかといえば、モノたちのなかに潜在的な可能性が残るのではないかと。モノたちが一時的に集められて、新たなアレンジメントが与えられながら封鎖空間を形作る。そうしたモノたちの連帯が一時的に形成されて、また再び元の場所へと帰っていく。しかし元の場所に戻ったモノたちは、別様であり得るという潜在性を帯びているとも言えるのではないかと。だからきちんと元の場所に戻す、ということがこのプロジェクトでは大事なんです。
そこからひとつめのご質問の、「アマチュアになること」というのは、アーティストと、他の人ではやはり異なるのではないか、という点について。これは非常に難しいところですね。僕の本のなかでは、アーティストは孤独に狭い関心に閉じこもるがゆえにこそ、外部からの鋭い触発を通じて新たな関心へと開かれ得る、そうした「アマチュアになること」のモデルを示すことができる、と議論しています。
けれども他方で、アーティストや美大生にかぎらず、あらゆる人が日々を、何らかの職能をもって生きているわけで、一般人など存在しないし、そうあるべきでもないと思います(現在の労働環境が、そうした「一般人」化を強いる傾向についても本のなかで触れています)。しかし僕たちには一時的にであれ、そうした職能を離脱する局面があるんじゃないか。それが例えばデモや占拠のような場に見られるんじゃないか、ということを台湾での経験を踏まえながら議論しています。それぞれに与えられた職能や役割を離脱するようにして、ワーク「のようなもの」が開始される局面があるのではないかと。ワークショップで一緒に作りましょう、みたいなものとは別の仕方で、しかし作ること、制作することを、アーティストや美大生に限らず広い可能性として提示したい、という気持ちがあったわけです。
佐々木 「アマチュアであること」と「アマチュアになること」の違いを強調されていますよね。僕は「アマチュアになること」の良さはあると思っていて、それを裏返すとプロフェッショナルになりきらないことだと思うんです。僕らはどうしても専門家になっていくわけじゃないですか。そのようなものとして社会から見られもする。そうしたプロフェッショナルになりきらないということが、アマチュアという言葉がもっている可能性で、それはアートでなくてもジャンルを超えてあらゆるものに適応できるものだと思います。僕もずっと自分はアマチュアだと思ってきたんですよ。
池田 佐々木さんは様々なジャンルを跨ぎながら執筆を続けてこられたわけで、全くのリスペクトを込めていうと「アマチュアになること」を体現している存在だと思います。実作者と批評家の違いを言われましたが、批評家も文章という作品を形にしているわけなので、やはり制作者に他ならないと考えています。
質問者 池田さんは京都に浄土複合を立ち上げて、佐々木さんも三鷹でScoolという場所を運営されています。こうしたアートや文化の場を作るということについてはどのように考えられていますか。
佐々木 特に東京の場合は、何かをやりたいと思った時に、どこかでやらないといけないわけで、そのどこかという選択肢が少ない上に、放っておくとどんどん数が減ってしまう、という感じがしています。だから自分が何かをやりたいと思った時に、他の場所でやるよりも相対的にリスクが低くやれるということ、あと容れ物を作ったら、それに人が何か入れに来るよね、という感覚が強いんです。つまり全部自分のやりたいことをやる、ということではなくて、あれば使いたいという人が出てきたり、潜在的にいろんなことが起きたり生まれてきたりする可能性はあっても、それを実現するためにはかなりいろんな条件があるわけですよね。例えば池田さんが言われていたように、アートに関する一定のボリュームの批評文を発表する場所がないから他の媒体などで書くしかないわけです。裏返すと入れ物があれば、例えば文章でもそれを載せられる媒体があれば、書ける人も書きたい人もいるかもしれない。しかし載せる媒体がないために、書くことができないということをなんとかしたいと僕は思うんですよね。だから浄土複合やScoolのような具体的な空間も、あるいは媒体を作ったり、あるいはいろんなところでトークに出たり、こういうのはある時期から始めたことなんです。それは、こういう広い意味での場を作ることがもっている可能性はやっぱりあると思うんです。
池田 浄土複合の場合は、京都ならではと言うべきか、ライブハウスや本屋、劇場など、それぞれにユニークでハードコアな場所が近くにあって、そういう環境は東京ではなかなか成立しないですよね。アートに限らずそういう他ジャンルとの連携はやっていければと思います。さっきも少し言いましたが、そもそも批評に関心をもったのも、批評にはジャンルを超えて異なるものを結びつける力があると感じたからなんですよ。ぜひこれから佐々木さんのお力も借りつつ様々な横断的実験をできればと考えています。今日はありがとうございました。(2019年3月10日、東京の青山ブックセンター本店にて/2019年5月14日公開)
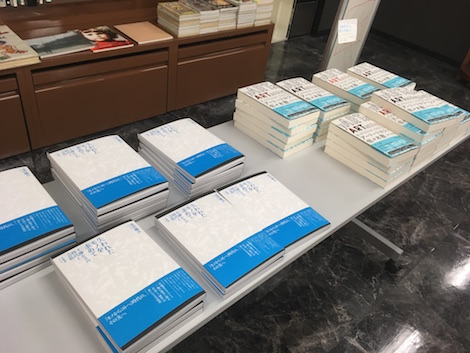
ささき・あつし
1964年生まれ。批評家。HEADZ主宰。文学、音楽、演劇、映画、美術など、芸術文化を貫通する批評活動を行う。著書に『ゴダール・レッスン』『ゴダール原論』『批評時空間』『新しい小説のために』『あなたは今、この文章を読んでいる。』『ニッポンの思想』『ニッポンの音楽』『ニッポンの文学』『筒井康隆入門』『未知との遭遇(完全版)』『シチュエーションズ』『ex-music(L/R)』『「4分33秒」論』『テクノイズ・マテリアリズム』『(H)EAR』『即興の解体/懐胎』『文学拡張マニュアル』など多数。2019年2月に『アートートロジー 「芸術」の同語反復』(フィルムアート社)を刊行した。
いけだ・こうすけ
1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。2019年2月に初の単著『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』(夕書房)を上梓した。

