高谷史郎『Topograph/ frost frame Europe 1987』展評
明るい部屋の外へ(高谷史郎『Topograph/ frost frame Europe 1987』)
清水 穣
ギャラリー2階の会場に上がると、正面には「Topograph / La chambre claire」、その対面に新作の「Toposcan」、左右に「frost frame Europe 1987」が展示され、つまり、正対の壁はスキャニング、左右の壁は写真という配分で、そのあいだに「mirror type k2」が置かれていた。展覧会は「写真」と「スキャン」の対比、すなわち、アナログ写真がそのモデルとなるような視覚と、最新のデジタル技術が開拓しつつある未来の視覚の対比を軸に構成されているのである。人間の眼が、つねにある時代のテクノロジーに規定されるものだとすれば、本展は、写真に深く影響されて「見る」ことの時代がいよいよ過去となり、デジタルスキャンという方式で「見る」時代が到来したことを承認しつつ、その未知の視覚がもたらす奇妙さと美しさに対峙する、数少ない試みである。





端的に言って写真的な視覚とは、1)「像」による視覚であり、対象との距離を前提とする(レンズに密着しては像ができない)。2)その基本単位は面(レイヤー)。3)誰でもない者の視点からの像であり、見る人の肉眼がその視点に代入される。4)「誰でもない者」が「見た」像を、「ある誰か」が「見る」という重合から、現実と意識は分裂し二重化する。「見る」とは現在の中の過去、現在の中の潜在、自己の中の他者を見ることである。
「frost frame Europe 1987」は、遠近法構図を強調して撮影した「かつて」のヨーロッパの光景を、正方形のフレーム(=標本箱)に容れ、さらに(大型カメラのピントグラスを連想させる)フロストアクリルの彼方へ遠ざけた作品群である。写真的視覚(上記1と2)を、美しい棺に納めて、ノスタルジックな過去へと遠ざける。

「写真」から「スキャン」への橋渡し的な位置を占める「mirror type k2」は、写真的視覚(上記3と4;時差と二重化)を修正する、シンプルでユーモラスな装置。写真に(「写った」ではなく)写る自分の顔をライヴで見る鏡である。他人には珍しくもない、本人にとってのみ衝撃的な顔の正像、それが現れるのは、装置の真正面に顔を据えたときだけである。映り込むことなく鏡の真正面の風景を見られたのは「誰でもない者」だけであった。その者になって装置をのぞき込めば、他人の眼に映る自分が見つめ返す。

「Topograph」は、20世紀初頭のコラージュを、それと原理的に異なるラインスキャンカメラによって再演し、言わば偽の標本として正方形のフレームに納めた作品である。ラインスキャンカメラは、名前の通り1ピクセル幅の線で対象をスキャンし、その線(1次元)を積分して画像(2次元)を作る。この作品の衝撃は、それが異なるパースペクティヴのレイヤーコラージュではなく、ストレート写真だということである。ラインスキャンカメラはこのように世界を「見て」いるのであり、そもそもパースという概念はないのだ!

「Toposcan」も、モダニズム初期の絵画の問題 —風景の分解と再構成、セザンヌのサント・ヴィクトワール山やポスト印象派— を参照しているが、その風景とはヨーロッパ/地中海文明の象徴、「海辺の墓地」(ヴァレリー)である。パノラマモードでスキャンされたその風景が、順々に画面右端ないし左端から、超高速(画像は走る無数の色線に分解)→ 通常速度(映像)→ 静止(写真)→ ふたたび高速の色線という移行を繰りかえす。これは静止フレームを連続させた見かけ上の動画ではない、真の動画であり、その基層(※1)にはカラフルな線の高速運動があるのみである。速度が変化するにつれ、人間にはその運動が「映像」として、「写真」として現れる。

スキャニングは上記4つの特性をもたない。それは原理的に「像」による視覚ではない。1ピクセルの線は、少なくとも人間にとって像とは言えないだろう。それは空間的な結像ではなく、距離を超えた被写体情報の感受(「センサー」が被写体を線や点で触わりまくること)である。二次元画像を出力するとしても、それは現在の人間に合わせて「写真」に擬態しているにすぎない。その画像の単位もレイヤーではなく、線(ないし点)である。画像は走査した線分を積分した結果であって、「誰でもない者」が「見た」像ではない。従って代入や二重化もありえず、潜在的なレベル(外部、他者)も消える。
実際、デジタル技術は一元論的である。線から面が生成され、線の運動から面の運動も静止も生成される。つまり一次元も二次元も、時間の点も線も、静止画も動画も、死も生も、そして他者と自己も連続する。ただしこの連続性とは、ニルヴァーナ的な溶解ではなく、無限の分割(微分不可能性)である。無限に細かくなっていくピクセルによる解像度でスキャンする、そういう連続的視覚によるアートのなかからも、かつて写真という分裂的視覚がもたらしたような質的な切断が、そもそも生じうるのか、生じるとすれば、それはどのような切断だろうか。
こうして、写真がもたらした他者性を、20世紀初頭の平面表現を参照しつつ弔う、喪の作品を提示する本展は、現在のデジタル技術がもたらすだろう未知の他者性のための予習、という性格を持つ。似た問題意識の作家にトーマス・ルフや松江泰治が挙げられるが、デジタル技術は、動画と静止画にとどまらず、音(音響)と光(映像)をも連続(連動ではない)させるのだから、「切断」はまず、マルチメディア・アーティストの表現に訪れるのではないか。
しみず・みのる
同志社大学教授。著書に『日々是写真』『プルラモン―単数にして複数の存在』など。
高谷史郎『Topograph/ frost frame Europe 1987』展 (児玉画廊京都)2014/ 4/29〜6/14日
写真提供:児玉画廊
—
※1 ちなみに任意のネット上の画像を、すべて色彩のうねりに還元する、トーマス・ルフの「Substrat(基層)」のシリーズも、「Toposcan」より単純ではあるが、同じコンセプトである。
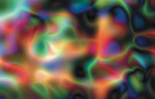
ギャラリー2階の会場に上がると、正面には「Topograph / La chambre claire」、その対面に新作の「Toposcan」、左右に「frost frame Europe 1987」が展示され、つまり、正対の壁はスキャニング、左右の壁は写真という配分で、そのあいだに「mirror type k2」が置かれていた。展覧会は「写真」と「スキャン」の対比、すなわち、アナログ写真がそのモデルとなるような視覚と、最新のデジタル技術が開拓しつつある未来の視覚の対比を軸に構成されているのである。人間の眼が、つねにある時代のテクノロジーに規定されるものだとすれば、本展は、写真に深く影響されて「見る」ことの時代がいよいよ過去となり、デジタルスキャンという方式で「見る」時代が到来したことを承認しつつ、その未知の視覚がもたらす奇妙さと美しさに対峙する、数少ない試みである。

展示風景(会場正面)
高谷史郎「Topograph / La chambre claire」

展示風景(対面)
高谷史郎「Toposcan」

展示風景(右面)
高谷史郎「frost frame Europe 1987」

展示風景(左面)
高谷史郎「frost frame Europe 1987」

展示風景 (正面と右面の間)
高谷史郎「mirror type k2」
端的に言って写真的な視覚とは、1)「像」による視覚であり、対象との距離を前提とする(レンズに密着しては像ができない)。2)その基本単位は面(レイヤー)。3)誰でもない者の視点からの像であり、見る人の肉眼がその視点に代入される。4)「誰でもない者」が「見た」像を、「ある誰か」が「見る」という重合から、現実と意識は分裂し二重化する。「見る」とは現在の中の過去、現在の中の潜在、自己の中の他者を見ることである。
「frost frame Europe 1987」は、遠近法構図を強調して撮影した「かつて」のヨーロッパの光景を、正方形のフレーム(=標本箱)に容れ、さらに(大型カメラのピントグラスを連想させる)フロストアクリルの彼方へ遠ざけた作品群である。写真的視覚(上記1と2)を、美しい棺に納めて、ノスタルジックな過去へと遠ざける。

高谷史郎「frost frame / Europe 1987 / pilotis 3」
2013 / Giclee print, frost acrylic frame / 91.2 x 91.2 cm (36” x 36”)
「写真」から「スキャン」への橋渡し的な位置を占める「mirror type k2」は、写真的視覚(上記3と4;時差と二重化)を修正する、シンプルでユーモラスな装置。写真に(「写った」ではなく)写る自分の顔をライヴで見る鏡である。他人には珍しくもない、本人にとってのみ衝撃的な顔の正像、それが現れるのは、装置の真正面に顔を据えたときだけである。映り込むことなく鏡の真正面の風景を見られたのは「誰でもない者」だけであった。その者になって装置をのぞき込めば、他人の眼に映る自分が見つめ返す。

高谷史郎「mirror type k2」
2013 / knife-edge right angle prism with optical glass
14 x 28 x 20(h) cm (5_1/2″ x 11″ x 7_3/4″)
「Topograph」は、20世紀初頭のコラージュを、それと原理的に異なるラインスキャンカメラによって再演し、言わば偽の標本として正方形のフレームに納めた作品である。ラインスキャンカメラは、名前の通り1ピクセル幅の線で対象をスキャンし、その線(1次元)を積分して画像(2次元)を作る。この作品の衝撃は、それが異なるパースペクティヴのレイヤーコラージュではなく、ストレート写真だということである。ラインスキャンカメラはこのように世界を「見て」いるのであり、そもそもパースという概念はないのだ!

高谷史郎「Topograph / La chambre claire 3」
2013 / Giclee print, mounted on Alpolic
100 x 100 cm (39_1/4” x 39_1/4”)
「Toposcan」も、モダニズム初期の絵画の問題 —風景の分解と再構成、セザンヌのサント・ヴィクトワール山やポスト印象派— を参照しているが、その風景とはヨーロッパ/地中海文明の象徴、「海辺の墓地」(ヴァレリー)である。パノラマモードでスキャンされたその風景が、順々に画面右端ないし左端から、超高速(画像は走る無数の色線に分解)→ 通常速度(映像)→ 静止(写真)→ ふたたび高速の色線という移行を繰りかえす。これは静止フレームを連続させた見かけ上の動画ではない、真の動画であり、その基層(※1)にはカラフルな線の高速運動があるのみである。速度が変化するにつれ、人間にはその運動が「映像」として、「写真」として現れる。

高谷史郎「Toposcan」
2014 / video installation / HD video, computer programing, plasma display
スキャニングは上記4つの特性をもたない。それは原理的に「像」による視覚ではない。1ピクセルの線は、少なくとも人間にとって像とは言えないだろう。それは空間的な結像ではなく、距離を超えた被写体情報の感受(「センサー」が被写体を線や点で触わりまくること)である。二次元画像を出力するとしても、それは現在の人間に合わせて「写真」に擬態しているにすぎない。その画像の単位もレイヤーではなく、線(ないし点)である。画像は走査した線分を積分した結果であって、「誰でもない者」が「見た」像ではない。従って代入や二重化もありえず、潜在的なレベル(外部、他者)も消える。
実際、デジタル技術は一元論的である。線から面が生成され、線の運動から面の運動も静止も生成される。つまり一次元も二次元も、時間の点も線も、静止画も動画も、死も生も、そして他者と自己も連続する。ただしこの連続性とは、ニルヴァーナ的な溶解ではなく、無限の分割(微分不可能性)である。無限に細かくなっていくピクセルによる解像度でスキャンする、そういう連続的視覚によるアートのなかからも、かつて写真という分裂的視覚がもたらしたような質的な切断が、そもそも生じうるのか、生じるとすれば、それはどのような切断だろうか。
こうして、写真がもたらした他者性を、20世紀初頭の平面表現を参照しつつ弔う、喪の作品を提示する本展は、現在のデジタル技術がもたらすだろう未知の他者性のための予習、という性格を持つ。似た問題意識の作家にトーマス・ルフや松江泰治が挙げられるが、デジタル技術は、動画と静止画にとどまらず、音(音響)と光(映像)をも連続(連動ではない)させるのだから、「切断」はまず、マルチメディア・アーティストの表現に訪れるのではないか。
しみず・みのる
同志社大学教授。著書に『日々是写真』『プルラモン―単数にして複数の存在』など。
高谷史郎『Topograph/ frost frame Europe 1987』展 (児玉画廊京都)2014/ 4/29〜6/14日
写真提供:児玉画廊
—
※1 ちなみに任意のネット上の画像を、すべて色彩のうねりに還元する、トーマス・ルフの「Substrat(基層)」のシリーズも、「Toposcan」より単純ではあるが、同じコンセプトである。
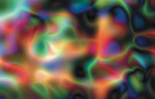
Thomas Ruff Substrat 22-I (2003)
(2014年7月3日公開)

