パリのテロとウエルベックの『服従』
浅田彰

1月7日にフランスで諷刺新聞『シャルリー・エブド』(チャーリー・ブラウンにちなむ名前なので『週刊チャーリー』と訳したいところ)による預言者ムハンマドの諷刺画に怒ったイスラム過激派が編集部を襲撃して5人の諷刺画家やライターを含む12人を殺害、並行して起こったユダヤ系食品店での人質立てこもり事件なども含めて、最終的に犠牲者は17人に上った(イスラム教徒も含まれる)。
『シャルリー』は1968年5月革命世代によるアナーキズム系の全方位斬りまくり諷刺新聞、前身が『Hara-Kiri』だったことからも推測できるように決して良識派の媒体ではない。筑紫哲也がインターネット上の匿名掲示板に溢れる書き込みを「便所の落書き」と呼んだことがあるが、あえて言えば『シャルリー』も「便所の落書き」に類するものだ。しかし、そもそもジャーナリズムや諷刺は「便所の落書き」から発生したと言うべきではないか。「便所の落書き」であるにもかかわらず、いやそれゆえにこそ、『シャルリー』は断固として擁護されねばならない。
ここで「言論・表現の自由といっても他者の信仰への一定の配慮が必要だ」などという「良識的」な留保は無用だ。フランスで言えば、そもそも旧体制の一部としてのキリスト教会に対する容赦ない諷刺と批判が近代を切り開いてきたのであり(「純朴なキリスト教徒を傷つけないように配慮を」などと言っていたら中世のままだったかもしれない——というのは大げさだが)、キリスト教の影響力が衰えた分、イスラム教が諷刺のターゲットとして浮上してきただけのことなのだ。
そのことを確認した上で言えば、フランス国内においてマイノリティであるイスラム教徒の信仰を一方的に愚弄するのは諷刺として良質とは言えないし、その意味では『シャルリー』も褒められたものではないだろう。しかし、低級な諷刺は社会的に軽視(さらには無視)すべきもので、「ヘイト表現禁止」のような形で法的に規制すべきものではない。そういう意味で、フランスの市民が「私はシャルリーだ」というスローガンのもと言論と表現の自由のために立ち上がったのは正しい(ちなみに1968年5月のスローガンのひとつ「われわれはみなドイツのユダヤ人だ」と比べると、「われわれ」から「私」への変化には時代の変化が如実に表れている)。
ただ、「私はシャルリーだ」というのがフランスの国民統合の合言葉のようになっていく一方、言論と表現に関する二重基準をあからさまに示す事件が起こった。『シャルリー』のイスラムに対する諷刺が許容されるのなら、ユダヤやイスラエルに対する諷刺も許容されるべきだろう。ところが違うのだ。「ハイル・ヒトラー」と「ファック・ユー」をまぜたようなジェスチャーで物議を醸し、ヘイト表現として何度も事実上の検閲を受けてきたデュードネ・バラ・バラというコメディアンがいる。彼はパレスチナ擁護で反イスラエル、それが反ユダヤ主義に近いということでフランスのヘイト表現禁止法に抵触したわけだ。そのデュードネが Facebookに「俺はシャルリー・クリバリのような気分だ」(クリバリはユダヤ系食品店で4人を人質にとって殺した容疑者)と書いて「シャルリー」翼賛体制をからかってみせたところ、それだけで警察に拘束されたのである。これは明らかに異常だ。確かにデュードネも芸人として褒められたものではなく、彼のギャグには「洒落にならない」ところがある。しかし、『シャルリー』を擁護するのならデュードネも擁護するべきなので、イスラムへの諷刺はよくてもユダヤへの諷刺はダメだというのは明白な二重基準と言うほかない。このような文脈において、言論と表現の自由を擁護すること(それ自体は完全に正しい)が、事実上、イスラムを批判すること(裏を返せばユダヤ=キリスト教文明を擁護すること)とほとんど等しくなるというイデオロギー的なずれが、徐々に表面化していったのである。
こうした世論を受けたフランス政府の対応を一瞥しておこう。事件をフランスの「9.11」ととらえる向きもあったが、総じて「9.11」後のブッシュのアメリカの対応とは違う方向を目指そうとしたことは、一応認めておいてよい。オランド大統領は「敵はテロリストであってイスラム教徒ではない」と明言し、1月11日に行われた抗議の行進(フランス全土で370万人が参加したと言われる)に欧州各国の首脳に加えイスラム諸国の首脳も招いた(オランド大統領を中心とする列にはパレスチナのアッバス議長とイスラエルのネタニヤフ首相も並んだ)。イスラム圏でもトルコのエルドアン大統領などは言論弾圧で悪名高く、他方、イスラエルのネタニヤフ首相にいたってはパレスチナ側のジャーナリストを多数殺害してきたのだから、彼らが言論と表現の自由のために行進するというのは噴飯ものだが、政治ショーというのは元来そうしたものだろう。
しかし、ヴァルス首相が国会での演説で「フランスはテロリズム、ジハード主義、過激イスラム主義との戦争状態にある」と踏み込み(*注)、オランド大統領もIS(「イスラム国」)空爆のためペルシア湾に向けて出港する空母シャルル・ドゴールに乗り込んで「対テロ戦争」に参加する兵士たちを激励する、それによって低迷していた支持率が急上昇する、といったその後の流れを見ていると、ブッシュのアメリカをあれほど批判していたフランスも結局は同じことをしていると言わざるを得ないだろう。
また逆に、行進に左右すべての党派を招きながら極右の国民戦線は排除した、これは結果的に国民戦線の立場を強めることになりかねない。そもそも「他者に開かれた多文化社会」を目指しつつ、実際は移民をフランス人の嫌がる仕事のための安価な労働力として使い、「郊外」という名のゲットーに隔離してきたわけで、そういう移民の若者の鬱屈をイスラム原理主義が吸収したあげく今回のようなテロが起きたと考えられる。国民戦線はそういう多文化主義の偽善を右翼の側から批判して大衆の支持を集めてきたのだ(とくに、古臭い極右だったジャン=マリー・ル・ペンに対し、後継者である娘のマリーヌは移民問題などをめぐって大衆の生活感情をとらえるのがうまく、今回は事件後ただちに『ニューヨーク・タイムズ』に寄稿するといったしたたかな国際感覚も見せている)。「多文化主義の建前を奉ずる偽善的言説のアゴラから排除された国民戦線こそが、そのようなアゴラの外の現実的矛盾を直視し解決しようとしているのだ」という主張にいっそうの説得力を与えてしまったとすれば、国民戦線の排除は賢明だったとは言い難いのではないか。
いずれにせよ、テロ後のフランスは、「9.11」後のアメリカほどではないにせよ、やはり大きく右傾化したと見るべきだろうし、「9.11」で始まった世界的な流れを再び加速することになったと言うべきだろう。移民問題に集約されるグローバル資本主義の矛盾の激発が、「文明の衝突」の焦点としての「宗教戦争」というイデオロギー的な表象に回収されてしまい、ユダヤ=キリスト教の側でもイスラム教の側でも宗教的情熱が火に油を注ぐ結果となっている——もともと、移民の若者たちも、彼らをリクルートしたと言われるISなどのイスラム原理主義組織も、本来のイスラム教主流とはほとんど無関係であるにもかかわらず。21世紀はいまだ「9.11」の呪縛から抜ける道を見いだせずにいるかに見える。
(*注)
9.11直後に言ったごく当たり前のことを念のために繰り返しておけば、戦争は国家と国家が行なうものであるのに対し、テロは(国家によるものを除き)あくまで犯罪であって警察が検挙し裁判にかけるべきものである。ところがアメリカが「対ドラッグ戦争」や「対テロ戦争」という言葉を一般化した結果、戦争だから裁判なしに敵を殺しても拘束してもいい、しかも、敵は国家ではないから、敵国に宣戦布告することなくその領土で勝手に敵を攻撃(たとえば空爆)してもいい、というような驚くべき無法状態に陥った。民間の論者が議論をわかりやすくするため「ドラッグ・カルテルやテロ組織が国家を超える力をもつケースが増え、国家がそのような非国家と行う非対称戦争が重要になってきた」などと言っても許されるだろうが、法治国家の政治家や軍人が「戦争」という言葉をそうやってメタフォリカルに濫用し、超法規的な実力行使に走るのは、見過ごすことのできない大問題なのだ。
思い返せば、今年はオウム真理教による地下鉄サリン事件の20周年になるが、あの教団も独立国家と称して省庁などの組織をもっていたらしい。その意味では、たとえばISもオウム真理教を巨大かつ強力にしたようなものなのであり、「ISと戦争する」というのは「オウム真理教と戦争する」というのと同様、ポストモダンな誇大妄想によって膨れ上がった組織を国家と認めるようなものなのだ。もちろんオウム真理教は国家ではなく、ISも国家ではない。そして、ついでに再確認しておくなら、オウム真理教が仏教を代表するものではないように、ISもイスラム教を代表するものではない。
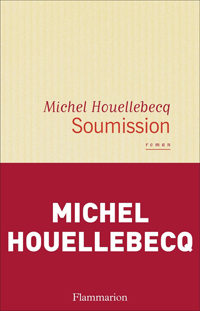
ところで、1月7日の段階でキオスクの店頭にあった『シャルリー』の表紙は何だったか。ノストラダムスめいた預言者として描かれたミシェル・ウエルベックの肖像である。奇しくも1月7日発売予定だったこのベストセラー作家の新作『服従』は、2022年の大統領選挙でムスリム同砲団(架空)が政権をとり、フランスがイスラム(それ自体「(神への)服従」を意味する)に服従する話であると予告され、マスメディアが前評判を煽っていた。それを踏まえて『シャルリー』もあらかじめ「預言者ウエルベック」をからかってみたということだろう。そして、実際にこの本が発売された1月7日に『シャルリー』編集部がイスラム過激派に襲撃され、『エコノミスト・ウエルベック』という本を出したばかりだったベルナール・マリス(経済学者で『シャルリー』にコラムを連載していた)も犠牲になったのである。テロはウエルベックの販売促進イヴェントではなかったのかという悪い冗談が語られるほど出来すぎた偶然だった。そして、あらかじめベストセラーになるべく予定されていた『服従』は、それを超えた歴史的事件となったのである。
私はいわばポストヒューマン/ポストヒューマニスティックな世界を淡々と描くウエルベックのニヒリズムに興味をもつ半面、1968年以後の多文化主義の建前を露悪的にひっくり返すことでセンセーションを起こすあざとい手法には批判的だった。とくに、彼をベストセラー作家にした『素粒子』(1998年)に続く長篇第二作『プラットフォーム』(2001年)には、「売春ツーリズムの何が悪い」と言わんばかりにタイに売春リゾートをつくる話が出てくる、それだけならまだしも、そこがイスラム過激派に襲撃されるという話でイスラモフォビアにも便乗しようとしているのは、あまりにあざといと思われた。フランスでアラン・ロブ=グリエの『反復』(2001年)が出たとき、ウエルベックの訳者でもある野崎歓とヌーヴォー・ロマンおよびそれ以後のフランス文学について対談したのだが(「壮麗なる廃墟のなかで」『早稲田文学』2002年7月号)、ヌーヴォー・ロマンがあり、J・M・G・ル・クレジオのポスト・フォークナー的小説があり、ジャン=フィリップ・トゥーサンのミニマリズム小説があり、その後でウエルベックを無視することはできないとはいえ、『プラットフォーム』はやり過ぎだろうという話になり、野崎歓もさすがにあれは訳す気にならないと言っていたのを思い出す(その後、別の訳者による邦訳が角川書店から刊行された)。とはいえ、第三作の『島の可能性』(2005年)はやはり興味深い作品だったし、第四作の『地図と領土』(2010年)は、ジェフ・クーンズやデミアン・ハーストのようにアートとビジネスを一体化させるあざといアーティストたちが活躍する現代のアート・シーンを背景とする小説ではあっても、それ自体はさほどあざとい小説ではなく、いささか図式的に過ぎるとはいえ、それなりに面白く読むことができた——ゴンクール賞を受賞したのは過大評価ではないかと思ったけれど。しかし、今度の『服従』は、前評判を聞く限り、やはりスキャンダル狙いの小説なのだろうなと思って、手を出さずにいた。テロをきっかけとして読んでみたというのが正直なところだ。しかし、読んでみると、確かに設定はスキャンダル狙い、しかし内容的にはこれがなかなか興味深い小説だったのである。
刊行前後に出た数多くのインタヴューをいくつか拾い読みしたところ、ウエルベックはもともと『回心・改宗(Conversion)』というタイトルを考えていたらしい。革命後のアトミスティックな社会は宗教なしでは崩壊してしまうという19世紀の社会思想家、とくにオーギュスト・コントのヴィジョンを踏まえ、1968年以後ますます規範が弱まりますますアトミスティックになった社会が宗教回帰に向かう過程を描こうというわけだ。主人公はユイスマンス(1848〜1907)を専門とするパリ大学文学部教授で、自然主義から出発して『さかしま』(1884)で世紀末デカダン唯美主義に転じたユイスマンスが最後にカトリックに改宗したように、カトリックに改宗する——という話になるはずが、しかし、ウエルベックはどうもうまく書けなかったという。確かに、それだけならあまり面白い小説にはならなかっただろう。
そこで、2022年の大統領選挙でフランスにイスラム政権ができるという設定が導入された。2017年の大統領選挙でマリーヌ・ル・ペンの国民戦線が単独では一位になり、国民戦線政権だけは避けようという諸党派の合意に基づいて現職のオランドが決選投票に勝つのだけれど、その下でますます矛盾が激化し、2022年にはル・ペンがさらに大統領に近づく。そこにムスリム同胞団(架空)が登場するわけだ。とはいえ、それはイスラム過激派とはまったく違って、エコール・ポリテクニークと国立行政大学院(ENA)を出た如才ない若きエリートが党首を務めている。これなら国民戦線よりましではないか。いや、EU/ユーロ圏からの離脱を目指す国民戦線に対し、ヨーロッパをアフリカ北岸まで拡大しようとするムスリム同胞団の方が、資本の利害にも合致している。そこで、社会党から保守党までみながムスリム同胞団と連立を組んでイスラム政権が出来てしまう、というわけだ。荒唐無稽に見えて、それなりにリアルな想定ではないか。(ここでウエルベックがパラダイムとしているのは、2002年の大統領選挙で右のシラクと左のジョスパンが対決するはずだったのに極右のジャン=マリー・ル・ペンがジョスパンに勝って決選投票に残ってしまい、仕方なく他の全党派がシラクを支持した、あの現実の悪夢である。)
こうしてイスラム政権が出来ると、郊外の治安は一気に改善され、アラブのオイル・マネーが流入して財政もぐんと改善される。その一方で、しかし、社会的にはかなりラディカルな変革が進む。一言でいうと中世回帰だ。経済的には、生産手段の私有(資本主義)か国有(ソ連型社会主義)かが問題ではなく、生産手段を分散させて小さなアトリエのネットワークのようなものを主とする経済をつくることが大切だ、というチェスタートン流の分配主義が採用される。もちろんチェスタートンはこれをカトリック社会主義に近い立場で主張したのだが、それはシャリーア(イスラム法)とも適合するだろう、というわけだ。それに伴って、高等教育は大幅に縮減し、職業教育を充実させる。ソルボンヌもイスラム大学になり、主人公は教授を辞めることになる。しかし、彼は冷静だ。まだ40代なのに定年まで勤めたのと同じ年金が出るし、考えてみれば文学教育など95%の学生には無意味なのだから未練などない、ときどき女子学生と性関係をもっていた、その機会を失うのは残念だが、そもそもそんな性生活は荒涼としたものでしかなかった……。社会的にも、近代の「ロマンティック・ラヴ」イデオロギーは放棄され、恋愛結婚から見合い結婚に戻る、しかしイスラム教では一夫多妻制が認められるのだから、結構な話じゃないか……。
こうして大学を辞めた主人公は、ユイスマンスの足跡をたどりつつ無神論からカトリックに改宗するかと思いきや、どうもそうはいかない。他方、かつてフランスのアイデンティティを声高に唱えていたイデオローグは早々とイスラム教に改宗してソルボンヌの学長になり、主人公に大学への復帰を促す。それで最後には、主人公もイスラム教に改宗して大学に復帰する——ただし、そこは条件法(「だろう」)で書かれている。最後の頁にあるのは「私は何ら後悔しないだろう」という一文だけだ。
ウエルベックは『プラットフォーム』ではイスラモフォビアを煽る書き方・売り方をしていたし、『服従』もそのように売られてベストセラーになっている。しかし、いまざっと見たように、作品自体は、西洋の没落とイスラム(繰り返せば、それ自体「(神への)服従」という意味)への服従を穏やかなニヒリズムをもって冷静に受け入れるという物語を、これまた冷静に語るというものなのだ。その静かなトーンは、センセーショナルな物語を求めて『服従』を読み始めた読者を当惑させるかもしれない。だが、彼自身の仕掛けるセンセーションの背後に最初からあったウエルベックの本領とは、むしろこのようなものだろう。『服従』ではニーチェも話題になるが、これはいわばニーチェの「末人(最後の人間)」の文学なのだ。
だが、問題は、現実世界の人間がどうやら「末人」にはなりきれないらしいということだ。穏やかなニヒリズムに満足しない鬱屈した情念は、非合理としか言いようのない「大義」——たとえばイスラム原理主義のそれに流れ込むだろう。西洋も冷静な「服従」と安楽死に向かうどころか、とっくに忘れていたはずの十字軍的な情熱さえ新たに燃え上がらせるかもしれない。歴史の流れがそういう方向に加速されていくかもしれない2015.1.7というモーメントに、ウエルベックの『服従』は立つ——センセーショナルなモニュメントとしてではなく、あくまでもクールでドライなアンチ・モニュメントとして。
伊丹市立美術館は諷刺画家ドーミエの世界有数のコレクションをもち、「風刺とユーモア」を重要なコンセプトとして活動してきている(伊丹は江戸時代有数の清酒の産地であり、それにつられて多くの俳人が往来した。隣接する柿衞文庫がそうした俳諧・俳句に関するコレクションを核としているところにも、一種の一貫性を見てとれる)。いまはドーミエは見ることができないけれど、かわりにコレクション展の一環として「シャレにしてオツなり——宮武外骨没後60周年記念」展が開催されている。実は私は1985年に熱心な外骨マニアだった赤瀬川原平(1937-2014)を種村季弘(1933-2004)とともに囲むシンポジウムに出たことがあり、とっくに忘れていたその記録が去年およそ20年ぶりに活字になったところだった(「予は危険人物なり——外骨ワンダーランド」『文藝別冊・赤瀬川原平』河出書房新社、2014年10月30日)。千葉市美術館で10月28日から開催された「赤瀬川原平の芸術原論」展に合わせた出版だが、その展覧会のオープニングの直前、長く病床にあったアーティストの訃報が伝えられたのだ。展覧会(現在は大分市美術館で開催中、3月21日から広島市現代美術館にも巡回予定)は作品や情報が満載できわめて興味深いものだったし、ついでに言えば少し前に板橋区立美術館で開かれた「種村季弘の眼 迷宮の美術家たち」展もなかなか面白いものだったが、それだけに生前の彼らにもっといろいろな話を聞いておきたかったという後悔の念は強まるばかりだ。とくに、早すぎた晩年の赤瀬川原平はもっぱらユーモラスな「老人力」の人として有名になり、過激な前衛としての顔が忘れられたかに見える。実は宮武外骨についても同様だ。たしかに彼の諷刺は「シャレにしてオツ」だったが、そのような「愛嬌」は「過激」と背中合わせだったのである。今回の外骨展にも、明治天皇ならぬ骸骨が大日本帝国憲法ならぬ頓智研法を発布する図が展示されているが、この骸骨の図によって外骨は不敬罪に問われ、未決拘留期間も含めて3年8ヶ月を獄中で過ごすことになったのだ(この図が墨で塗りつぶされた雑誌の頁も展示されている)。過激にして愛嬌あり。これが宮武外骨であり、そして赤瀬川原平であった。確かに、良質の諷刺には愛嬌がつきものである。しかし、過激でない諷刺、「他者への配慮」によって去勢された諷刺など諷刺とは言えず、諷刺のないところには民主主義も文化もない。
(後記)
1月17日の夕刻に東京・五反田のゲンロン・カフェで東浩紀の司会のもと中沢新一と語る機会があった(記録の一部は『新潮』4月号に掲載予定)。東京に向かう車中でウエルベックの『服従』を読んだので、鼎談でも話題のひとつとして取り上げたのだが、ライヴでは十分に語れなかったところが多い。大体そのときの論点を踏まえつつ欠落を埋めてリライトしたものを、ここに書評として掲載する次第である。

『シャルリー・エブド』2015年1月7日号
“Charlie Hebdo” 7 January 2015
1月7日にフランスで諷刺新聞『シャルリー・エブド』(チャーリー・ブラウンにちなむ名前なので『週刊チャーリー』と訳したいところ)による預言者ムハンマドの諷刺画に怒ったイスラム過激派が編集部を襲撃して5人の諷刺画家やライターを含む12人を殺害、並行して起こったユダヤ系食品店での人質立てこもり事件なども含めて、最終的に犠牲者は17人に上った(イスラム教徒も含まれる)。
『シャルリー』は1968年5月革命世代によるアナーキズム系の全方位斬りまくり諷刺新聞、前身が『Hara-Kiri』だったことからも推測できるように決して良識派の媒体ではない。筑紫哲也がインターネット上の匿名掲示板に溢れる書き込みを「便所の落書き」と呼んだことがあるが、あえて言えば『シャルリー』も「便所の落書き」に類するものだ。しかし、そもそもジャーナリズムや諷刺は「便所の落書き」から発生したと言うべきではないか。「便所の落書き」であるにもかかわらず、いやそれゆえにこそ、『シャルリー』は断固として擁護されねばならない。
ここで「言論・表現の自由といっても他者の信仰への一定の配慮が必要だ」などという「良識的」な留保は無用だ。フランスで言えば、そもそも旧体制の一部としてのキリスト教会に対する容赦ない諷刺と批判が近代を切り開いてきたのであり(「純朴なキリスト教徒を傷つけないように配慮を」などと言っていたら中世のままだったかもしれない——というのは大げさだが)、キリスト教の影響力が衰えた分、イスラム教が諷刺のターゲットとして浮上してきただけのことなのだ。
そのことを確認した上で言えば、フランス国内においてマイノリティであるイスラム教徒の信仰を一方的に愚弄するのは諷刺として良質とは言えないし、その意味では『シャルリー』も褒められたものではないだろう。しかし、低級な諷刺は社会的に軽視(さらには無視)すべきもので、「ヘイト表現禁止」のような形で法的に規制すべきものではない。そういう意味で、フランスの市民が「私はシャルリーだ」というスローガンのもと言論と表現の自由のために立ち上がったのは正しい(ちなみに1968年5月のスローガンのひとつ「われわれはみなドイツのユダヤ人だ」と比べると、「われわれ」から「私」への変化には時代の変化が如実に表れている)。
ただ、「私はシャルリーだ」というのがフランスの国民統合の合言葉のようになっていく一方、言論と表現に関する二重基準をあからさまに示す事件が起こった。『シャルリー』のイスラムに対する諷刺が許容されるのなら、ユダヤやイスラエルに対する諷刺も許容されるべきだろう。ところが違うのだ。「ハイル・ヒトラー」と「ファック・ユー」をまぜたようなジェスチャーで物議を醸し、ヘイト表現として何度も事実上の検閲を受けてきたデュードネ・バラ・バラというコメディアンがいる。彼はパレスチナ擁護で反イスラエル、それが反ユダヤ主義に近いということでフランスのヘイト表現禁止法に抵触したわけだ。そのデュードネが Facebookに「俺はシャルリー・クリバリのような気分だ」(クリバリはユダヤ系食品店で4人を人質にとって殺した容疑者)と書いて「シャルリー」翼賛体制をからかってみせたところ、それだけで警察に拘束されたのである。これは明らかに異常だ。確かにデュードネも芸人として褒められたものではなく、彼のギャグには「洒落にならない」ところがある。しかし、『シャルリー』を擁護するのならデュードネも擁護するべきなので、イスラムへの諷刺はよくてもユダヤへの諷刺はダメだというのは明白な二重基準と言うほかない。このような文脈において、言論と表現の自由を擁護すること(それ自体は完全に正しい)が、事実上、イスラムを批判すること(裏を返せばユダヤ=キリスト教文明を擁護すること)とほとんど等しくなるというイデオロギー的なずれが、徐々に表面化していったのである。
こうした世論を受けたフランス政府の対応を一瞥しておこう。事件をフランスの「9.11」ととらえる向きもあったが、総じて「9.11」後のブッシュのアメリカの対応とは違う方向を目指そうとしたことは、一応認めておいてよい。オランド大統領は「敵はテロリストであってイスラム教徒ではない」と明言し、1月11日に行われた抗議の行進(フランス全土で370万人が参加したと言われる)に欧州各国の首脳に加えイスラム諸国の首脳も招いた(オランド大統領を中心とする列にはパレスチナのアッバス議長とイスラエルのネタニヤフ首相も並んだ)。イスラム圏でもトルコのエルドアン大統領などは言論弾圧で悪名高く、他方、イスラエルのネタニヤフ首相にいたってはパレスチナ側のジャーナリストを多数殺害してきたのだから、彼らが言論と表現の自由のために行進するというのは噴飯ものだが、政治ショーというのは元来そうしたものだろう。
しかし、ヴァルス首相が国会での演説で「フランスはテロリズム、ジハード主義、過激イスラム主義との戦争状態にある」と踏み込み(*注)、オランド大統領もIS(「イスラム国」)空爆のためペルシア湾に向けて出港する空母シャルル・ドゴールに乗り込んで「対テロ戦争」に参加する兵士たちを激励する、それによって低迷していた支持率が急上昇する、といったその後の流れを見ていると、ブッシュのアメリカをあれほど批判していたフランスも結局は同じことをしていると言わざるを得ないだろう。
また逆に、行進に左右すべての党派を招きながら極右の国民戦線は排除した、これは結果的に国民戦線の立場を強めることになりかねない。そもそも「他者に開かれた多文化社会」を目指しつつ、実際は移民をフランス人の嫌がる仕事のための安価な労働力として使い、「郊外」という名のゲットーに隔離してきたわけで、そういう移民の若者の鬱屈をイスラム原理主義が吸収したあげく今回のようなテロが起きたと考えられる。国民戦線はそういう多文化主義の偽善を右翼の側から批判して大衆の支持を集めてきたのだ(とくに、古臭い極右だったジャン=マリー・ル・ペンに対し、後継者である娘のマリーヌは移民問題などをめぐって大衆の生活感情をとらえるのがうまく、今回は事件後ただちに『ニューヨーク・タイムズ』に寄稿するといったしたたかな国際感覚も見せている)。「多文化主義の建前を奉ずる偽善的言説のアゴラから排除された国民戦線こそが、そのようなアゴラの外の現実的矛盾を直視し解決しようとしているのだ」という主張にいっそうの説得力を与えてしまったとすれば、国民戦線の排除は賢明だったとは言い難いのではないか。
いずれにせよ、テロ後のフランスは、「9.11」後のアメリカほどではないにせよ、やはり大きく右傾化したと見るべきだろうし、「9.11」で始まった世界的な流れを再び加速することになったと言うべきだろう。移民問題に集約されるグローバル資本主義の矛盾の激発が、「文明の衝突」の焦点としての「宗教戦争」というイデオロギー的な表象に回収されてしまい、ユダヤ=キリスト教の側でもイスラム教の側でも宗教的情熱が火に油を注ぐ結果となっている——もともと、移民の若者たちも、彼らをリクルートしたと言われるISなどのイスラム原理主義組織も、本来のイスラム教主流とはほとんど無関係であるにもかかわらず。21世紀はいまだ「9.11」の呪縛から抜ける道を見いだせずにいるかに見える。
(*注)
9.11直後に言ったごく当たり前のことを念のために繰り返しておけば、戦争は国家と国家が行なうものであるのに対し、テロは(国家によるものを除き)あくまで犯罪であって警察が検挙し裁判にかけるべきものである。ところがアメリカが「対ドラッグ戦争」や「対テロ戦争」という言葉を一般化した結果、戦争だから裁判なしに敵を殺しても拘束してもいい、しかも、敵は国家ではないから、敵国に宣戦布告することなくその領土で勝手に敵を攻撃(たとえば空爆)してもいい、というような驚くべき無法状態に陥った。民間の論者が議論をわかりやすくするため「ドラッグ・カルテルやテロ組織が国家を超える力をもつケースが増え、国家がそのような非国家と行う非対称戦争が重要になってきた」などと言っても許されるだろうが、法治国家の政治家や軍人が「戦争」という言葉をそうやってメタフォリカルに濫用し、超法規的な実力行使に走るのは、見過ごすことのできない大問題なのだ。
思い返せば、今年はオウム真理教による地下鉄サリン事件の20周年になるが、あの教団も独立国家と称して省庁などの組織をもっていたらしい。その意味では、たとえばISもオウム真理教を巨大かつ強力にしたようなものなのであり、「ISと戦争する」というのは「オウム真理教と戦争する」というのと同様、ポストモダンな誇大妄想によって膨れ上がった組織を国家と認めるようなものなのだ。もちろんオウム真理教は国家ではなく、ISも国家ではない。そして、ついでに再確認しておくなら、オウム真理教が仏教を代表するものではないように、ISもイスラム教を代表するものではない。
❖
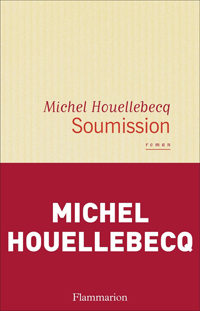
ミシェル・ウエルベック『服従』
Michel Houellebecq “Soumission”
ところで、1月7日の段階でキオスクの店頭にあった『シャルリー』の表紙は何だったか。ノストラダムスめいた預言者として描かれたミシェル・ウエルベックの肖像である。奇しくも1月7日発売予定だったこのベストセラー作家の新作『服従』は、2022年の大統領選挙でムスリム同砲団(架空)が政権をとり、フランスがイスラム(それ自体「(神への)服従」を意味する)に服従する話であると予告され、マスメディアが前評判を煽っていた。それを踏まえて『シャルリー』もあらかじめ「預言者ウエルベック」をからかってみたということだろう。そして、実際にこの本が発売された1月7日に『シャルリー』編集部がイスラム過激派に襲撃され、『エコノミスト・ウエルベック』という本を出したばかりだったベルナール・マリス(経済学者で『シャルリー』にコラムを連載していた)も犠牲になったのである。テロはウエルベックの販売促進イヴェントではなかったのかという悪い冗談が語られるほど出来すぎた偶然だった。そして、あらかじめベストセラーになるべく予定されていた『服従』は、それを超えた歴史的事件となったのである。
私はいわばポストヒューマン/ポストヒューマニスティックな世界を淡々と描くウエルベックのニヒリズムに興味をもつ半面、1968年以後の多文化主義の建前を露悪的にひっくり返すことでセンセーションを起こすあざとい手法には批判的だった。とくに、彼をベストセラー作家にした『素粒子』(1998年)に続く長篇第二作『プラットフォーム』(2001年)には、「売春ツーリズムの何が悪い」と言わんばかりにタイに売春リゾートをつくる話が出てくる、それだけならまだしも、そこがイスラム過激派に襲撃されるという話でイスラモフォビアにも便乗しようとしているのは、あまりにあざといと思われた。フランスでアラン・ロブ=グリエの『反復』(2001年)が出たとき、ウエルベックの訳者でもある野崎歓とヌーヴォー・ロマンおよびそれ以後のフランス文学について対談したのだが(「壮麗なる廃墟のなかで」『早稲田文学』2002年7月号)、ヌーヴォー・ロマンがあり、J・M・G・ル・クレジオのポスト・フォークナー的小説があり、ジャン=フィリップ・トゥーサンのミニマリズム小説があり、その後でウエルベックを無視することはできないとはいえ、『プラットフォーム』はやり過ぎだろうという話になり、野崎歓もさすがにあれは訳す気にならないと言っていたのを思い出す(その後、別の訳者による邦訳が角川書店から刊行された)。とはいえ、第三作の『島の可能性』(2005年)はやはり興味深い作品だったし、第四作の『地図と領土』(2010年)は、ジェフ・クーンズやデミアン・ハーストのようにアートとビジネスを一体化させるあざといアーティストたちが活躍する現代のアート・シーンを背景とする小説ではあっても、それ自体はさほどあざとい小説ではなく、いささか図式的に過ぎるとはいえ、それなりに面白く読むことができた——ゴンクール賞を受賞したのは過大評価ではないかと思ったけれど。しかし、今度の『服従』は、前評判を聞く限り、やはりスキャンダル狙いの小説なのだろうなと思って、手を出さずにいた。テロをきっかけとして読んでみたというのが正直なところだ。しかし、読んでみると、確かに設定はスキャンダル狙い、しかし内容的にはこれがなかなか興味深い小説だったのである。
刊行前後に出た数多くのインタヴューをいくつか拾い読みしたところ、ウエルベックはもともと『回心・改宗(Conversion)』というタイトルを考えていたらしい。革命後のアトミスティックな社会は宗教なしでは崩壊してしまうという19世紀の社会思想家、とくにオーギュスト・コントのヴィジョンを踏まえ、1968年以後ますます規範が弱まりますますアトミスティックになった社会が宗教回帰に向かう過程を描こうというわけだ。主人公はユイスマンス(1848〜1907)を専門とするパリ大学文学部教授で、自然主義から出発して『さかしま』(1884)で世紀末デカダン唯美主義に転じたユイスマンスが最後にカトリックに改宗したように、カトリックに改宗する——という話になるはずが、しかし、ウエルベックはどうもうまく書けなかったという。確かに、それだけならあまり面白い小説にはならなかっただろう。
そこで、2022年の大統領選挙でフランスにイスラム政権ができるという設定が導入された。2017年の大統領選挙でマリーヌ・ル・ペンの国民戦線が単独では一位になり、国民戦線政権だけは避けようという諸党派の合意に基づいて現職のオランドが決選投票に勝つのだけれど、その下でますます矛盾が激化し、2022年にはル・ペンがさらに大統領に近づく。そこにムスリム同胞団(架空)が登場するわけだ。とはいえ、それはイスラム過激派とはまったく違って、エコール・ポリテクニークと国立行政大学院(ENA)を出た如才ない若きエリートが党首を務めている。これなら国民戦線よりましではないか。いや、EU/ユーロ圏からの離脱を目指す国民戦線に対し、ヨーロッパをアフリカ北岸まで拡大しようとするムスリム同胞団の方が、資本の利害にも合致している。そこで、社会党から保守党までみながムスリム同胞団と連立を組んでイスラム政権が出来てしまう、というわけだ。荒唐無稽に見えて、それなりにリアルな想定ではないか。(ここでウエルベックがパラダイムとしているのは、2002年の大統領選挙で右のシラクと左のジョスパンが対決するはずだったのに極右のジャン=マリー・ル・ペンがジョスパンに勝って決選投票に残ってしまい、仕方なく他の全党派がシラクを支持した、あの現実の悪夢である。)
こうしてイスラム政権が出来ると、郊外の治安は一気に改善され、アラブのオイル・マネーが流入して財政もぐんと改善される。その一方で、しかし、社会的にはかなりラディカルな変革が進む。一言でいうと中世回帰だ。経済的には、生産手段の私有(資本主義)か国有(ソ連型社会主義)かが問題ではなく、生産手段を分散させて小さなアトリエのネットワークのようなものを主とする経済をつくることが大切だ、というチェスタートン流の分配主義が採用される。もちろんチェスタートンはこれをカトリック社会主義に近い立場で主張したのだが、それはシャリーア(イスラム法)とも適合するだろう、というわけだ。それに伴って、高等教育は大幅に縮減し、職業教育を充実させる。ソルボンヌもイスラム大学になり、主人公は教授を辞めることになる。しかし、彼は冷静だ。まだ40代なのに定年まで勤めたのと同じ年金が出るし、考えてみれば文学教育など95%の学生には無意味なのだから未練などない、ときどき女子学生と性関係をもっていた、その機会を失うのは残念だが、そもそもそんな性生活は荒涼としたものでしかなかった……。社会的にも、近代の「ロマンティック・ラヴ」イデオロギーは放棄され、恋愛結婚から見合い結婚に戻る、しかしイスラム教では一夫多妻制が認められるのだから、結構な話じゃないか……。
こうして大学を辞めた主人公は、ユイスマンスの足跡をたどりつつ無神論からカトリックに改宗するかと思いきや、どうもそうはいかない。他方、かつてフランスのアイデンティティを声高に唱えていたイデオローグは早々とイスラム教に改宗してソルボンヌの学長になり、主人公に大学への復帰を促す。それで最後には、主人公もイスラム教に改宗して大学に復帰する——ただし、そこは条件法(「だろう」)で書かれている。最後の頁にあるのは「私は何ら後悔しないだろう」という一文だけだ。
ウエルベックは『プラットフォーム』ではイスラモフォビアを煽る書き方・売り方をしていたし、『服従』もそのように売られてベストセラーになっている。しかし、いまざっと見たように、作品自体は、西洋の没落とイスラム(繰り返せば、それ自体「(神への)服従」という意味)への服従を穏やかなニヒリズムをもって冷静に受け入れるという物語を、これまた冷静に語るというものなのだ。その静かなトーンは、センセーショナルな物語を求めて『服従』を読み始めた読者を当惑させるかもしれない。だが、彼自身の仕掛けるセンセーションの背後に最初からあったウエルベックの本領とは、むしろこのようなものだろう。『服従』ではニーチェも話題になるが、これはいわばニーチェの「末人(最後の人間)」の文学なのだ。
だが、問題は、現実世界の人間がどうやら「末人」にはなりきれないらしいということだ。穏やかなニヒリズムに満足しない鬱屈した情念は、非合理としか言いようのない「大義」——たとえばイスラム原理主義のそれに流れ込むだろう。西洋も冷静な「服従」と安楽死に向かうどころか、とっくに忘れていたはずの十字軍的な情熱さえ新たに燃え上がらせるかもしれない。歴史の流れがそういう方向に加速されていくかもしれない2015.1.7というモーメントに、ウエルベックの『服従』は立つ——センセーショナルなモニュメントとしてではなく、あくまでもクールでドライなアンチ・モニュメントとして。
❖
最後に、直接の関連はないが、アート・シーンから諷刺にかかわる情報をひとつだけ。伊丹市立美術館は諷刺画家ドーミエの世界有数のコレクションをもち、「風刺とユーモア」を重要なコンセプトとして活動してきている(伊丹は江戸時代有数の清酒の産地であり、それにつられて多くの俳人が往来した。隣接する柿衞文庫がそうした俳諧・俳句に関するコレクションを核としているところにも、一種の一貫性を見てとれる)。いまはドーミエは見ることができないけれど、かわりにコレクション展の一環として「シャレにしてオツなり——宮武外骨没後60周年記念」展が開催されている。実は私は1985年に熱心な外骨マニアだった赤瀬川原平(1937-2014)を種村季弘(1933-2004)とともに囲むシンポジウムに出たことがあり、とっくに忘れていたその記録が去年およそ20年ぶりに活字になったところだった(「予は危険人物なり——外骨ワンダーランド」『文藝別冊・赤瀬川原平』河出書房新社、2014年10月30日)。千葉市美術館で10月28日から開催された「赤瀬川原平の芸術原論」展に合わせた出版だが、その展覧会のオープニングの直前、長く病床にあったアーティストの訃報が伝えられたのだ。展覧会(現在は大分市美術館で開催中、3月21日から広島市現代美術館にも巡回予定)は作品や情報が満載できわめて興味深いものだったし、ついでに言えば少し前に板橋区立美術館で開かれた「種村季弘の眼 迷宮の美術家たち」展もなかなか面白いものだったが、それだけに生前の彼らにもっといろいろな話を聞いておきたかったという後悔の念は強まるばかりだ。とくに、早すぎた晩年の赤瀬川原平はもっぱらユーモラスな「老人力」の人として有名になり、過激な前衛としての顔が忘れられたかに見える。実は宮武外骨についても同様だ。たしかに彼の諷刺は「シャレにしてオツ」だったが、そのような「愛嬌」は「過激」と背中合わせだったのである。今回の外骨展にも、明治天皇ならぬ骸骨が大日本帝国憲法ならぬ頓智研法を発布する図が展示されているが、この骸骨の図によって外骨は不敬罪に問われ、未決拘留期間も含めて3年8ヶ月を獄中で過ごすことになったのだ(この図が墨で塗りつぶされた雑誌の頁も展示されている)。過激にして愛嬌あり。これが宮武外骨であり、そして赤瀬川原平であった。確かに、良質の諷刺には愛嬌がつきものである。しかし、過激でない諷刺、「他者への配慮」によって去勢された諷刺など諷刺とは言えず、諷刺のないところには民主主義も文化もない。
(後記)
1月17日の夕刻に東京・五反田のゲンロン・カフェで東浩紀の司会のもと中沢新一と語る機会があった(記録の一部は『新潮』4月号に掲載予定)。東京に向かう車中でウエルベックの『服従』を読んだので、鼎談でも話題のひとつとして取り上げたのだが、ライヴでは十分に語れなかったところが多い。大体そのときの論点を踏まえつつ欠落を埋めてリライトしたものを、ここに書評として掲載する次第である。
(2015年1月17日)

