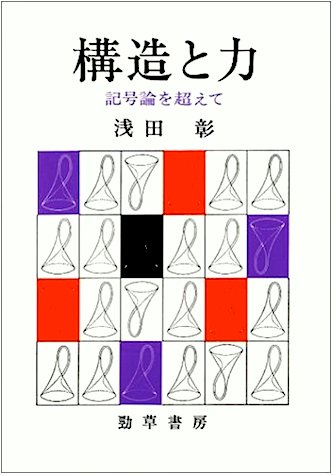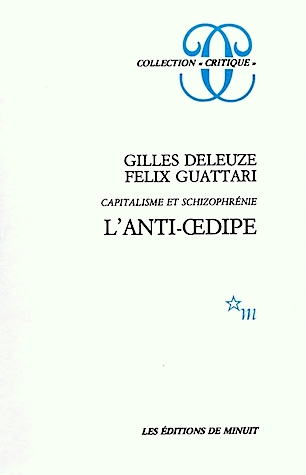プロフィール

浅田 彰(あさだ・あきら)
1957年、神戸市生まれ。
京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長。
同大で芸術哲学を講ずる一方、政治、経済、社会、また文学、映画、演劇、舞踊、音楽、美術、建築など、芸術諸分野においても多角的・多面的な批評活動を展開する。
著書に『構造と力』(勁草書房)、『逃走論』『ヘルメスの音楽』(以上、筑摩書房)、『映画の世紀末』(新潮社)、対談集に『「歴史の終わり」を超えて』(中公文庫)、『20世紀文化の臨界』(青土社)などがある。
最新のエントリー
- 19.05.01 昭和の終わり、平成の終わり
- 19.03.29 原美術館のドリス・ファン・ノーテン
- 19.03.07 マックイーンとマルジェラ――ファッション・ビジネスの大波の中で
- 18.12.07 映画のラスト・エンペラー――ベルナルド・ベルトルッチ追悼
- 18.11.03 トランプから/トランプへ(5)マクロンとトランプ
アーカイブ
- ▼2019年5月
- ▼2019年3月
- ▼2018年12月
- ▼2018年11月
- ▼2018年10月
- ▼2017年5月
- ▼2016年2月
- ▼2016年1月
- ▼2015年8月
- ▼2015年6月
- ▼2015年4月
- ▼2015年3月
- ▼2014年12月
- ▼2014年11月
- ▼2014年10月
- ▼2014年9月
- ▼2014年7月
- ▼2014年6月
- ▼2013年9月
- ▼2013年4月
- ▼2013年3月
- ▼2013年2月
- ▼2013年1月
- ▼2012年11月
- ▼2012年10月
- ▼2012年9月
『構造と力』刊行30周年
2013年09月10日
私の最初の本である『構造と力』が刊行されたのは、いまから30年前の1983年9月10日だ。幸い、この本はいまも現役で、すでに54刷を数えている。それが引き起こした「ニュー・アカデミズム」ブームの波が引いていった後も少しずつ着実に増刷し続けてくれた版元の勁草書房には、感謝しなければならない。30周年を記念して朝日新聞にインタヴューが掲載されたが(聞き手=高久潤:3月26日夕刊掲載)、ここにそのカット前のヴァージョンを公開する。
*
僕が26歳の時の本です。当時は現代思想といってもすべてがごた混ぜだった(マルクスやニーチェやフロイト、サルトルやメルロ=ポンティやラカン、ソシュールの構造言語学やレヴィ=ストロースの構造人類学、フーコーの系譜学やデリダの脱構築、etc.)ので、それさえ頭に入れておけば知の世界を自由に渉猟できるような明快な地図が描きたかったんですね。
そのため暴力的な単純化によって情報を圧縮する手法を取りました。そもそも僕は哲学に興味がなかったんで、哲学的な正確さは多少は犠牲にしてもいいと思ったんですね。マルクスの言ったように、哲学は世界をさまざまに解釈してきた。観念論か唯物論か、主観主義か客観主義か、解釈はどうにでも変更できる。しかし大切なのは世界を変革することなのだ、と。そのためには、現実に対するクリティーク(批評・批判)や、別の現実を構想するヴィジョン―それらを総合した「思想」が必要です。
しかし、とくに1972年の連合赤軍事件の後、日本ではマルクス主義思想が急激に退潮します。替わって、「どうせ資本主義しかない」というシニシズムのもと、問題が生じたらそのつどパッチを当てるというプラグマティックな「部分的社会工学」が支配的になる。それを補完するのが、ソ連流のドグマティックなマルクス主義を批判し、日本の「大衆の原像」あるいは「マス・イメージ」に立脚しようとする、吉本隆明流の思想でした。マルクス主義が退潮してしまえば、それは大衆の自足と自閉を肯定するだけになってしまうでしょう。こうした流れは、「(部分的)情報社会工学」と「オタク文化論」という現在支配的な思潮にそのまま受け継がれています。
そういう流れに抵抗するため、僕がヒントにしたのは、哲学者ジル・ドゥルーズが反精神医学者フェリックス・ガタリと組み、哲学的な正しさなどかなぐり捨てて書いた『アンチ・オイディプス』(1972年)でした。ユートピアはもはや不可能だと言われるようになった時代に、マルクスをニーチェやフロイトと結びつけながら、資本主義のダイナミズムを半ば肯定しつつ、さらにそれを超えたユートピアを大胆に描いてみせる。『構造と力』と『逃走論』では、それをモデルとして、いわばマルクスの思想をポップ化しようと思ったんですね。だから、一般向けの本として書いたのではないけれど、ベスト・セラーになっても驚くことはありませんでした。ただ、消費社会で使い捨てられることは警戒していた。次々に続編を書かなかったのは才能がないせいですが(僕にはどうしても書きたいという欲望がない、つまりは才能がないということです)、消費されることへの抵抗があったのも確かです。
現在、「難解」な理論や思想はもはや求められていないように見える。しかし、本当にそうか。グローバル資本主義が成立した結果、反資本主義の運動も世界中で激化している。もはや部分的社会工学ではカヴァーできない矛盾が噴出しているわけです。日本でも東北大震災を契機に反原発運動が広がっている。そこで大江健三郎さんや柄谷行人さんが語る原理的な言葉が多くの人々をとらえているのは、注目すべきことです。利口ぶったプラグマティストは「あんなナイーヴなことを言って」とシニカルに構えるけれど、それは間違っている。原点に帰って現実を批判し、別の現実を構想することが、求められているのです。
そのためにも、『構造と力』をヴァージョン・アップしたような新しい地図が必要になっているのかもしれない。とくに、東アジア諸国には、さまざまな伝統がある一方、日本が百年以上かけて受容してきた近代思想や現代思想が十年くらいで一挙に押し寄せている。議論を整理するためにも何らかの地図が必要でしょう。さもなければ、マイケル・サンデルの「ハーバード白熱教室」のようなアメリカの有名大学の「知」がすべてを呑み込んでしまう。それこそ悪しきグローバル化じゃないでしょうか。
*
僕が26歳の時の本です。当時は現代思想といってもすべてがごた混ぜだった(マルクスやニーチェやフロイト、サルトルやメルロ=ポンティやラカン、ソシュールの構造言語学やレヴィ=ストロースの構造人類学、フーコーの系譜学やデリダの脱構築、etc.)ので、それさえ頭に入れておけば知の世界を自由に渉猟できるような明快な地図が描きたかったんですね。
そのため暴力的な単純化によって情報を圧縮する手法を取りました。そもそも僕は哲学に興味がなかったんで、哲学的な正確さは多少は犠牲にしてもいいと思ったんですね。マルクスの言ったように、哲学は世界をさまざまに解釈してきた。観念論か唯物論か、主観主義か客観主義か、解釈はどうにでも変更できる。しかし大切なのは世界を変革することなのだ、と。そのためには、現実に対するクリティーク(批評・批判)や、別の現実を構想するヴィジョン―それらを総合した「思想」が必要です。
しかし、とくに1972年の連合赤軍事件の後、日本ではマルクス主義思想が急激に退潮します。替わって、「どうせ資本主義しかない」というシニシズムのもと、問題が生じたらそのつどパッチを当てるというプラグマティックな「部分的社会工学」が支配的になる。それを補完するのが、ソ連流のドグマティックなマルクス主義を批判し、日本の「大衆の原像」あるいは「マス・イメージ」に立脚しようとする、吉本隆明流の思想でした。マルクス主義が退潮してしまえば、それは大衆の自足と自閉を肯定するだけになってしまうでしょう。こうした流れは、「(部分的)情報社会工学」と「オタク文化論」という現在支配的な思潮にそのまま受け継がれています。
そういう流れに抵抗するため、僕がヒントにしたのは、哲学者ジル・ドゥルーズが反精神医学者フェリックス・ガタリと組み、哲学的な正しさなどかなぐり捨てて書いた『アンチ・オイディプス』(1972年)でした。ユートピアはもはや不可能だと言われるようになった時代に、マルクスをニーチェやフロイトと結びつけながら、資本主義のダイナミズムを半ば肯定しつつ、さらにそれを超えたユートピアを大胆に描いてみせる。『構造と力』と『逃走論』では、それをモデルとして、いわばマルクスの思想をポップ化しようと思ったんですね。だから、一般向けの本として書いたのではないけれど、ベスト・セラーになっても驚くことはありませんでした。ただ、消費社会で使い捨てられることは警戒していた。次々に続編を書かなかったのは才能がないせいですが(僕にはどうしても書きたいという欲望がない、つまりは才能がないということです)、消費されることへの抵抗があったのも確かです。
現在、「難解」な理論や思想はもはや求められていないように見える。しかし、本当にそうか。グローバル資本主義が成立した結果、反資本主義の運動も世界中で激化している。もはや部分的社会工学ではカヴァーできない矛盾が噴出しているわけです。日本でも東北大震災を契機に反原発運動が広がっている。そこで大江健三郎さんや柄谷行人さんが語る原理的な言葉が多くの人々をとらえているのは、注目すべきことです。利口ぶったプラグマティストは「あんなナイーヴなことを言って」とシニカルに構えるけれど、それは間違っている。原点に帰って現実を批判し、別の現実を構想することが、求められているのです。
そのためにも、『構造と力』をヴァージョン・アップしたような新しい地図が必要になっているのかもしれない。とくに、東アジア諸国には、さまざまな伝統がある一方、日本が百年以上かけて受容してきた近代思想や現代思想が十年くらいで一挙に押し寄せている。議論を整理するためにも何らかの地図が必要でしょう。さもなければ、マイケル・サンデルの「ハーバード白熱教室」のようなアメリカの有名大学の「知」がすべてを呑み込んでしまう。それこそ悪しきグローバル化じゃないでしょうか。